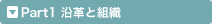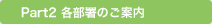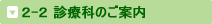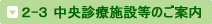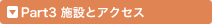TOP >>病院概要2012・本体編 - Part2 各部署のご案内 >>脳神経外科
脳神経外科
科長 若林 俊彦(教授) 7E
進化型手術室 ”Brain Theater“ を擁し、超難度の手術に挑む
当教室の歴史は古く、日本脳神経外科学会の創設者・齋藤眞教授より始まりました。その後、常に脳神経外科の先駆的開発に挑戦し続けています。

診療体制
最新鋭の脳外科手術機器の開発、産学連携による新規治療法の確立、コンピュータシミュレーションモデルを用いた脳内病態の診断・治療の解析による治療成績の向上に努めています。また、救急医療との提携により、医療機関ネットワーク体制の確立により血栓溶解術の迅速対応体制や、脳卒中後の回復期リハ施設や在宅医療との提携による有機的治療体制の確立、更には脳ドックによる予防医療の啓発活動を推進しています。
対象疾患
脳腫瘍グループ、脳血管内外科・脳卒中外科グループ、下垂体・神経内視鏡グループ、機能的脳外科・画像解析グループ、脊髄・脊椎グループなど、適応疾患は多岐に渡ります。
得意分野
脳腫瘍の高精度画像誘導ナビゲーション手術、脳卒中疾患の超高度血管内手術および動脈瘤クリッピング術、神経内視鏡による下垂体腫瘍手術および脳室内手術、機能的脳外科によるパーキンソン病・本態性振戦定位脳手術、難治性疼痛・てんかん手術、脊髄・脊椎疾患の低侵襲手術。脳神経先端医療開発グループによる核酸医療等の先進医療開発。
診療実績
年間の手術数は457件。関連病院(45施設)を含めると10,193件。関連病院を含めた入院患者疾患別では、腫瘍2,780例、動脈瘤2,255例、脳出血3,123例、脳梗塞2,798例、頭部外傷4,444例、脊椎脊髄疾患1,185例、機能的脳外科疾患821例等、総計19,741例(2010年実績)。
専門外来
脳腫瘍、遺伝子・再生医療・細胞療法、血管内手術、機能・てんかん外科、下垂体・内視鏡手術、脊髄・脊椎、末梢神経、脳卒中、神経機能回復リハビリテーション、BMI。
先進医療・研究
当教室は生命科学・医用工学の進歩を取り入れ、本邦初の脳腫瘍遺伝子治療を実施。細胞・再生医療や、脳血管内治療の開拓に尽力するとともに、コンピュータ・画像診断の新技術を導入し精巧な手術法を開発しています。術中MRIやアジア初の導入された高精度ナビゲーションロボ「Neuro Mate」を駆使した進化型手術室(Brain Theater)を擁立しています。