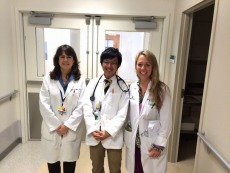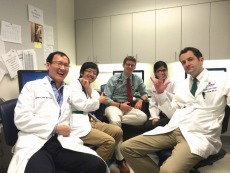帰国報告文 (ジョンズホプキンス大学)
伊吉祥平
2013年3月末から12週間,メリーランド州ボルティモアにあるジョンズ・ホプキンス大学にて病理,循環器,腫瘍内科の実習をさせていただきました。優秀な先生や学生達に囲まれ,とても密度の濃い時間を過ごすことができ,様々なことを学ぶことができました。以下まず今回留学を志した理由について述べたのち,各ローテーションでの実習内容を振り返り報告書とさせて頂きたいと思います。
<留学を志した理由>
今回留学を志願するにあたり,目標としたことが2つありました。一つ目は将来,基礎と臨床をつなぐような橋渡し研究に取り組みたいと考えているため,本場であるアメリカでいかにtranslational research が行われているかを体感すること。そして二つ目は,五年生の夏にアリゾナ大学循環器科をローテートした際に感じた「アメリカの医学生との差」を埋めるべく努力したことが,どれくらい身についているかを確かめることでした。基礎・臨床ともに世界的に名が知れ,優秀な教員・学生が集まっているジョンズ・ホプキンス大学で3カ月苦しみながらも実習できたことは,私にとってとても貴重な経験でした。
<病理(research rotation)>
最初の1ヶ月は病理及び消化器内科で教授をされているProf. Michael Gogginsの研究室でお世話になりました。Goggins Labの研究テーマは膵臓癌の早期診断で,十二指腸腋や膵液,血液などの検体から有益なマーカーを見つける試みを続けておられます。また,CAPS (Cancer of Pancreas Screening) studyなど,いくつかの多施設共同臨床研究を中心となって進めておられます。実習内容としては,ERCPやEUSといった手技を行う患者さんが研究対象としての適応を満たすかどうかをチェックし,患者さんのところに出向いて研究内容を説明して同意をとり,そのまま内視鏡手技を見学し,出てきたサンプルをlabに持ち帰って処理・解析を行うというというものでした。1ヶ月と期間が短く,何か結果を出すことはとても出来ませんでしたが,遺伝子解析の一部や標本作成を経験させていただきました。その他にも,translational
researchに関するランチョンセミナーや,若手の研究発表会などのイベントも多々あり,これらに参加して基礎の先生と臨床の先生が共に集まって議論している様を直接見ることができたのは大きな収穫でした。また,メリーランド州のOffice of the Chief Medical Examiner(監察医の方が所属しておられる部署)に出向いて法医学解剖やAutopsy imagingを見学する機会も得ることができました。
<循環器内科(clinical rotation)>
循環器内科ではConsultのチームでお世話になりました。基本的にAttending1人,Fellow1人,resident1-2人,私というチーム構成で,毎日コンサルトが5-10件ほどあるので,そのうちの1-2件を担当して,問診,身体診察,プレゼンをするという流れでした。チームの方々は皆さんとても優しく,したいことを言えば基本的にさせてもらえるのですが,逆に言わなければただのObservasionで終わってしまう様子だったので,積極的に自分をアピールするよう心がけました。最初の1週間は直接ラウンドの時にAttendingへプレゼンさせてもらえなかったので,Fellowにプレゼンをしてフィードバックをいただくようにしていました。また,カルテの記載も基本的にはFellowとResidentの仕事ということになっていたので,自分で担当した患者さんに関してはカルテを書きFellowにコメントを貰うようにしていました。2週目半ばくらいからは,色々任せてもらえることも多くなったので,積極的に動いて信頼を得ることの必要性を痛感しました。コンサルトが少なく時間が空いたときなどは,CCUや心筋症のチームのラウンドに参加させていただいたり,カテを見させていただいたりすることもできました。
<腫瘍内科(clinical rotation)>
血液腫瘍と固形腫瘍に大きく分かれる腫瘍内科の中で,私は固形腫瘍を扱うグループで実習を行いました。癌患者さんのフォロー中に入院が必要になった症例や,免疫療法など副作用をきちんとコントロールしなければならない化学療法目的での入院症例などを担当させていただくことができました。各チーム隔日で入院を受け入れるシステムになっていたので,私も隔日で1人ずつ担当患者さんを受け持たせていただきました。入院日の問診・身体診察・カルテの記載,翌日のラウンドでのフルプレゼンテーション,その後毎日のフォローとラウンドでのショートプレゼンテーションが主な実習内容でした。また,進行胃癌の患者さんを受け持たせていただいたことをきっかけとして,日本とアメリカにおける進行胃癌に対する治療の違い,特に日本独自でエビデンスが積み重ねられてきた経緯のあるTS-1という抗癌剤についてショートトークをさせていただく機会もいただけました。トライアル中の化学療法など最先端な内容を勉強しなければならない場合もありましたが,発熱や腹痛など一般的な主訴も非常に多く,英語での基本的な臨床力という点では最も勉強になったローテーションでした。
<最後に>
留学前に掲げた目標の達成度合いから,今回の派遣留学を振り返ってまとめとしたいと思います。一つ目の目標として掲げていた「アメリカにおけるtranslational researchを体験すること」に関しては,時間的制約もあり,研究としては殆どなにも出来なかったに等しいですが,研究現場の雰囲気や基礎・臨床間のディスカッションの様子を直接見ることができたのは大きな収穫でした。また,それ以上に,将来そういった現場で活躍するであろうMD-Ph.Dコースの学生達とたくさん知り合うことができ,一緒に野球を見に行ったり,ご飯を食べながら将来像について話をしたりできたことがとてもかけがえのない経験でした。彼らのキャリアに対する考え方や研究に対する姿勢などから刺激を受けましたし,自分の強み・弱みや将来の展望について新たな気づきがありました。二つ目に関しては,自分の成長を実感することができたものの,まだまだ必要とされるレベルには及ばないといったところが正直な感想でした。英語でのカルテの書き方やプレゼンテーションの仕方などは,事前研修で諸先生方の協力の下,十分準備してから渡米することができたのでスムーズに取り組むことが出来ましたし,医学単語を集中して勉強した成果もあり,議論に全くついていけないと感じることはほぼなかったのですが,アメリカでの最終学年に想定される医学知識を知らないことは多々ありましたし,アメリカの4年生と比べるとパフォーマンスにまだまだかなりの差があると感じました。努力すべき方向性は見えてきたと思うので,今回の経験を糧に努力を重ねて行ければと思います。
今回の留学では本当に多くの,かけがえのない経験をさせていただくことが出来ました。医学的知識・英語についてはもちろんですが,積極性やツールとしてのコミュニケーション力など自分の足りてない部分がとてもクリアになりました。これらを改善すべく,日々努力していければと思います。こういった将来に繋がる素晴らしい経験をすることができたのも,粕谷先生,近藤先生,西尾さんをはじめ,本当にたくさんの方々のサポートがあったからこそだと思っております。本当にありがとうございました。
国立台湾大学病院派遣留学報告
稲垣 知希
3月24日から6月13日までの計12週間、台北市中央部に位置する国立台湾大学病院(National Taiwan University Hospital)にて臨床研修を受ける機会を頂戴致しました。台湾を始めとするアジア各国では英語での医学教育が盛んに行われていることはよく耳にする所であり、今回の実習を通じて是非台湾での医学教育や医療を肌で感じてみたかった事と、そういった経験の中から自分自身の医療に対する視野を広げてみたいと思っていた事がこのプログラムへの参加の契機となりました。
家庭医学(Family Medicine)での最初の3週間は上級医・レジデント・研修医で構成されている一つのチームに入り、レジデントと共に毎朝の患者回診を行った後、自ら作成した紙カルテに対しレジデントからフィードバックを受け、また私の方で疑問に思ったこと等を適宜質問し、夕方に行われる上級医による患者回診につくといった毎日でした。バイタルを基本とする日々移り行く患者情報の把握は極めて大切なものであり、例えば全身転移の進行癌に伴う全身管理で一見容態が安定していた長期入院の患者が、翌朝に突然、肝膿瘍由来のsepsisを引き起こした症例などもその余りの急激な容態の変化とデータの変動ぶりに驚かされました。科としての守備範囲は広く、めまいや肺炎など多岐に渡るcommon diseaseから、高血圧・糖尿病などの種々の背景疾患に至るまでを主に扱い、私は各症状・疾患に対する系統的なアプローチや病態の理解に努めようとしておりました。それでもやはり臨床では全てが教科書通りとはいかず、めまい症状で入院した患者さんに対し、それが頭頚部の器質的疾患に由来するものなのか、低灌流に伴う虚血によるものなのか所見や検査結果と睨み合いながら研修医の先生らとともに診断に難渋した事も思い出されます。
耳鼻咽喉科での3週間は、外来や手術室を中心に滲出性中耳炎や真珠種、耳硬化症などの疾患を抱えた患者を診る機会が多くありました。それ以外にも、台湾古来の嗜好品であるビンロウを噛む習慣がまだ一部で残っているため、大変多くの口腔内癌や咽頭癌患者が入院していたのも教科書通りだなといった印象を受けました。また研究室にも案内して下さり、そこでマウスを使った蝸牛の剖出や免疫組織化学染色などを指導して頂きました。
続いて計4週間ローテートした腫瘍内科(Oncology)では、担当患者を7年生の台湾学生とともに診ていく形での実習となりました。各患者は腫瘍切除後の術後化学療法のために入院することが多く、退院までの間にカルテに書かれている現病歴や既往歴、画像所見等を教科書的な知識と絡めて理解するとともに、出来る限り臨床に即した教科書以上の最新の知識も得ようと努めておりました。診察に関しては鑑別のための問診・所見を積極的に取りにいくというよりは、化学療法に伴う一般的な吐気、貧血などの副作用から各抗癌剤に特異的な副作用まで、幅広い知識を念頭にした患者管理の側面が強いものとなりました。実際経過観察中に容態が芳しくなかったある患者では、抗癌剤であるifosfamide投与後の急性感染を疑うあまり、合併症として報告されているFanconi症候群を呈したことに気付けず愕然するとともに、改めて副作用を知っていることの重要性にも気付かされました。その他、コンサルト業務に同行させて頂いたり、胃がんに関するプレゼンテーションをする機会を頂いたのもよい経験となりました。
最後の2週間は麻酔科において中心静脈カテーテル、気管挿管などをレクチャーして頂いたり、Pain clinic外来にて線維束筋痛症や三叉神経痛の患者に対する解剖学的な知識を基にした慢性疼痛の緩和の実際を教えて頂きました。麻酔科をはじめとする全ての科の研修を通じ、どの科においても各医師の優れた英語力や、全てが英語記載されているカルテあるいはプレゼンテーションに圧倒されることが多く、台湾の徹底した英語教育の片鱗を見たように感じます。国立台湾大学に通う学生とも多く話す機会がありましたが、誰しもが当然のように堂々とした英語でコミュニケーションを取る姿には驚きを禁じ得ませんでした。また実習を通じて台湾の医学教育もさることながら、医療制度、そして政治問題まで理解を深めるにつれ、日本やアメリカの制度、文化を取捨選択し積極的に取り入れながらも、中国との間で揺れ動く台湾の現在が浮き彫りになって来るよう感じました。
これらの経験を振り返り、私自身何を得ることができたかと考える時、自分の医療に対する姿勢の変化に気付かされます。それは例えば患者と向き合う上で疑問が生じた際に出来る限りそれに関する新しい知識を自分で調べて得ようという意識であったり、英語が当然のコミュニケーションツールとして日本以外のアジアで自分の想像以上に使われている現状を目の当たりにして、英語に対する思いを新たにしたことであったり、そして何よりも台湾での医療を肌で感じることができた事は、今後私が日本での医学・医療と関わる中で今後大きな意味を持ってくると信じます。
このような貴重な機会は国際連携室の先生方及び国際交流・留学生掛の方々の多大なご尽力とご支援ではじめて実現できたものです。粕谷先生、近藤先生を始めとする国際連携室の先生方、国際交流課の西尾さん、現地で出会った国立台湾大学の温かな先生方、学生達、クラークさんや看護師の方々、そして家族にこの場を借りて心から感謝の意を表したいと思います。本当にありがとうございました。
Tulane大学派遣留学報告
横田 裕史
私は4年生の夏、先輩に勧めていただいたのをきっかけにこの派遣留学制度に挑戦することを決めました。それまでの4年間は部活一辺倒であったため、この挑戦は私にとって真新しいことばかりの非常に刺激的なものでした。私が派遣していただいたのは、New OrleansにあるTulane大学です。アメリカの他の都市とはまったく異なる、アメリカとヨーロッパとアフリカを足し合わせたようなこの街で過ごした3カ月間は非常に充実したものでした。
1ヶ月目はHematology/Oncologyで実習を行いました。この科は日本で言うところの血液腫瘍内科で、血液疾患に加えて、その他全領域の化学療法を一手に引き受けている科です。私が所属したのはその中のconsultチームで、主な実習内容は、他科からのconsultがあった際に、上級医と一緒に患者さんの所に行き、所見を取って、治療方針を話し合うといったものでした。その他にも、病理部、放射線科、各内科、外科とのカンファレンスが毎日のように開かれていたり、血液標本を読む練習をさせていただいたりと、非常にアカデミックな実習をさせていただいたように感じます。何より小グループで一人一人の患者さんを丁寧に診ていくというこの科のスタイルは、英語やアメリカの病院に慣れるという意味でも1ヶ月目の私に合ったものでした。
2ヶ月目は呼吸器/ICU科を選択しました。アメリカには腫瘍内科や感染症科が別にあるため、呼吸器内科の対象疾患は日本とかなり違っています。Tulane大学でも呼吸器科は、癌や感染症を除く呼吸器疾患を扱う呼吸器consultチーム、MICU(内科系ICU)の管理および全病棟の呼吸管理されている患者さんを診るICUチーム、睡眠時無呼吸症候群など睡眠障害を扱うSleep medicineチームの3チームに分かれていました。この科には日本人アテンディングの先生がいらっしゃったこともあり、私は全チームに関わることのできる非常にフレキシブルな実習をさせていただきました。特にICUチームでは担当患者さんを振り分けてもらい、毎朝自分で所見を取ってプレゼンテーションを作り、回診時にチーム全員に対して発表するという流れも経験できました。1ヶ月目に比べるとdutyも増え、少し忙しい月になりましたが、患者さんもスタッフの方々も皆協力的で、満足度の高い非常に充実した実習ができたと思っています。
3ヶ月目はあまり実習可能な科が無かったこともあり、前半後半2週間ずつ異なる科をローテートするやや変則的な月になり、前半は放射線科をローテートしました。この科はローテートすることが決まった数時間後には、実習のdutyやスケジュールを送信してくれるという非常に学生実習に力を入れている科で、実習内容も病院の中央部門ということもあってか、他の科の実習とは完全に趣の異なるものでした。具体的には10人ほどの現地学生と講義を聞いたり、その中で小グループに分かれて読影の見学やディスカッションに参加したりと日本でのポリクリⅠに近い内容だったように思います。そのため、現地学生と交流する機会もたくさん持つことができました。先生の差し入れのドーナッツをほおばりながらグループの仲間と読影に取り組む毎日は、もともとやりたかったこととは違ったものの、思いのほか充実していました。学生のdutyとして症例を一例選んで最終日にパワーポイントを用いてプレゼンテーションをするのですが、拙い英語で未熟な内容の発表をした私に大きな拍手と称賛をくれたあのクラスの温かい雰囲気は忘れ難い思い出です。
最後の2週間は内分泌内科を選択しました。内分泌内科の学生実習は専ら外来実習で、私も患者さんの身体診察を担当させていただきました。患者さんはほとんどの方が糖尿病、稀に甲状腺疾患や骨粗鬆症の方が混ざるというぐらい糖尿病の患者さんが多かったため、私の仕事は専ら神経診察でした。実習内容こそ単調でしたが、その分余裕があり、先生方からたくさんフィードバックをもらえたり、患者さんと患者背景にまで踏み込んだ会話ができたりと他の科とは違った学習ができたと思います。
また、実習外ではありますが、名古屋大学の卒業生でTulane大学教授として活躍された故有村章先生の研究室を訪ねたのも私の心に強く残っています。有村先生の残した業績、アメリカの研究のスケールの大きさ、そしてそれを維持発展させていくことの魅力と苦労を奥様のお話を伺いながらのぞき見たあの日は間違いなく3ヶ月間で最高の一日でした。
3ヶ月間を通して私は文化面、医療面共に日本とアメリカを比較する機会を多く持つことができました。私は、この派遣留学実習での最大の収穫を自分の中に芽生えた新しい価値観だと考えています。正直な印象として実際に行われている医療に日本とアメリカでそこまで大きな差があるとは感じませんでした。寧ろ日本のほうがより優れていると感じる場面も多くあったように思います。専門職の種類も日本とは比べられないほど多く、それが業務の軽減につながっている印象は受けました。それでもその仕事の質が日本の医師やコメディカルの方々よりも高いかというと、決してそのようなことはないと感じたのです。もちろん、業務が軽減されている分学生教育やカンファレンス、研究に時間を割くことができていたり、consultの敷居が低い分、患者さんも容易に専門家の治療を受けられたりとポジティブな面も見受けられましたが、それが医療費の高騰につながっていたりとどの国も同じような問題を抱えているということを実感できました。幼いころから抱いていた外国、特にアメリカに対する盲目的な憧れではなく、より客観的にものを見られるようになったことは大きな収穫だと思います。その一方で世界中の国から優秀な人材が集まっていることや、研究の規模の大きさなどやっぱりアメリカにまた来てみたいと思える材料も見つけられました。
人との出会いも貴重な財産になりました。病院の先生方は、レジデントからアテンディングまで全員教育的で、質問した時はもちろん、黙っていても私がわかっていなさそうと判断するやいなや、その場で講義を始めて下さりました。選択肢ができるかどうかではなく、やるかやらないかだったのも印象深いです。現地の日本人の先生方にもお世話になりました。慣れない土地で不安を抱えていた私たちにとって、プライベートで付き合ってくださった先生方の存在はとても大きなものでした。自分たちよりもはるかに先を進んでおられる日本人医師、研究者の方々のお話は、ほかの国の先生方とはまた違った面で私の心に響くものでした。そして欠かすことができないのが、現地で出会った学生たちです。病院内では一番身近な先生として、病院外では友人として付き合ってくれる彼らなしでは、今回の留学は成立しえなかったと思います。特に名古屋大学に交換留学生として来た、もしくは来る学生たちには毎週のように連れ出してもらい、実習とはまた一味違う学習ができました。
振り返ってみてもこの派遣留学に挑戦すると決めた日から、留学を終える日まであっという間に時が過ぎたように感じます。それだけ一日一日が重みのある充実した日々でした。留学に行ったから学べたこと、日本で実習しなかったから学べなかったことどちらもたくさんあるとは思いますが、私は留学したことを全く後悔していません。今回得た経験や価値観、そして人との出会いは私にとって貴重な財産だと信じています。今後も多くの後輩がこのような経験ができることを強く願っております。最後になりましたが、今回の留学にあたって大変お世話になった全ての方にこの場をお借りして感謝申し上げます。
グダニスク医科大学
加藤寛之
私が最初にこの名古屋大学の留学プログラムに参加しようと思ったのは、純粋に英語力を向上させたいと思ったのがきっかけでした。世界共通語として、とりわけ医療の世界では避けては通れない英語に対して壁を取り去ることが、医学の勉強と同等かそれ以上に、学生の間にやっておくべきこととして重要だと思ったからです。それは、日常会話レベルではなく、専門用語が飛び交う中で物事を考え、発言できるレベルです。留学先を選ぶにあたって、最初はアメリカ、イギリス、オーストラリアといった、英語を公用語とする国ばかりを考えていましたが、グダニスク医科大学のEnglish Divisionの話を聞いてからは、選択肢としてポーランドも考えるようになりました。English Divisionでは、ヨーロッパ内を含む世界中の国から学生が集まり、一学年100人程度で6年間英語の医学教育を受けることができます。グダニスクへの留学では、このEnglish Divisionの学生に混ざり、一緒に英語で実習をすることができるので、世界中の様々な国からの学生と交流を深めることが可能です。さらに、グダニスク医科大学は外科系の科がどこも症例数が多いので、手術中にいろいろな手技を経験させてもらえるということも、外科系志望の私にはとても魅力的でした。英語の環境、そして外科手技の経験という二つの大きな長所を持ったグダニスク医科大学が、他のどの提携校よりも自分の目標に適した環境であるということは、留学を終えた今思い返しても、間違いありませんでした。
病院実習では主に外科系の科として、心臓外科、一般外科、脳神経外科を、また内科系の科として一つだけ、generalに学べる家庭医学を選択し,計12週間実習しました。
心臓外科では他の学生はおらず、英語の話せる先生がマンツーマンで私の担当をしてくださいました。グダニスク医科大学では心臓移植を行っているということでしたが、結局私の実習期間中には一件も行われず、貴重な経験を逃したという残念な気持ちでいっぱいでした。しかし、心臓外科では基本的に、冠動脈バイパスと弁置換を毎日どちらかは行っており、興味深い多くの手術を術野から間近で見学することができました。特に、バイパス2本+大動脈弁置換という大きな手術はとても記憶に残っています。手術中は担当の先生が英語で解説を入れてくださり、とても理解が深まりました。
家庭医学ではEnglish Divisionの学生のクラスに参加することができました。授業形式で、内容は循環器・呼吸器などの臓器別から精神科、さらには肥満といった幅広い知識をカバーしています。私の参加したグループは大半がアメリカ人で、他にはカナダ人やスウェーデン人もいました。授業と言っても受け身のものではなく、学生が常に先生に質問を投げかけ、時には先生と討論にもなるようなディスカッションに近い授業です。ポーランドにいながら、nativeのディスカッションに参加できたのは大変貴重な経験でした。時には学生の方から、日本ではこういう時どう対応するのか、日本の現状はどうかなどの質問が飛んでくることもあり、自然とそのディスカッションに参加することもできました。
一般外科では、学生は私一人のみであったので、私の希望にできるだけ沿った形での実習を組んでいただけました。主にオペの助手に入り、縫合やステイプラーなどの手技を経験させてもらうことができました。オペの内容としては、虫垂切除などの比較的簡単なものから、膵臓全摘や副腎全摘、さらには外傷など、5年生のポリクリでは見ることのなかった手術も多くあり、非常に興味深かったです。膵頭十二指腸切除が最も印象的で、膵頭部切除の他に、胆摘、膵管再建、胆管再建を淡々とこなす教授の技術の高さに、深い感銘を受けました。また、日本ではそれほど行われていない肥満に対する治療としての胃切が、毎日行われていました。手術は内視鏡で行われますが、毎日行われているので先生方は慣れた手付きでオペをされていました。
脳神経外科では基本的にオペ見学で、現地の学生は実習期間が終わっていた時期だったので学生は私一人でした。日本では脊髄の手術は整形外科が行うところが多いですが、グダニスク医科大学では全て脳神経外科が担当しているので、一日に6,7件は脊髄のオペが入っていました。僕の希望で出来るだけ脳のオペに入れるようお願いしたので、日本の脳外科に近い形で実習を進めることができたかと思います。オペ中は主に開頭と閉頭時に術野に入って、創部の止血や縫合を経験させてもらいました。脳腫瘍、中大脳動脈瘤クリッピング、クリッピングの難しい動脈瘤に対して内頸動脈近位部閉塞術など、いろいろな手術を見ることができましたが、脳室内視鏡による脳腫瘍生検は非常に興味深かったです。グダニスク医科大学では脳室内視鏡は先月1症例目を始めたばかりで、今回が2症例目だったそうです。貴重な瞬間に立ち会うことができました。
グダニスクでの12週間の実習を通して、本当に貴重なかけがえのない経験をすることができました。特にグダニスクの特色であるEnglish Divisionの学生との交流は、私の当初の目的である英語力の向上に大きな成果をもたらせてくれました。スウェーデンを始めとして、イギリス、オランダ、スペイン、イタリアなどヨーロッパ各国からの学生だけでなく、アメリカ、カナダ、インド、ベトナム、サウジアラビア、アフガニスタンなど世界中からの学生との触れ合いを通して、アクセントの異なるいろいろな「生きた」英語を毎日浴びるように聞きながら、日本人との様々な価値観や考え方の違いにも気付くことができました。また、どの外科系の科も毎日オペがあり、多くの症例を目にすることで、日本の術式は世界のスタンダードに乗っ取って行われているということを実際に目で見て実感するとともに、若干の手技の違いも垣間見ることができました。
このような貴重な経験をすることができたのも、粕谷先生、近藤先生、西尾さん、グダニスクとの交流を始めてくださった若林先生やWoźniak教授、研修会でご指導いただいたフロンティア会の先生方、現地での生活について情報を頂いたグダニスクOBの先生方、励ましあった同級生、いろいろな面で支えとなってくれた家族、そしてこの留学プログラムに関わって下さった全ての方々のお陰であり、深く感謝しております。学生生活も残りわずかとなりましたが、今回の留学で得た何にも負けない積極性を、今後の人生に生かせるよう努力していきたいです。本当にありがとうございました。
米国Tulane大学医学部留学レポート
玉木 香菜
私は4月から7月に掛けての三ヶ月間、米国Tulane大学に派遣して頂きました。Tulane大学のあるルイジアナ州New Orleansは、全米屈指の観光地として栄え、人口の約8割を黒人が占める土地柄、彼らの大らかな性格が街の雰囲気にも現れ、常にジャズを中心とする音楽の流れる陽気な街です。実習を開始した4月からかなり気温と湿度が高く春にも関わらず晴れた日は強い日差しの降り注ぐ土地でした。
・各科での実習について
留学一ヶ月目は腎臓内科を選択し、他科からの診察の依頼を受けるconsult teamの一員として実習をさせて頂きました。
nephrology consult teamは腎臓内科のFellow Dr.1名が毎月交代で運営を担当し、Attending Dr., Resident, 学生で一日1~2回の回診を行って依頼のあった患者さんの管理を行っています。
私はfellowの先生の指示の元、毎日約1~3名の担当患者さんを与えて頂き、回診の時間に合わせて患者さんの情報収集・問診を済ませ、回診時、attendingの先生が患者さんを診察する前にプレゼンをさせて頂きました。また、attendingの先生に課題を出して頂き後日それについてディスカッションとミニレクチャーをして頂いたり、nephrologyやinternal
medicineのカンファレンスに参加する機会もありました。残念ながら私以外に学生が居なかった為、実習中に現地の学生と交流する機会はありませんが、腎臓内科の先生方は親切で優しく、チームは不定期で回診に参加するresidentの先生数名がいらっしゃらなければAttending Dr, Fellow Dr, 私の3人なのでほぼマンツーマンで実習を行っており、プレゼン準備では疑問点や伝えるべき重要な情報などはfellowの先生に、プレゼン時はその都度Attendingの先生からプレゼンの仕方から患者さん毎のAssessment
& Planについて細かくご指導頂きとても贅沢な環境で勉強する事が出来ました。
担当患者さんは最初の二週間は主に何らかの理由で既往として腎不全(CKD)で血液透析を行っており、入院中の腎機能・透析の管理を依頼された方々を中心に担当させて頂き、CKDのマネージメントや透析について多くを学ぶ事が出来ました。実習開始当初は、今日の透析のオーダーはどうすれば良いか?という質問にほとんど答える事が出来ませんでしたが、徐々に腎臓内科の先生方がどのようなプロセスで患者さんの管理、透析のオーダーを考えておられるかがわかるようになりました。後半の二週間はAKI(急性腎障害)の患者さんを割り振っていただきました。主に何らかの慢性疾患による免疫力低下により発症した原因不明の感染症による入院中に腎機能が低下した方が多かったこともあり、背景が複雑な方が多く、全体像を把握した上で腎機能のマネージメントを考えるのには苦労しましたが、これで日本においても日常的に遭遇しうるCKDとAKIの管理を両方学ぶ事が出来、大変為になりました。その他、何らかの慢性肝機能障害を背景にHepatorenal
Syndrome(HRS, 肝腎症候群)を起こした患者さんやSIADHや腫瘍崩壊症候群などによる電解質異常、リチウム中毒などの症例も経験することができました。特にHRSの方は、liver transplant candidates であるか否かが透析を行うか決定する上で最重要であり、移植が盛んなアメリカならではという印象を受けました。
2ヶ月目はAllergy, Immunology and Reumatology departmentにて実習をさせて頂きました。当科での一週間の大まかなスケジュールは、月・金は論文抄読会、カンファレンスに出席し、残りの火~木はクリニックで実習しました。
扱う疾患は主に喘息、鼻炎、皮膚炎、食物アレルギー、CVID(common variable immunodeficiency; 分類不能型免疫不全), specific polysaccharide antibody deficiency
syndromeなどの免疫不全の診断症例などが中心であり、clinicもprimary careに近い雰囲気を持っていました。実際火・水の外来はTulane hospitalではなくOchsner という別の病院のprimary care clinicで実習を行いました。
実習の内容としては、まずFellow Dr.と一緒に患者さんの問診・身体診察を行い、Attending Dr.と治療の検討を行い再び患者さんとお会いして治療方針などの説明を行うという流れでした。また、日本では見る機会の無かったskin
test(prick, intradermal)やallergen-specific immunotherapyなども多く見学する事が出来ました。
残念ながら学生のみで問診をとる機会はありませんでしたが、日本においてアレルギー性の鼻炎や皮膚炎、じんましん、食物アレルギー、喘息などのcommon diseaseの管理は大学病院での実習ではなかなかきちんと学ぶ機会がなかったのでとても勉強になりました。特にアレルギーの診断において、日本ではすぐに血液検査をオーダーするという印象を持っておりましたが、こちらはまずskin
testを行うのが主流であり、そのような日本との違いは興味深かったです。
また当科での実習は米国の医療システムや医療を取り巻く環境を垣間みる機会ともなり、公衆衛生にも興味がある私にとって大変貴重な経験となりました。
Tulane hospitalはmedicareの患者さんを受け入れているという事もあり、患者さんの多くは黒人で低所得の方も多く、治療への金銭的な制約があったり、自分の病気に対しての理解や意識が低い方も多く見受けられました。一方Ochsnerは大手の私立病院にあたる病院で患者さんはほとんどが白人でTulane hospitalとは全く雰囲気の異なる外来でした。両者の病院によって先生方の対応が異なるという事は全くありませんでしたが、保険の種類や社会的背景によって出来る事が限られてしまったり、患者さんの考えも異なったりと、人種のるつぼであるアメリカならではの経験が出来たのではないかと思います。
また、当科の先生方はほとんど女性で、子育てしながらfellowshipを行っている先生も多く、こちらでの女性医師のキャリアパスやワークライフバランスについてもお話を聞く事が出来ました。
最終月前半の二週間はCCU/Cardiology consultにて実習させて頂きました。
CCUでは二年目のResidentと一年目のInternの先生が二人一組でチームを組み、患者さんを管理しています。
一日の流れは、朝7時にCCUに行き新しい患者さんの情報を集め、Residentのpreroundに同行します。その後CCUに帰り、8時頃から今月のCCU/consult担当のFellow Drにチーム毎に報告を行い、治療に対するアドバイスを頂きます。9時頃からAttending Drがいらっしゃるので、まず皆で座って全ての患者についてプレゼンを行い、その後roundに向かいます。
私は初日はその内の1チームに入れて頂き実習させて頂きましたが、その後は各チーム3日に一度回ってくるon
callの担当residentにその日来た新しい患者さんを割り振って頂き、ERでの問診やAttending Drへのプレゼンをさせて頂いていました。
担当させて頂いた患者さんはほとんどがERに胸痛を主訴に来られるので、ERで一人で問診を取る機会も頂きました。今回の留学では残念ながら希望していたERでの実習が出来なかったので、とても良い機会となりました。 その他、経食道的心エコー(TEE)などの検査を見せて頂く機会も頂きました。
CCU/consultが管理する症例は主に胸痛を主訴に来られた患者に対するacute colonary syndromeのルールアウト・管理や高血圧の管理でしたが、典型的なACSの他にも大動脈解離やmyxoma、たこつぼ型心筋症などの疾患も診る事が出来ました。
最後の二週間はRadiologyにて実習させて頂きました。
当科のローテーションは一度に回る学生の数も多く、講義などきちんと組まれている為とても学生らしい実習内容でした。実習は、学生一人一人が決められた順に従い胸部レントゲン、CT.、超音波、MRI、脳神経の画像読影及びinterventional radiologyのブースを毎日一つずつ、各ブースが3-4人ずつになるよう回ります。画像読影は担当のfellow doctorが読影をする横で一緒に画像を見ていきます。先生方は一症例ずつの各検査の基本的な読影方法や診断のポイントなども交えながら丁寧に解説してくださいました。またFellow
DrはAttending Drに対して一人で予め読影した画像について自らの診断をプレゼンしていく際、Attending Drから更に詳しい解説や知識のレクチャーがありました。Attending Drからは学生に対してもその画像をどのように診断するかや疾患に対する知識についての質問がなされ、ディスカッションも行われました。質問への回答には疾患に対する知識と細かい解剖学の知識が要求されると共に、その知識を説明する為の医学英単語などの英語力も必要であり、日本語では説明出来るが英語では答える事が出来なかった事もあり、まだまだ勉強不足である事を痛感致しました。同時に先生方の幅広い知識には感銘を受けました。
講義もほぼ毎日行われ、脳神経、筋骨格系、胸腹部の画像読影の知識を深める事が出来ました。
更に学生には2週目に一症例について5-10分のプレゼンを行う事が義務づけられており、英語での症例報告を初めて行う機会も得る事が出来ました。
最終日にはそれまでの講義およびFelson's principles of rentogenologyの内容に関するテストがありました。
それまでの2ヶ月半は全て内科を選択していた為、最後に少し趣の異なる科を経験出来た事のは新鮮であったと共に、英語での画像読影も経験する事が出来,最後の二週間の実習もとても充実した者にする事が出来ました。
・留学全体を通して
今回の派遣留学を通して、多くの医学的知識・経験を得る事が出来ました。担当患者を割り当てられ、ファーストタッチから上級医への初回のプレゼンまで行ったので各患者、疾患に対しての知識がより深まった。また英語での問診、プレゼン、ディスカッションは、英語でのそれらの方法を習得出来ただけでなく、より効率的でオーガナイズされた問診やプレゼンをするにはどうすれば良いか、効率的な病歴を取る方法など、日本での臨床にも大いに役立つ経験でした。更に、病棟、外来、ER,検査部など満遍なく米国の医療現場を見る事が出来、日本とは異なる医療制度について広く学べた事で、改めて日本の医療の優れている点・問題点を認識・再考する事が出来ました。また、アメリカという多様性に富んだ社会で多くの患者さんと話し、その社会的背景を垣間みた事で、患者一人一人の社会背景まで考慮して治療方針を考えていくという経験ができました。
更に、医学的知識のみならず、現地学生や他国からの留学生と交流する機会を通して、彼らの学業や医療に対する並々ならぬ努力、情熱に触れる事が出来、自分のモチベーションの向上につながりました。また、海外で活躍する日本人医師・研究者の先生方とお話する機会は、彼らの海外で働くという事のメリット・デメリット、苦労・楽しさを踏まえた経験談を通して自分のキャリアパスを再考するきっかけともなりました。加えて、多様な人種・社会的背景・思考が混ざり合う環境で生活・学習した事で、より広い視野・知識・心で他者の意見に耳を傾け、それを受容し、共に解決策を試行錯誤するという事を経験出来た事は人間的な成長につながりました。この経験は日本というほぼ一つの民族で構成されている国においては経験する事が出来なかったであろうし、将来患者さん一人一人に対して、彼らの社会的背景まで含めた視点から疾患を診て、彼らや他の医療職の方々と共に協力して治療を進めるという医師の仕事を行っていくにあたり、得難い経験になったと感じています。
最後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださった名古屋大学の先生方、国際連携室の皆様、学務課の皆様、惜しみないサポートをして下さった先輩方、同級生の皆様、家族、英語もつたない私を暖かく迎え指導して下さったTulane大学の先生方、スタッフの方々、現地学生の皆さんに心より感謝致します。
University of Pennsylvania留学を終えて
高宮城冴子
アメリカ留学は、自分への挑戦そのものでした。沖縄県で生まれ育った私にとってアメリカはすぐ横のフェンス越しにある身近な国でしたが、医学を学ぶ上ではいつも文献の向こう側にある医療超大国でした。そのような環境下で自分がどれだけのことが出来て、どれだけ成長できるのかを知るために、この度Pennsylvania大学に2ヵ月間留学させていただきました。
Pennsylvania大学は、アメリカ独立宣言の地であるPhiladelphiaにあり、高層ビルが立ち並ぶ大都市の中に古くからのレンガ造りの建物が混在するとても美しい街でした。たった1人で降り立ったアメリカでしたが、Phillyという愛称で親しまれるPhiladelphiaはどこか安心感を与えてくれる温かい土地でした。そんな伝統的な街の、全米最古の病院であるPennsylvania HospitalのNICU(新生児集中治療室)と、全米最高の小児専門病院であるChildren’s Hospital of Philadelphia(通称CHOP)の小児感染症科にて1ヵ月ずつ実習させていただきました。
実習の始めのうちは、何もかもに圧倒され自分の無力さを痛感する日々でした。NICUでは担当患児が与えられ、知識不足と医学英語や略語に苦戦しながらも終えた最初のたどたどしいプレゼンテーション。先生に、”So, what do you want to do her today?(じゃあ、君は今日この子に何をしたいの?)”、と聞かれて頭が真っ白になったのを覚えています。しかし、毎日担当の子を診察するにつれ、自分にしか見えてこない点がたくさん出てきて、日に日に自身のAssessment & Planを立てられるようになりました。「低血糖症状がなくなってきたので栄養の注入時間を1時間から30分に変更したい」、「黄疸が見られるのでビリルビンの値を測りたい」、先生は私のプランを妥当だと思ったときは実行させてくれました。そうして一ヵ月間診させていただいた赤ちゃんは日々成長し、管も一本ずつ抜けていって、最後にはお母さんの母乳を飲む練習をするまでになりました。インキュベーターから出た赤ちゃんを受け取ったお母さんの顔は今でも忘れられません。
次の実習先であるCHOPの小児感染症科では、受け持ち患児をずっとフォローしたNICUとはうって変って、Consultチームの一員として毎日何人もの患者さんを次々と診ていかなければなりませんでした。アメリカでは医学生にFirst Touchさせるのが当たり前で、患者さんについての情報がほとんどない状態での問診からスタートし、身体診察、Assessment & Planを自分で立てます。 それをチームのRound(回診)のときにプレゼンして、Attendingの先生の鋭い突っ込みを受けつつ、チーム全体で私が立てたPlanを検証します。小児病院として数々のジャーナルで第1位に輝くCHOPには、世界中からあらゆる問題を抱えた子供たちがやってきていました。リウマチ熱後の舞踏病、結核、マラリア、HIV、寄生虫…日本では教科書でしか見た事がないような感染症ばかりで、毎回論文を検索してもなかなかPlanが立てるのが難しい症例ばかりでした。文献検索の方法やカルテの書き方は一緒にローテートしていたPennsylvania大学医学部4年生の女の子から教わりました。彼女はとても優秀で、同じ医学生として学ぶ点が多くあり、刺激的な存在でした。
そんな精一杯な実習の日々を屈することなく送れたのは、寮の友達の存在が大きかったです。私が住んでいた寮International Houseは、Pennsylvaniaで学ぶ大学生が入れる寮で、私は6人の女の子たちとルームシェアしながら暮らしていました。寮に帰ると、”Hey, Saeko! How was your day today?”と迎えてくれ、みんなで一緒に料理を作る日々でした。世界各国の大学生と夜な夜なあらゆる分野の議論をするのは、何とも言えない貴重な時間でした。日本代表として矢面に立つ機会が多く、日本という国について客観的に考える機会を与えてくれたと思います。
私がこの留学を通して学んだことを一言で表すと、「視野を広げるだけでなく、視点を増やす」重要性です。視野を広げているだけのうちは、視点は変わっていません。アメリカの生活、アメリカの医療に自分から飛び込んで溶け込んでいって、初めて得られる視点がありました。世界各国の大学生との熱い討論の末に見えてくる世界、そして日本の新たな側面を知りました。そして、そのためには、日本人的な謙虚な自分を捨てて思い切ってなんでも挑戦する強さが必要でした。日本人1人で留学したことは、常に不安と隣り合わせの日々でしたが、それと同時に自発性と積極性が求められ、人間的にも大きく成長することができたと思います。私は最初に「自分がどれだけ成長できるのか」を知るために留学したと書きました。留学は自分を一瞬で変えてくれる魔法箱のように思えますが、私がこの経験をどう活かしていくかで初めて今回の留学の意義が深まるのではないかと思います。今回のこの素晴らしい経験を今後必ず何らかの形で還元していきたいです。
最後に、今回の留学に携わって下さった名古屋大学の先生方や先輩方、国際連携室の皆さん、Philadelphiaで出会った多くの人々、そして力強い助言を下さった西崎先生に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

Children’s Hospital of Philadelphia(CHOP)の小児感染症科にて

寮International House Philadelphiaにて
国立台湾大学留学記
佐橋秀紀
私は台湾大学において、3ヶ月の間、6週間ずつ皮膚科と形成外科で実習致しました。
まず、皮膚科では、早朝からのモーニングレクチャーに始まり、その後外来見学または病棟の回診をして、午後は処置を手伝わせて頂いたり、カンファレンスに出席しました。先生は逐一私の希望を確認して下さり、望むものに対してはきめ細かいご指導を頂きました。こちらでは、美容外科の需要が高く、街中には多くの美容外科を掲げた医院をみることができ、大学病院でも美容外科を扱っており、いろいろ見学をしたり、処置を手伝ったり日本ではできない体験ができたと思います。
形成外科では、毎週月曜に患者を数名紹介してくださり、それらの症例について、金曜にプレゼンを行い、それ以外の日は手術を見学したり、抄録会に出席したりと日本のポリクリに近い形で実習しました。中国語の言葉の壁もありましたが、現地の学生の優しい心遣いのおかげで、充実したものとなりました。
台湾では、国民一人一人に識別番号が割りあてられ、電子カルテの共有が本格化しており、そのデータを国や民間企業がビックデータとして解析すれば、いずれは診断や治療方針の決定はコンピュータで行うことができます。実際に、世界を見渡すと、IBMが人工知能であるワトソンを医療に生かす試みが実用段階であります。その結果医師の負担や医療ミスが減るので、この点に関しては、日本も柔軟に対応してもらいたいものです。
台湾は九州本土と同じくらいの国ですが、観光資源が多く、全てを周るには3ヶ月では物足りないほどでした。また、あちらでは家庭で料理をほとんど作らないため、一人暮らし用のマンションにはキッチンはありませんし、スーパーマーケットはほとんどなく、その代わりに屋台や食べ物の路上販売、飲食店がひしめいています。値段も安く、味も良いです。
台湾でのベストグルメは、蘇抗(http://www.suhung.com.tw/)の東坡肉(トンポーロウ)で、これを食べに台湾に行こうと言わしめる味です。さらに、人々も親切かつ穏やかで、細かいことを気にしないため、本気で台湾移住を考えたことも何度かありました。
これを読んでいる後輩がいれば、ぜひ台湾で実習してもらいたいと思います。
多様な働き方が可能になった現代で、今後どのような生き方を選択するのが自分にとってベストなのか考える機会を得られることでしょう。
このように、意義のある実習をさせていただいたのは、数多くの方々のおかげであり、留学の機会を与えてくださりその前後にわたって留学をサポートしてくださった国際交流室の皆様を始め、私の留学に関わる全ての方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。間接的にせよ何らかの形で還元できるよう、一層努力したいと思います。
ウィーン医科大学留学体験記
山根 一輝
私はオーストリアのウィーン医科大学において3ヶ月間留学させて頂いていました。私がこの留学プログラムに応募した理由は、日本と異なる価値観に触れ、海外の医療やシステムに対する理解を深めることだけでなく、全く知らない土地でどれ程のことを学びとり、どれ程広く深い人間関係を築くことが出来るか挑戦してみたいという気持ちがあったからです。ウィーン医科大学では、心臓外科、脳神経外科、救急をそれぞれ一カ月ずつ実習させて頂きました。
一番始めの一カ月でローテートさせて頂いた心臓外科では医療教育が日本と大きく異なっていることを痛感しました。ウィーン医科大学では1学年人数が日本よりも遥かに多く600人ほどの生徒がいました。そのため、生徒はより主体的に学ぶ姿勢が求められました。心臓外科ではとても多くの手術が行われ、また常に医師は緊張していたためより顕著でした。私はまず朝ミーティングに参加し、その後学生の仕事である病棟患者と新患の採血と心電図の記録を行った後、自身が興味のあるオペを自由に見学するという一日でした。このように日本のポリクリの一日とは全く異なっていたため初めは慣れず、戸惑う事も多くありました。しかし、慣れてくるにつれ、先生方の動きを見て手技を見学し、また回診に同行し質問をするというように学ぶチャンスを自ら見つけ自分の物にしていく姿勢が身につき、将来につながるとても良いスキルを手に入れることが出来たと思います。さらに、心臓外科の実習中、現地の学生や様々な国からの留学生と知り合う事ができ彼らとは残りの二ヶ月間病院外で交流を深めました。英語で一から人間関係を構築することが出来、自信につながりました。
次の一カ月でローテートさせて頂いていたのは脳神経外科でした。脳神経外科は自分の志望科であったため、とても意気込んで実習に臨みました。脳神経外科の実習は朝のラウンドから始まり、その後カンファレンス、オペ見学と続きました。オペ見学は自由に選択することができ、また心臓外科の時とは違い学生の仕事が無かったためオペを最初から見学、参加までさせて頂くことが出来とても良い経験になりました。さらに、問診・診察を英語でしたいと希望を出したところ、希望通りさせて頂くことができ、ディスカッションまで担当の医師とする事が出来ました。最後の一週間では朝のカンファレンスにおいて英語でプレゼンテーションを行う機会を与えられました。プレゼンテーションの後に”Good job”と言われた時が留学に来て最も喜びを感じた瞬間でした。
最後の一カ月は救急を見学させて頂きました。救急では朝はラウンドに参加し、その後Walk-inの患者の診察を見学しながら、救急車が到着した時は処置を見学しました。救急のWalk-inではほとんどの患者に静脈路を取り、その仕事は学生に任されていました。日本ではまだ、ほとんど経験していなかった手技でしたが、医師に教えて頂きながらだんだんと上達を感じ自信をつけていくことが出来ました。その他に採血、心電図の記録も行い、その結果を担当の医師とディスカッションし理解を深めました。最後の実習であり、その頃には医師と患者がドイツ語で話していても具体的な単語やフレーズは分からなくとも、どのようなことについて話しているのか会話の内容をおおよそ把握するまでになりました。実習の後半では非ドイツ語圏の患者が来院した際には、問診を取る経験をさせて頂きました。
この3ヶ月間の留学で経験した一つ一つの出来事が自分の将来にとって、非常に貴重であり唯一無二の物であったと感じています。ここで書かせて頂いた病院内での経験だけでなく、院外での現地の学生、他の国からの留学生と交流を深めることが出来たのも大きな収穫でした。移植についての考え方、医学部を卒業してからのキャリア、海外で医師として働くことについて等、今まで日本で当然だと思っていたことが、実は寧ろ日本の方が特別であったと気付かされたことが多くありました。これらの多くの経験は私自身が自分の将来を考える上でより広い視野を持つことが出来るようになったと考えています。
最後になりましたが、この様な留学という貴重な機会をくださりまた支援してくださった、国際連携室の先生方、学務の方々、現地の先生方、フロンティア会の先生方には心から感謝しております。本当にありがとうございました。
Duke大学実習報告
志波大輝
一年前の秋、私は留学先はヨーロッパにしようと考えていた。まだ訪れたことのない東欧の街を散策し、言語の勉強でもしながら悠々と過ごす留学生活を夢見ていた。しかし、親しい友人と父の言葉に私は考えを変え、ほぼ書き上げていた志望書類をアメリカ用に書き変えることになる。これから医者として働きはじめようという時に、ただ遊びに行くよりも世界の一流の医療、医師の働きぶりを見てきてはどうか、という説得にそれもそうだなとすんなり納得したのである。選考の末に留学先はDuke大学になった。陽光降り注ぐヨーロッパの石畳は雲散霧消し、私は新たな留学の目的として、アメリカにいる知人友人を訪問し久闊を叙すこと、そして将来の自分の指針となるような医師に出会うことの二つを掲げ、出発した。
Duke大学はタバコ産業で一財を築いたDuke家の寄付によりNorth CarolinaのDurhamという小さな町にできた大学である。初夏、Durhamの空は連日澄み渡り(ただし週に三度は激しい夕立がくる)、キャンパス内の滴るような緑が石造りの峻厳なチャペルを際立たせている。そして昨年、病院の建物はガラス張りの豪奢なものに建ち変わり、Duke大学は一層そのブランド力を増したかに思える。私がアメリカで出会った医師、研究者はそれぞれに光る個性と天賦の才能を持ち合わせた人たちであった。紙幅の関係ですべての先生に登場していただくわけにはいかないが、こちらで出会った先生の言葉を引きながら今回の留学を振り返ってみたい。
Dr. Perfectは感染症科のチーフの職に加えて、基礎研究、ラボの運営、内科のアテンディングと多くの仕事をこなす先生であった。ホームステイ先の家族と親交があったため、病院以外で話す機会が何度かあった。私がこの先生を鮮明に覚えているのは、その恰幅のいい体と豪快さによるばかりではなく、自身が多くの仕事を掛け持っていることを形容して”I am an old type of man”と述べたからである。俚諺に、人は四十になったらその顔に責任があるというが、分業の極みに達した現代において、幾つもの仕事を兼ねる先生の顔には他の人にはない風格があった。
Mayo ClinicのDr. RoccaはRochester Epidemiology Projectを率いる先生で、幸運にも自宅に三日間滞在させていただく機会があった。先生はイタリア人らしい陽気さと磊落さで出迎えてくれ、多忙を極める中Mayo Clinicの案内をして下さった。実際は病院そのものよりも病院内にある美術案内を楽しみ、ロダンの粛然たる彫刻や墨痕淋漓に描かれた古代中国の書画を鑑賞した後は、Rochesterの有名な建築家の家を見て回った。病院にほど近い小高い丘に並ぶ家々は歴史を感じさせ、近代的なMayo Clinicの建物とは対蹠的に滋味のある家屋が並ぶ一角である。非常に穏やかな三日間のなかで、先生が莞爾として語った「アメリカは肌の色、体格、宗教、家柄などに関係なく、自分が本当に優秀なら無条件で認めてくれる」という言葉が印象に残っている。私は次は医者か研究者としてここに戻ってくると約束し、先生の芸術から文学にまで及ぶ博識と高風を欽慕し、帰途についた。
私が好きな詩に佐藤春夫の「綾にしき何をか惜しむ/ 惜しめただ君若き日を/ いざや折れ花よかりせば/ ためらはば折りて花なし」という一篇がある。若い時分に受ける刺激は大切なもので、その一瞬を逃してはならないといったほどの意味である。私が今回の留学で出会った人々の感性や思惟は私のこれからの人生に大きな影響を及ぼすものであると確信している。このような経験は決して日本で得られないわけではないが、私は若いうちに海外に出て行く重要性を改めて感じた。外国に行くということは、日常の定点から自身をはずして異物に衝突し、文化を観察し観察されるということである。異国にいくと、日常は無数の菌糸で私たちを絡みとっていて、自分が感じているよりはるかに自分が根無し草でないということが鮮やかな不安でもって知覚できる。後輩たちには是非勇気を持って日本を抜け出し、人生の糧となる経験を積んでほしいと思う。慣れない言葉と環境のなかに身をおき、挑戦を続けた私のアメリカ生活ももう終わりである。膨張、展開、奇異、驚愕の日々はすでに過ぎ去ってしまった。羊群声なく牧舎に帰る。
Tulane 大学派遣留学報告
春日井 大介
私は米国のLousiana州New OrleansにあるTulane universityで2014年の4/4~7/3までの三ヶ月間臨床実習を経験させて頂きました。New Orlenasはアメリカの中でも独特の文化がの素地があります。Jazz発症の地であり、クレオール/ケイジャン料理という特有の食文化、圧倒的にFestivalが多く楽天的な人々、一方でBible beltと言われるくらい保守的な人が多く、黒人社会であり、ベトナム戦争後のベトナムからの移民が多い、そんな歴史的にもuniqueな土地でした。このように体験記を書いていると、留学中の出来事が思い返され、既に懐かしく感じております。
#留学の動機
今回、私が留学しようと思い立ったきっかけは、アメリカでの医療システム、教育システムを見てみたいと思ったからです。主要な論文雑誌はアメリカで発刊されていると聞き、そのような論文が執筆されやすい土壌に興味をもったのと同時に、良いと聞いていた教育システムを実際に体験してみたく思いました。また、今後私が日本で医療をしていく上で、どこかの段階では教育に関わるのではないかと考え、将来役に立つかもしれないと漠然と考えていました。
#実習内容
最初の一ヶ月はSurgical Intensive Care Unit(SICU), 二ヶ月目は内分泌内科、三ヶ月目は脳神経外科とMedical Intensive Care Unit(MICU)で実習をさせて頂きました。
SICUでは毎朝当日に担当患者が割り振られ、朝6:30に回診/カルテチェックを行い、Attending doctor(指導医)へのプレゼンテーションの準備をします。行くまで事前準備ができず、プレゼンテーションのfomatもわからず最初はとても緊張しましたが、最後にはスリリングな状況を楽しめるようになりました。自分が興味をもった患者さんを何人でも担当して良いということになり、指導医は総回診後にその日の内容から臨床的トピックをピックアップしてレクチャーをしてくださいました。
内分泌内科では、クリニックでの外来を見学をさせていただきました。疾患としては大部分が糖尿病フォローでしたが、甲状腺疾患やテストステロン欠乏症なども診ることができました。関連するガイドラインや論文を提示され、適宜勉強することができました。
脳神経外科では、朝5:30から全患者の回診をレジデントのドクターと行います。その後はオペ見学を行います。脳神経外科はcompetitiveな科であると同時にとても忙しい科で、毎日三件以上のオペをこなして、終了時間は午後7時を超えることも多かったです(午後七時から最後のオペが始まった日もありました)。ERに新患が運ばれてきた時は、コンサルトを任されることもありました。担当患者にさせて頂き、オペ中も積極的に参加させていただくことができ良い経験となりました。
MICUは呼吸器内科に属しております。毎日午前と午後に回診があり、午前の回診はレジデントの教育を兼ねているので3時間ほどあります。毎週木曜日はchest conferanceと呼ばれる、胸部X線画像と胸部CTの読影会があり、その後は抄読会に参加します。chest conferanceではfellow doctor(後期研修医)がX線やCT画像の所見を述べていくのを聞くことができ、アメリカでの読影の作法のようなものを学ぶことが出来ました。抄読会はLosiana州立大学と共同開催で、NEJMに投稿された最新の論文についてfellowが発表した後、attending
doctorと侃々諤々の議論をします。その後別のattendingが関連項目に関しレクチャーを行います。論文の読み方、評価の仕方について僅かながら知ることができて、大変よい機会でした。
#文化の違い
今回の留学で私が一番実感したことは、文化が違うと適正な医療も違うということです。医学の世界のスタンダードと言われるアメリカですが、私が実習していたTulane medical centerでも文化の違いによる影響を強く感じました。New orleansは米国の中でも陽気な人々が多い地域で、看護師は患者さんのことを「baby」「buddy」「honey」などと呼びます。DNRのインフェームドコンセントをとうようなシリアスな場面でも医師も患者もお互いにジョークを言い合ったりしており、衝撃を受けました。
#医療システム
アメリカの保険システムは、皆保険制度ではなく、民間の保険を使うのが一般的です(medicare,medicaidなど民間でない保険もあります)保険により、できない治療、出来る治療があるというのはよく言われている話ですが、内分泌内科で実習している際、糖尿病で第一選択とされている薬が使えなくなってしまった方を見ました。治療がわかれるのは最先端の治療や薬だけなのだろうと思っていましたが、生活習慣病である糖尿病でさえ保険で治療法が変わってくるのだということを実感しました。また、ある先天性心疾患の既往がある患者さんのケースでは、保険に入っているといっても一生のうちに保険会社が支給してくれる額に限度があり、既に外科手術で大部分を使ってしまったという話も聞きました。アメリカの医療の効率がよく便利な側面も見ることができましたが、このように一部の方々が不遇されている現状を見ることが出来ました。
#教育システム
所謂屋根瓦式の元祖で、良い評判をたくさん聞いておりました。実際に体験してみると、確固としたシステムがあるわけではなく、結局のところ個々人の裁量次第であると強く実感しました。毎日のようにその日の回診のトピックでレクチャーをしてくださる指導医の先生もいらっしゃれば、レクチャーなどはしないという先生もいらっしゃいました。レジデントの先生方も特に義務ではなのに、たくさんミニレクチャーをしてくださる先生もいらっしゃいました。一方で、そのような沢山レクチャーをしてくださる先生のお話を伺うと、自身が沢山レクチャー受けてきたことを還元したいという気持ちでやっているのだと教えて下さいました。教育的な「文化」があることが屋根瓦式の教育システムに大変重要なのだと感じました。
#最後に
今回の留学を通して、特に有意義であったのは人との出会いでした。米国人だけではなく、同じように留学に来ているサウジアラビア人、タイ人、ネパール人等多様な人種のドクターと知り合い、考え方や価値観に触れることができたことは、私の今回の留学での収穫だと思います。また、留学中は様々な方々のお世話になりました。人種問わず沢山の方々の慈善的なサポートのお陰で、充実した実習を送れたということを強く実感しています。留学先でお世話になった先生方、一緒に留学した仲間達、お忙しい時期にアドバイスをくださった先輩方、国際交流室の先生方や留学に関わったスタッフの皆様には今一度御礼を申し上げます。本当に有り難うございました。
ウィーン医科大学派遣留学報告
星野 昭芳
私は、オーストリア・ウィーン医科大学Medical University of Viennaに12週間派遣留学をさせていただき、大学病院付属の神経病理研究所にて神経病理学、St.Anna Kinderspital小児病院の小児腫瘍・血液腫瘍部門にて小児科、大学病院の第三内科にて膠原病内科を実習いたしました。ウィーン大学医学部は、オーストリア大公ルドルフ4世の時代である1365年の設立で、ドイツ語圏最古の歴史を誇る大学です。大学病院AKH (Allgemeines Krankenhaus)は、全部で36診療科、病床数は病棟2棟(21階建ての病棟が2棟あり、それぞれ「赤病棟Rotten Bettenhaus」「緑病棟Grün Bettenhaus」と呼ばれています)で合計2134床の巨大病院です。
大学病院付属の神経病理研究所にて5週間神経病理部門の実習を行いました。神経部門にてもっとも刺激になったことは、やはりBrain Cutting件数の多さです。オーストリアの変性疾患はすべてウィーン大学医学部に集約されているため、Brain Cuttingは週2回と症例数も多くなっております。アルツハイマー認知症はもちろんのことFTLD, DLB, PDなど認知症、PSP, CBDなど神経変性疾患さらに多発性硬化症とその類縁疾患、さらに診断のつかない脱髄疾患など、40件の開頭解剖症例に立ち会うことができました。プリオン病疑いも6件くらいあったのですが、CJD確定症例は1件、ほかは意外とPMLになっている症例に遭遇しました。ご存知のとおり日本でも70%くらいが不顕性感染していると推定されています。しかしオーストリアでは症例数が多く感じます。これは解剖となる症例数そのものがオーストリアでは多いことに起因するようです。国立感染症研究所の報告では日本における発生率は
0.9人/1000万人(2007年)と極めてまれな疾患になっていますが、潜在的患者はもっと多いのかもしれません。このようにオーストリアで解剖数が多い理由ですが、キリスト教的な価値観では、死後は魂こそが重要であり、残った肉体に重きを置かない(まったく配慮しないわけではありませんが)という文化的背景もあるのでしょう。それ以上にオーストリアでは、疾患の解明は非常に公共性の高い案件とされており、疾患の研究という社会的使命の高いものために、肉体を献じるべきであるというコンセンサスが存在するそうです。これはオーストリア・ハンガリー二重帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の命令により作られた方針とのこと。オーストリアは今でこそ中欧の一国家ではありますが、かつてのハプスブルク王朝の遺産の上に成り立っている歴史の重さも感じました。
滞在期間中に、"Lange Nicht der Forscung"という大学主催の親子向けの公開講座に立ち会うことができました。公開講座は夕方17時から23時まで病院の研究診療37部門がそれぞれの講座の研究をアウトリーチ活動するもので、神経病理滞在時には脳研究のアウトリーチ活動を、小児病院滞在時には腫瘍免疫療法の解説にそれぞれ参加しました。他部門でも、スキルラボで聴診器を使うお医者さんごっこやBLS体験、外科部門では心臓移植のライブ中継など行われていたようです。こういう本格的体験学習が小学生くらいから味わえるというのがウィーンの医学教育の深さなのだと、ただただ感心するばかり、かつ羨ましく思った次第です。
大学病院を離れてサンタアンナ小児病院の腫瘍・血液疾患部門にて5週間の小児科実習を行いました。小児科では医療業務は英語で行われていますが、患者(患児)はドイツ語になるため、指導医の先生と相談して、研究業務に関与する割合を増やした実習としていただきました。「樹状細胞免疫療法」をおこなう患児の臨床業務については、回診に同行するobservationを中心として患児の日々の体調を一緒に観察することとなりました。患児は担癌かつ樹状細胞のadoptive transferになりますので、やはり感染がおおきな問題となります。一般細菌感染、ウィルス感染(特にCytomegalovirus感染が警戒されます)も気をつけなければならないのはもちろんですが、侮れないのが真菌感染です。Candida属、Aspergillus属、Cryptococcus属に加え、こちらではときにZygomycetes属が日和見感染菌として問題になることがあります。欧州の土壌には広く常在するそうで、副鼻腔などに感染巣を形成し、組織を侵襲しながら眼窩内へと拡大するため、血液腫瘍や脳腫瘍術後にはとりわけ警戒しなければならないやっかいな真菌になります。いずれにしても免疫療法患児の管理は、長期戦になりますので毎日の体調の変化を見逃さないようにという実習内容となりました。
平行して付属小児腫瘍研究所にて免疫療法のQuality Controlに関する研究に参加しました。またこちらの研究所でも"Die Lange Nicht der Kinderkrebsforscung" (The long night of Children's Cancer Laboratory)という公開講座が開催されました。小児疾患の研究所なので、対象は一般向けと子供向けの2種類です。「研究所の長い夜」の名前の通り、学校や会社が終わったあとに参加できるように夕方17時から22時までの開催です。大学病院の公開講座に引き続き小児病院でも、派遣留学中に2回も公開講座のお手伝いができるという大変にありがたいめぐり合わせとなりました。大人向けの講座では各部門の教授による一般向け解説が行われ、
研究の重要性を説くとともに、寄付のお願いをすることになります。研究資金の約半分はこうした寄付でまかなわれているそうで、広く社会に研究の意義を説明することは、研究活動の継続性にとって非常に重要な活動になっています。こちらでは寄付行為は、税控除となるという利点?ばかりではなく、富裕層のNoblesse obligeとしても機能しているようで、寄付行為は社会的に非常に高く評価される「名誉」でもあります。
最後の2週間はふたたび大学病院にもどって、第三内科の膠原病内科部門にて実習をしました。ウィーン大学では内科は大きく3つにわかれています。第一内科は腫瘍内科、血液内科、感染症科・熱帯医学の各部門、第二内科は循環器内科・血管科・呼吸器内科の各部門、そして第三内科が消化器内科・肝臓科・内分泌内科、腎臓内科、そして今回実習した膠原病内科になります。膠原病内科は赤病棟の20階に30床の病床を割り当てられています。病室の構成は、個室、ふたり部屋または三人部屋で、部屋の中には日本の病院でみられるような仕切りのカーテンも個人割り当てのテレビもありません。また、病棟の廊下にコーヒーと紅茶が用意してあり、患者さんは飲水制限がかからない限りは飲み放題というのもいかにもカフェ文化花盛りのウィーンらしさ、日本との文化の違いを感じます。
これまで実習した神経病理部門、小児病院とは異なり、第三内科では診察もカンファレンスもすべてドイツ語、まだカルテもデジタル化されておらず紙カルテが使用され、基本的に患者情報や治療記録、検査や看護記録なども含めてすべてがこのファイルに集約されています。ラウンドはこれらファイルを片手に行われています。手書きのドイツ語なので何が書いてあるかさっぱりわかりません。そのかわり、引継ぎ用にこの紙カルテとは別に、患者ごとの状態が要約された印刷物が配られますので(ドイツ語ですが)、これを翻訳しながら状況を把握することになります。略語も多く、一般名と商品名の両者が混在していたりして、解読に手間取ります。診療はすべてドイツ語で行われているのでこれら診察やカルテ記載やプレゼンをする機会はなく、そのかわりに実習内容は入院患者に対する手技を中心とすることとなりました。実習期間中は毎朝7時30分に病棟へ行くと、オーダーに従って採血管や点滴輸液が用意されていますので、最大30人分の採血と点滴と注射を行うことから始まります。この間8時から当直医との引継ぎカンファレンスがドイツ語で行われています。これら手技が終わってからラウンドに同行します。すべてドイツ語ですが若手の先生のご配慮で患者ごとのポイントを英訳してくれるので非常に助かりました。また回診中にも指示があって、心電図をとったりポータブルX線の撮影を手伝ったり新患に点滴留置針を置いたりとさまざまな手技を行うことになります。回診は13時すぎまで4時間近くかけてじっくりと行われています。午後も新患の対応があればそれを行い、15時30分の引継ぎカンファまでが実習時間です。
膠原病内科部門とはなっていますが、一般内科の入院患者も対応していますので、約半数は感染症(尿路感染がなぜか多いです)や呼吸不全(肥満に伴うもの)、透析患者や急性 冠症候群などの患者さんも対応します。RAを含む関節炎、SLE、PM/DM、systemic sclerosis、ベーチェット病、サルコイドーシス、クリオグロブリン血症や血管炎などの疾患と、それらのoverlap syndrome症例、あるいはCIDPの急性増悪に対するrapid infusion治療などみることができ、よい経験となりました。治療は基本的には「ステロイド」で、重症度と”予算”(さすがに優良な民間保険に加入していないと高額な分子標的薬は使用できません…)に応じて免疫抑制薬のほか分子標的薬やIVIg治療などを行っています。日本で未承認の薬剤の使用や日本では保険適用外になる使用方法などがとても印象的でした。もうひとつユニークな点があるとすれば風土病の存在です。ウィーンで若年の関節炎をみたときには、Tick-borne
feverを疑うそうで、屋外でダニにかまれたかどうかが問診のポイントになります。オーストリアのダニの80%にはBorreliaが存在していて「ライム病」を発症させることになります。遊走性紅斑が特徴的ですが必発ではないので膠原病との鑑別が重要になります。また、1%と頻度が低いのですが、Tick-borne encephalitisウィルスを同じダニが媒介するため、膠原病のような症状がみられたにもかかわらす、1週間程度で症状が消失した場合にはその数週間後に中枢神経系症状を呈することがあるので、併せて警戒する必要があります。こういった膠原病との鑑別を要する風土病について、症例にこそ出会わなかったもののポイントをおさえた勉強をすることができてたいへんためになりました。
この2週間は、臨床の手技のみならず文化的な側面も含めて患者さん対応は学ぶことが多かったと思います。採血が上手くいかなくても「Das macht nichts」(≒気にしないで)といってくれました。これは”若い先生の育成に患者として協力している”という社会貢献意識が念頭にあるそうで、体調が優れないから入院している患者さんに逆に助けていただいているようで、たいへんに申し訳なくまたありがたく、感謝の念でいっぱいです。実習中もレジデントの先生がさりげなく手技をみていてくれて良かったところや改善すべき点をフィードバックしていただけたのが良かったです。わずか2週間であっても技術面の向上に直結し、実際に患者さんにも「上手くなった」といってもらえて、技術の向上にも自信が持てたのではないかと思います。ウィーンの医学生は日本に比べて許可されている手技の範囲が広いため(もらった実習手引きによると、指導医監督下で学生が中心静脈カテや骨髄穿刺もやってよいことになっています)、おそらく技術的にはこちらの学生は日本の研修医に近いレベルなのではないかと想像します。したがってウィーン大学の医学部学生は、日本の研修医相当のきめ細やかなフィードバックを受けることができる体制であることがわかります。
最後にまとめとして日本とオーストリアの医療の違いを考察することにします。
オーストリアは欧州でも裕福な国家であり、欧州有数の重税国家でもありますが医療福祉は充実しており、民間の保険を併用することを前提としても、アメリカのように経済状況によって受けられる医療サービスに差が生じるようなではないようです。医療制度で受けることが出来る医療の質も、現場の最前線で働く医師の先生も貢献度も、日本とオーストリアでそれほど違っているとは思えません。強いて違いを見出そうとするなら、オーストリアではすべての人が社会の一員であり社会貢献しているという意識は非常に高く思えます。滞在期間中に私がオーストリアの医学で感じた差はむしろ教育に関するもののほうが多かったと感じます。まず前提としてオーストリアでは医師数に余裕があり、人口は800万人あまり(愛知県と同程度)ながら、年間1400名の医師を輩出しています。医師も年間3週間の連続休暇を補償されているなど労働環境も恵まれています。また労働資源保護のために分業を推進しており、診療中の医師にはかならず医療系事務員が同席していて、医師が所見を述べると事務によってカルテ記載されていきます(同時に録音されており細かな記述について文字越こしされます)ので、医師は文章の最終チェックのみすることになります。
家庭環境すべての医師が若手医師や学生の教育にも熱心です。医師に時間的余裕があることを差し引いてもなお、オーストリアは教育熱に溢れています。どうやらオーストリアでは「教育」というものが、われわれ日本人が考えているよりももっとずっと広い意味で捉えられているようです。学校教育はもちろんのこと、みんなでこどもたちを守り育てて立派な市民にするのが、教育に直接携わるもののみならずおとなの義務と考えられているようです。もちろんおとなも生涯にわたり学習する責務を負っています。研究部門では技師さんであってもテクニシャンであってもアウトリーチ活動にはみな積極的に参加しますし、決して自分は教育には関係ないといった態度をとることは決してありません。ある技師さんにお話を伺ったところ、「自分もかつて教育の恩恵を受けたのでそれを次世代に引き継ぐ」という考え方なのだそうです。あたかも、上級医の先生が若い先生を教育して育成していくのと同じようなことが、オーストリアでは国民全員参加で社会全体にて広く行われているという喩えが最も適切かもしれません。こうした教育熱の高さを実際に感じ取り、非常によい刺激的な経験となったと思います。
日常生活で感じたこととしては、オーストリアに限らずドイツ語圏では、時間を守るという意識の高さはかなり忠実かつ厳格なものになっています。商店は平日あさ7時から夜20時までの営業で日曜休日はお休みということで、うっかりしていると買い物をし損なうことになります。また閉店時間を1秒でも過ぎるとお店には入れてもらえなくなります。日本人なら「融通が利かない」と思うところですが、この1秒を譲歩してしまうと際限なく譲歩しなければならなくなるとのこと。思い返せば日本社会では、上述のような1秒の遅れはおそらく配慮してもらえることでしょう。確かに非常にサービス精神が旺盛ではあるのですが、それがかえって仇となってしまっていて、いまや社会全体が過剰労働になっています。結果として人的資源をいたずらに浪費している傾向にあり、日本社会全体が巡りめぐって人間を大切にできていないのではないかとさえ感じました。欧州の高緯度地域ならではの長い夕方を優雅に楽しむウィーン市民をみながら、日本には残念ながら欠落してしまっている経済的な部分ではない「豊かさ」を、少し羨ましく感じました。
少々長くなりましたが、ご通読いただきましてありがとうございました。この文章を通じて社会全体が教育に熱心なウィーンの街の熱気のようなものを感じ取っていただければ幸いです。末筆ではありますが、12週間にわたりにてすばらしい経験をすることができたのも、ひとえに派遣留学プログラムにご尽力いただきました粕谷先生、近藤先生をはじめとする留学プログラム担当の諸先生のおかげと感謝しております。今回の派遣留学では、ウィーン医科大学の諸先生とウィーンの人たちの温かさに見守られて育てられたんだなという感謝の念でいっぱいです。いつか医師として臨床でも研究でも教育であってもなにか恩返しできたら、と思っています。
帰国報告文
浅井雄介
私は今春の3ヶ月間、台北の国立台湾大学へ名古屋大学からの初めての派遣留学生として学ぶ機会を頂きました。当大学、実は戦前の日本統治時代、1928年に日本政府によってつくられた元旧帝大で、名古屋大学よりも10年ほど古い大学です。
現地に到着した3月、台北はデモの真最中で、病院や滞在先の寮からデモの中心部までは数百メートル、警察官が常に待機している物々しい状況でした。しかし、待機している警察官達は弁当を食べたりスマホでLINEをしていたりして、マイペースでのんびりした台湾人の気質を目の当たりにしながら、3ヶ月の留学生活が始まりました。
実習したのは台北駅から徒歩10分、2300床の国立台湾大学付属病院です。15階建てのメインの建物が4つそびえ立ち、さらに独立した外来棟、小児科棟を含めると6つの大きなビルからなり、互いに地下道で連絡しています。ここで一般内科、外科、皮膚科をローテートしました。
一般内科では主に回診に参加しました。台湾は多民族国家であり、中国語を話す人、台湾語を話す人、先住民族の言葉を話す人がおり、回診中も患者さんによって言語を使い分けます。私は中国語に堪能ではありませんが、先生方や学生は皆、流暢な英語を話し、回診中なども患者の話をその場で英語で説明して下さり、言語面の問題はなくスムーズに実習させていただくことができました。
外科ではオペ見学を中心に実習しました。南国特有の国民性からか、オペ中の雰囲気はとてもリラックスしていて、ドクターとナースが歓談していたり、日本人留学生がきたということで、日本旅行する予定のナースの旅行計画をドクターも交えてオペ中に話し合ったりと、非常に和気藹々とした雰囲気でした。
皮膚科では病棟回診、外来、オペなど、なんでも希望通り参加させていただき、がん・膠原病・感染症など幅広い疾患をみることができました。国立大学病院でも美容皮膚科の範囲をカバーしており、ニキビの処置で来院する女性が多かったのは印象的でした。カンファレンスでは日本についてプレゼンテーションする機会をいただきました。カンファレンスは、若手から教授まで非常にオープンな雰囲気で、どんどん質問や意見が飛び交っていて活発な議論が行われていました。
当院では電子カルテはすべて英語化されており、学生達は原著の英語教科書を使っていたりと、英語の標準化はかなり進んでいると感じました。個人のiPadで電子カルテにアクセスできたりと、個人情報を守る意識が高い日本では考えられないようなこともあり、国民性の違いを感じました。
現地学生とは、実習中や食事など交流する機会が多くありました。台湾人学生は皆おおらかでオープンな性格で、相手を思いやる気持ちに溢れた人々でした。また、国立台湾大学には様々な国から学生が集まっており、香港、シンガポール、マレーシアなど、アジア各国から国をこえて進学してきている学生が多くいました。彼らはまず何を学ぶかを決め、次にそれに合った大学を世界中から探し、進学する、という感じで、国境を軽々と越えるフットワークを持ち合わせています。
台湾ならではの食べ物も、印象深いです。温暖な気候で育った、パパイヤ、マンゴー、バナナ、パイナップルなど糖度の高い果物はとても美味です。とりわけ、パパイヤと牛乳をミックスしたパパイヤミルクは絶品で、日本に持ち帰れないかと思うほどでした。タロイモという、熱帯地方でとれるサツマイモの一種もとても美味しく、そのまま食べたり、ミルクとミキサーしてタロイモミルクにしたり、油で衣と揚げて唐揚げにしたり、忘れられない美味しさでした。朝ご飯によく食べられる鹹豆漿は、豆乳のスープのベースに、ネギ、ごま油、油條と呼ばれる揚げ物、醤油が入っていて、とろとろの豆腐と香味野菜とごま油の非常にマッチした料理でした。台湾と言えばおなじみの小籠包は、肉汁の滴るこってりしたもの、あっさりとしていて朝ご飯にぴったりのもの、街の屋台で1つ30円程度で買える、スナック感覚のものなど、街中で色々な種類を楽しみました。
現地の人々とサッカーをしたり、サーフィンをしたり、現地の歴史を教えてもらったりと、交流する機会にも恵まれました。彼らは、ひとりひとり考え方や意見が違うことは当然で、自分の意見を正直に発することがよいことだ、と考えていて、ポジティブなこともネガティブなことも率直に話す彼らは、いつもリラックスした表情をしていました。彼らと過ごす中で、日本人特有の年功序列の意識や、周りと異なる考え方や意見を発言しにくい雰囲気など、今まであまり意識することのなかったネガティブなところを感じました。一方で、日本を離れてみて、初めて気づく日本の素晴らしさもありました。四季があり海山川に恵まれた日本列島の自然、人々の勤勉さ、細かいところまで美しく仕上げる丁寧な仕事、歴史ある伝統文化や建築物、さらに寿司に代表される日本の食文化の素晴らしさなどは、誇れるものだと思いました。地球上で、人、もの、情報、お金、あらゆるもののやりとりのスピードが上がっている世界で、日本人として育った自分をベースに、他の国から学ぶべきと思ったことはどんどん取り入れていこうと思いました。
今回の3ヶ月を通じて様々な人と出会い、医療の違い、文化の違い、気候風土の違いを感じられたことは大きな経験となりました。粕谷先生、近藤先生、西尾さん、フロンティア会の先生方、また現地でお世話になった方々、そして共に留学した同級生の皆、本当にありがとうございました。
Duke大学留学報告
滝翔太
5~7月の2か月間Duke大学に留学させていただきました滝翔太と申します。留学報告を書くにあたって、留学前の自分と現在の自分の違いは何だろうかと、記憶を辿ってふと考えてしまいます。留学するまでの間、日本では診察や医学用語など英語で医学を勉強するということをしていましたが、実際のアメリカの医療・医学教育については何も知らないも同然の状態でした。また学問としての医学がいかに膨大で深遠であるかということもどこかぼんやりとした視点でしか掴めていなかったように思います。留学経験によって大きく変わったことはそういった医学に対する見方や自身の今後の理想像が頭の中でよりはっきりとしたイメージで捉えられるようになったことだと感じています。
まず5月の初め、Duke大学のあるノースカロライナ州Durhamに到着します。話に聞いていたとおり、緑溢れる自然の多いのどかな都市で、時折雷雨が来るものの、天候の良い住みやすい街でした。ホストファミリーも寛容な方々で温かく、近くにスーパーも充実しているので、料理を作って、ゆっくりと勉強する日々を過ごしていました。
まず初めに神経内科の実習が始まりました。初週早速患者さんを一人持たせていただき、ラウンドでのプレゼンを行います。緊張しながらのしどろもどろなプレゼンで内容も今思えば酷いものでしたが、attendingの先生は非常に優しく、幾つか容態について質問され、最後には”Good job.”と温かい言葉をかけてくれました。少しプレゼンにも慣れ始めた木曜日、ラウンドの終わり際にattendingが私とDukeの学生に「明日くも膜下出血と心原性脳梗塞についてそれぞれ25分のプレゼンをしてね。」といきなり言い放ちました。一緒にいた学生は”Awesome.”とすぐ了承していましたが、口が裂けても私はawesomeなどとは言えない心境でした。そもそも口頭のみで疾患について25分のプレゼンをするなど日本語でもやったことがなく、まして英語でと思うと困難であることは間違いありません。どのようなプレゼンをするのかも見当がつかず、attendingに尋ねると”You don’t need to make a powerpoint. Make just a fancy.”と言われfancyな発表とは何なのか結局わからないまま次の日を迎えました。翌日Dukeの学生が先に発表を行いました。疾患の病態、症候から治療まで興味深い最新の知見を含めて流暢に話しました。先生方が「それは知らなかった」と学生の発表を通して新たな知識を得たり、また議論したり、質問をしたり、発表を通じて全員が知識を共有しようとしていました。なるほど発表というのはこういう場なのかということに気づいた頃には既に遅く、極めて教科書的な知識しか話せなかったのがアメリカでの初めての発表でした。
患者さんのプレゼンや疾患の口頭発表にも徐々に慣れ始めた頃、2か月目に入り、呼吸器内科の実習が始まりました。こちらでのattendingの先生は非常に気さくで、かつ教育的な方で「ショウタ、喘息の表現型について面白い論文があるぞ。読んでみてくれ。」と毎日のように興味深い論文をメールで送って頂きました。論文を読むこと自体不慣れで大変なものでしたが、先生自体も「遺伝子の細かい話はよくわからんな」「こんな複雑な分類意味あるのか」とあまりにも素直な意見を出してくださるので肩肘張らずに楽しんで話ができました。実習中だけでなくアメリカのジャンクなお菓子やハンバーガーを奢って頂いたり、野球場に連れて行って下さったのも非常に印象に残る思い出です。こうして文献を読むことを多くこなしたためか、終わり掛けには疾患についてのちょっとした発表を何も見ずに話すことができ、初めの発表と比べて大きな成長を実感することができました。
こうした一連の経験から感じたことは、Dukeでの医学教育がディスカッションと探求心を重んじていることと、そのために学生であっても各人に出来るだけ平等な発言権を置こうとしていることです。治療方針は、自分たち学生も含めた全てのチームメンバーでのディスカッションで決まっていましたし、先に述べた疾患の発表に関しても、先生方が質問や自分の経験談を語りながらより多くの情報を議論しながら出し合っていたように思います。こうした議論の中で疑問があれば喜んで文献や情報の検索を始めますし、疑問が出ること自体をいつも歓迎しています。また学生がプレゼンをしているときには、いつも真摯な姿勢で聞いており、その中で知らないことがあると「これは知らなかったよ。教えてくれてありがとう。」と時には感謝までしてくれるといった様子でした。もちろん発言の権利は平等にあっても学生が常に素晴らしいことを言えるわけではありませんが、時々でもそんな事を言われれば当然嬉しくないわけはありませんし、向上心も膨らみます。この点に関しては学生側からすれば喜ばしいことだったと思います。例えば患者さんのプレゼンで治療について話ができ、それをきちんと聞いて評価してもらえるというのは、治療に責任を持つという点で自信に繋がると思いますし、同時に学ぼうとするモチベーションにもなります。アメリカの医師の全員がこのようにしっかりと忍耐強く教育してくれるかと言えばそうではないと思いますが、全体として平均化して見たときに日本とはこの点で異なっていると私は思いました。こういった発言権を平等にもつということは突飛な意見でもまず聴いてみようとする点で新しい発想や研究に繋がり、医学の発展へと繋がっていくのではないでしょうか。日本にいるととかく標準的で皆と同じ知識を好んで受け入れやすいですが、アメリカでは人の知らないような知見もきちんとした論理に則り、説得力があるものであれば積極的に受け入れていく点で新しい試みが為され易いのかもしれないと感じました。
さらに滞在中は実習外でも基礎医学の教授や脳外科教授の福島孝則先生、Durham周辺地域の日本人研究者会の方々との交流など非常に様々な機会に恵まれておりました。少しでも繋がりがある先生が留学先にいるならば積極的にアポイントメントを取って話をするということは今回の留学をより豊かにしてくれました。特に自分とは異なる分野の人々と話すことで違う視点から物事を見ることができ、時に自分がいかに固定概念に囚われていたかということに気づかされることもあり、今後もこういった機会を持っていくべきだと感じました。
今回の留学ではこういった全ての経験からアメリカの医学と世界で活躍するということについて具体的なイメージを持つことができました。もちろん2か月で見られたものはアメリカの医学のうちのごく一部だと思いますし、医師になって後渡米したとするとまた違った観点を得ているだろうと思っています。しかし、これから働く上での一つの指針・モチベーションになるという点で非常に意義深い経験になったと確信しています。最後に、この貴重な留学経験を支えて下さった先生方、国際交流室スタッフの皆様、先輩、友人、家族にお礼申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
Warwick大学留学報告
中村 汐里
私はイギリスのWarwick大学にて12週間勉強させて頂きました。学生visaに関する法律の改正により、今年は8週間を病院で、残りの4週間を大学で実習することとなりました。直前まで渡航できるのかわからず、先生方のご協力のもと無事に留学することができ本当に感謝の気持ちでいっぱいです。留学を通じて学ばせて頂いたことを少しばかりですが報告させて頂きます。
1つ目は、NHSの難しさです。NHSとは全ての国民がGPに登録することで、無料で診療を受けられるイギリスの医療体制を示します。日本と違い緊急の場合を除き、国民は登録されたGPのもとを最初に必ず受診します。GPとは総合診療科の様な役割を果たしています。GPの診断を受けた後に、患者はようやく専門医や、大きな病院機関を受診することが出来ます。病院で働かれている先生方は、全ての患者さんが平等に治療を受けられるNHSのシステムに誇りを持つ一方で、医療費がとてもかかること、検査や専門医を受診するまでに時間がかかってしまうことを問題視されていました。すぐに検査、治療を行えないもどかしさを感じる時があると仰っていて、助けられる患者の数が減ってしまうのではと思いました。また、留学中に私が滞在していたprivate lodgeの大家さんの義父が膵癌であることが判明した際、大家さんは検査の結果や治療方針の決定までに時間がとてもかかるために、家族にかかるストレスはとても大きいと嘆いていました。そして無料であるイギリスの医療より、お金を払ってでも早く治療を受けられる日本の医療が羨ましいと言われ、医師の視点からも患者やその家族の視点からも、理想的な医療体制とは何かを考えるいい機会になりました。
2つ目は、治療の違いです。大学の実習は、simvastatinの薬の副作用に関するレポート作成でした。日本とイギリスの副作用の報告について比較を試みたのですが、日本とイギリスの患者の服用量に大きな差があり、充分に比較することが出来ませんでした。論文など、医療情報を世界で共有できる今でも、こんなにも治療に差があるのだと驚きました。また、日本がどうしてそのような治療方針をとっているのかを理解し、先生方に説明するのがとても難しく、自分で情報を調べる能力の大切さも痛感することが出来ました。
今回の経験は、沢山の方のご協力なしには得ることのできない貴重なものばかりでした。1人でのイギリス留学に不安もたくさんありましたが、優しい方達に恵まれ、本当にかけがえのない三カ月間を過ごすことができました。この様な機会を頂けたことを心から嬉しく思います。Visa取得の際に尽力を注いでくださった粕谷先生、Singer教授をはじめとした、私の留学に関わり支えてくださった全ての方に感謝し、お礼申し上げます。ありがとうございました。
国立台湾大学病院での実習で得たもの
田中 裕之
私はこの度、国立台湾大学で3ヶ月間臨床実習をさせていただきました。国立台湾大学の前身は、当時台湾を統治していた日本により1928年に設立された台北帝国大学です。メインキャンパスには椰子の木が並ぶメインストリートがあり、そのスケールの大きさは南国らしく壮観です。当時日本により建設された校舎が、現在も大切に使われています。キャンパスには各種スポーツの施設・コートが贅沢に設けられており、週末にもキャンパスは大勢の学生でにぎわっています。また、家族連れの散歩コースとしても人気で、台湾の人なら誰しもが憧れる国立台湾大学のキャンパスを大勢の人が歩いています。医学部キャンパスと病院のエリアは、メインキャンパスから離れた台北駅のすぐ近くにあります。ちょうど私たちが台北に到着したころ、学生運動が起きており日本でもニュースでキャンパスの様子が伝えられました。このキャンパスもメインキャンパス同様に、病院関係者だけではなく、地域の人たちの広場としての意味合いを持っているように見受けられました。病院のホールでは、たびたび演奏家の公演があり地下のフードコートと合わせてちょっとした憩いの空間となっています。
さて、3ヶ月の実習では、外科・産婦人科・泌尿器科の3科をそれぞれ一ヶ月選択しました。台湾での実習で一つ大きなネックとなるのは言葉の問題です。当初、一般内科を選択に組み込もうとしていましたが、患者さんとのコミュニケーションの問題もあるだろうということで、現地の国際交流室から非中国語圏の学生には外科系の診療科をお勧めするという話があり、上記3科を最終的に選択したという経緯がありました。現地に到着してみると、常に20人程度の交換留学生が入れ替わり来ているとのことでしたが、シンガポールなどのマンダリンを話せる学生も多く、そういう学生には内科が推奨されていたのかもしれません。しかし、科の選択は大きな問題ではなく外科系の中でそれなりにやっていけばいいのだと思いました。
現地での実習内容は、おおむね日本でのポリクリの形態と同じです。台湾では医学部は7年間あり、7年目は日本での研修医に相当する業務をします。そういう意味では日本のシステムと実質的に異なることはないと思います。産婦人科では特に、現地のポリクリの5・6年生と一緒に実習を行う機会を多く設けていただきました。日本のポリクリでは午前と午後にそれぞれ早く実習が終了するということが頻繁にあり、実質的な実習時間や量はかなり少なかったと思います。台湾でのポリクリでは、学生は一日中病院の中にいて多くの講義を受け、実技の実習をしていました。外国人学生がポリクリに混ざるということは全く珍しいことではないということが彼らの雰囲気から伝わってきました。先生が現れると、「今日は日本から留学生が来ているから英語で説明しますね」という風に自然な感じで始まり、時折混ざるマンダリンを、近くに座っている学生が折に触れ説明してくれたりしました。
こういう外国人に対する壁の低さは、台湾の歴史的背景が影響しているかもしれないということが後々わかってきました。台湾では、いわゆる台湾人が多くを占めていますが、その中にも互いに異なるエスニックグループが存在するようです。それは彼らや患者さんと一緒に過ごしているうちに、外国人の私にもおぼろげながら感じられてきました。顔立ち・背の高さ・雰囲気・話し方などについて、日本で感じるような集団内の連続性がないのです。そういう自らの抱える多様性は、内部にある多様性を許容するとともに外部から多様なものを受け入れる素地につながると思います。その点は日本の医学部での均質性と対照的であると思いました。彼らは、文化については日本を本当に良く見ており並々ならぬ関心を寄せているのですが、医療についてはすべてアメリカを基準としています。教科書はもちろんインターネットでの情報も英語で得ることを当たり前としており、学生も英語を本当に良く使いこなしていました。母国語のテキストやWeb pageがあれば助かるのに、という言葉も聞かれましたが、世界レベルの知識を一生アップグレードしていかないといけないのだから学生のときから英語で知識を得るのは当然だという意識がはっきりあり、日本人学生である私との意識の差を感じました。
さて、ここでオペ室の様子を書いておきたいと思います。特徴的なことは、何よりもナースの振る舞いでした。医師との関係が比較的フラットなのだと感じました。日本でよく見られるような、医師に遠慮して自らを抑えるような雰囲気を目にすることは少なく、自らの思うように振舞っているという印象を受けました。その場の「空気」の支配力が強い日本のオペ室や病棟と対照的でした。実際的な問題さえ生じなければ、軍隊のように規律がなくてもそれでよいという合理性であるという風に私は理解しました。また、台湾の街中ではビンロウが売られており、比較的高齢者を中心に嚙む習慣があるようですが、この嗜好品を原因とする口腔癌が台湾では多いということでした。こういう癌組織を切除すると、切除後すぐの生々しい組織を待合室に持って行き、家族にも見せるという習慣がありました。家族はその肉片のどこが癌組織なのかについて医師から説明を受け、スマホで写真を撮って帰ります。そういう風に家族に見せないと納得してもらえないとのことでした。台湾の人の独特な感覚だと思います。
回診での様子についても触れておきたいと思います。朝回診に回ると、多くのベッドでは横に家族用ベッドがあり家族があわてて起きて寝ぼけ眼で先生と話を始めるという具合でした。先生は二種類の挨拶を使い分けていました。マンダリンと台湾語と。比較的高齢の患者さんは多くが台湾語を話し、マンダリンとは全く異なる言語を話しているのだということだけは伝わってきましたが、内容はわかりませんでした。現地学生の多くは台湾語を理解できるということでしたが、あまり得意ではないと誰もが口をそろえて言っていました。回診の様子を見る限りでは、マンダリンだけではなく台湾語も使いこなせないと台湾では患者さんとのコミュニケーションで困ることになりそうです。外来では、客家語を話す患者さんにも出会いました。台湾のエスニックグループについては、もう少し突っ込んでその様子を伺っておきたかったなと今では思います。
今回こうして国立台湾大学病院に留学させていただいたことで、多くの貴重な経験ができました。アメリカなどでチームの戦力になるべく奮闘した同級生とはまるで違う3ヶ月であったわけで、その点はこれで良かったのかな…という気持ちも正直ありますが、それは表向きのコメントです。実際に台湾で得たものは、「○○を学んだ」と書くようなものとは違う種類のものであり、今回こうして留学しなければ今後二度と得られなかったと思います。
留学に応募しようか迷っていた際に、「まぁいいところたがら行ってみなよ!」と豪快に背中を押してくださった粕谷先生、近藤先生、学務課の皆様、事前研修でお世話になった先生方と先輩方には本当に感謝しています。ありがとうございました。
2014年度名古屋大学医学部六年次派遣留学報告書
布施佑太郎
~The Treasures That I Found In Boston and Baltimore~
Harvard University MGH並びにJohns Hopkins Hospitalにおける実習を終えて
この度、私は2014年春から夏にかけ三か月間ハーバード大学とジョンズ・ホプキンス大学において臨床実習をさせていただきました。帰国した今、振り返ると矢のように過ぎ去っていったように感じるかけがえのない経験でした。
本留学で私が学ばせていただいたことは沢山ありますが、なかでも病院実習、ボストンとボルチモアでの生活、そして出会いについて記したいと思います。
最初の一か月はHarvard University MGH Radiation Oncology Departmentにお世話になりました。ハーバード大学は多くの病院と提携を結んでおり、その中にはMassachusetts General Hospital (MGH)やBrigham and Women's Hospitalなど名だたる病院が数多くあります。MGHは医学部の敷地から離れており、チャールズ川に面したひときわ目を引く建物群が特徴の病院です。その放射線腫瘍科は陽子線治療センターを擁する一大部門であり11の領域チームに細分化されています。
実習は朝カンファレンスに参加することから始まります。これはレジデントを対象に行われる勉強会やケースカンファレンスの事が多く、論文や最新の臨床トライアルが飛び交う議論や幅広い分野にわたるレクチャーなど大変勉強になりました。医学的な知識だけでなくプレゼンの様式も学ぶことができました。
放射線腫瘍科は外来がメインであるため各アテンディングの外来に同行し問診、身体診察、治療計画立案などを一緒に行いました。治療の放射線照射は医師ではなく技師が行うことになっていましたが、技師について照射の様子も見せていただくこともできて診察から治療の流れを掴むのに役立ちました。
MGHのあるボストンは歴史的な趣のある都市です。Tと呼ばれる地下鉄兼路面電車が発達しており市内どこでも行くことができ、かつ夜も安全である便利な場所でした。さらにMITやタフツ大学などもある学術都市のため休日など多くの学生と知り合うことができ見聞が広がりました。
次の二か月間はJohns Hopkins Hospitalで実習を行いました。ジョンズ・ホプキンス大学 (JHU)は巨大な附属病院を持ち、臨床とともに研究も非常に盛んな世界中から医療関係者と患者が集まる施設です。最初の実習は腫瘍内科で、次の実習は内分泌内科でお世話になりました。
腫瘍内科では病棟管理が実習の大部分を占めます。ここでは研修医に近い立場に置かれ病棟管理を行うSubinternshipを経験しました。腫瘍内科はLiquid Tumor Team と Solid Tumor
Teamの2つに別れており、私はSolid Tumor Serviceに配属され実習を行いました。
腫瘍内科では化学療法がメインとなるため外来に通院をして化学療法をする患者さんが殆どです。しかし中には糖尿病や高血圧など高度な管理が必要となる患者さんや、副作用の恐れが大きく管理が必要となる患者さん、また救急外来から運ばれてくる腫瘍内科の患者さんなどケアの必要なケースもあります。そのような患者さんは病棟でケアを受けることになります。
病棟の実習では毎朝のプレラウンドで担当患者さんを診察し、総合ラウンドでプレゼンを行いました。総合ラウンドは医師・ナースプラクティショナー・看護師・薬剤師・ソーシャルワーカーから成り立っており、数時間にわたる密度の濃いものでした。午後は新患の診察を行い空いた時間に担当症例について理解を深めました。また、毎日ランチタイムにはカンファレンスが開かれておりそこで交わされるアテンディングの論議は興味深く毎回わくわくして聴講していました。
最後の一か月を過ごした内分泌内科は病棟を持たず、外来・コンサルのみのサービスでした。内分泌内科の朝は外来に始まります。朝7時半頃からアテンディングはそれぞれ甲状腺や副腎など専門性をもって外来を担当していて、そこへ参加しました。実習中にカルテを書いた患者さんの数は50を超え、甲状腺腫瘍など比較的罹患率の高い病気からヴォンヒッペルリンドー病やターナー症候群、MENなど稀な疾患まで経験させていただくことができました。
ここで、外来での実習の内容について触れたいと思います。約8-10名の患者さんをアテンディングが診察する前にフェロー以下のドクターと学生が診察する形式、すなわち患者さんを他の医師と交互に担当して診察する形式です。問診と身体診察を行った後は速やかにアテンディングと患者さんの前でプレゼンを行いそのままアテンディングの診察が始まりました。実習では10名近いアテンディングと働き学ぶという貴重な経験となりました。
午後はコンサルされた患者さんのうち比較的Complicatedではない患者さんを担当しコンサルノートを記載します。アテンディングの回診では病室でプレゼンをする機会が与えられました。ここではマネジメントを細かく述べることが求められ、飛んでくる質問に満足に答えられず歯がゆい思いをすることも多々ありました。
その後コンサルノートを完成させ、午前の外来のFull H&PとA&Pを記載した担当患者のカルテはアテンディングのフィードバックを受けました。どのアテンディングも非常に教育的であり、フェローによるレクチャーや、最終日の自分のプレゼンを準備する過程は内分泌疾患マネジメントの基本を学ぶのにとても役立ちました。
JHUのあるボルチモアはワシントンDCに近い港町であり、港のあたりは素敵です。しかし、JHHの周りは相当治安が悪く、日本との違いを肌で感じることができました。JHHでは様々な背景を持つ医師や医学生と議論を深めることで日本や自分の将来について熟考できました。
この三ヶ月間の実習で得られたものは言葉で言い表せないほど大きく、感慨深いです。このような素晴らしい機会をくださった粕谷先生、近藤先生をはじめとする名古屋大学の先生方、ハーバードとジョンズ・ホプキンスの先生方、西尾さん、事務の皆さん、家族、その他ご支援くださったすべての方々に感謝する気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
海外派遣留学 報告レポート
新井 有里子
この度、アメリカのルイジアナ州ニューオーリンズにありますTulane大学に3か月間派遣留学させていただきました。昨年留学された先輩方の充実感にあふれて活き活きとした姿に魅了され、この留学プログラムに興味を持ったのは約1年前のことです。一体アメリカには何があるのだろう?アメリカの何がそんなに優れているのだろう?という漠然とした疑問を、自分の目で確かめに行きたいと思いました。初めての渡米・海外生活は、見るものすべてが新しく、3か月はあっという間に過ぎてしまいました。しかし、短い期間だからこそ一日一日を大切にし、濃い時間を過ごすことができました。
3ヶ月間の実習で、循環器内科、泌尿器科、産婦人科をそれぞれ1カ月ずつ回らせていただきました。
まず、1ヶ月目の循環器内科の実習ではCCU(Cronary Care Unit)チームに配属されました。
CCUではERや他科からコンサルトを受け、緊急性の高い患者さんを受け持ちます。毎朝7時に病棟へ行き前日担当した患者さんの診察をした後プレゼンテーションの準備をします。フェローへの報告を行った後、アテンディングの回診に参加してプレゼンテーションを行い、午後はその日にコンサルトされた新たな患者さんの問診、身体診察を行ってアセスメントとプランをたてます。
今回の留学をより有意義なものにすべく、毎月初めに目標を定めて実習に取り組むこととしました。この初めの1ヶ月間の目標は、“胸痛が主訴の患者さんの鑑別とアセスメント、プランを自分で立てられるようにすること、そしてプレゼンテーションに慣れること”でした。一言に“胸痛”と言っても、急性心筋梗塞や大動脈解離など命に関わる重症疾患から、消化器系や筋骨格系が痛みの原因であった患者さんまで幅広く、沢山の症例を見せていただきました。プレゼンテーションでは、自分の考えの道筋を盛り込むことに苦戦しました。しかし、その都度先生方に「なぜその疾患を疑ったのか?」「なぜその薬を選んだのか?」と自分の意見を聞いてもらえたことで、次第に型が身につきました。実習の後半ではERでのファーストタッチを任せられることもあり、日々出来る事が増えていくことを実感でき、嬉しかったです。
2ヶ月目は泌尿器科を選択し、手技をできるだけ沢山こなすことを目標に実習を行いました。
Tulane大学では朝6時台から手術が始まることも多く、6時前には病棟で入院患者さんのIn&Out Balanceをチェック、回診を行い、その後手術やクリニック、カンファレンスに参加しました。アメリカではロボット手術を前立腺全摘出術以外にも、腎摘、膀胱摘、また骨盤内臓器術後の失禁や臓器脱を防ぐためのメッシュ挿入にも用いており、大変興味深く拝見しました。手技に関しては、希望すればいつでも手術に清潔で入れていただけるという恵まれた環境の中、助手や閉腹の際の縫合、経尿道的尿管砕石術などをやらせていただきました。
3ヶ月目はついに志望科である産婦人科での実習です。Tulane大学の産婦人科では今まで留学生の受け入れをしていなかったため、コーディネーターの先生を始めとして前の月に回った泌尿器科の先生や現地の学生など、沢山の方々のご協力を得て実習できることとなりました。
産婦人科では、主に婦人科のクリニックと手術に参加し、最終週は産科に特化した分院にて実習を行いました。産婦人科は日本でも外病院実習や病院見学などで長い期間実習した科であるため、日本とアメリカの医療を比較する良い機会となり、それを考えながら実習することを最後の目標としました。
クリニックでは学生が予診を担当し、レジデントに報告した後本診を一緒に行い、アテンディングにプレゼンテーションを行います。ここではPapスメアやSTDスクリーニングなどの手技が学生に任せられていました。以前からアメリカの優れた点として学生がとても勉強熱心だと感じていましたが、責任感を伴うからこそより意欲的に学ぶのだなと納得しました。教科書だけではなく、Up to dateなど最新の情報を用いてプレゼンテーションを作成することも、より臨床の現場に適していて効率的だと感じました。
手術では広汎子宮全摘など一般婦人科のものから女性泌尿器の分野の手術、また帝王切開などを見学させていただきました。産科の分院で当直をした際には経膣分娩にも立ち会うことができ、臍帯を旦那さんが切っていることが印象的でした。皆さん切る際にとても感動されていて、出産の時点から旦那さんも育児参加しているという意識が高まる素敵なアイデアだなと思いました。その一方で、手術法などに大きな違いはありませんが、日本で見た腹腔鏡下手術を思い返してみると、日本人の先生方はやはり器用であり丁寧であったということが、外国に来たことによってはっきりとわかりました。
長いようであっという間だったこの3ヶ月間を通して、大きな収穫が2つありました。
一つは、自分の気持ちや考えを積極的に表現することの大切さを学んだことです。英語の壁は想像以上に厚く、また現地の学生とのあまりのレベルの違いに落ち込むことも多々ありました。しかし、だからこそ積極的に発言したり集まりに参加したりして貪欲に学ぼうとする姿勢を見せることで、先生方、友人たちとの信頼関係が築き上げられていくことを実感しました。
もう一つは、現地でできた友人達です。医学部に入学してからの6年間、新しい友人といっても部活の繋がりでできる程度で、バックグラウンドが全く異なる友人ができるということは新鮮な体験でした。今回の留学では実習中だけでなく、寮においても国籍の異なる様々な学生達と関わることができ、勉強のことからそれぞれの母国の恋愛・結婚観など、多くの話題で盛り上がりました。同じように留学で来ていた学生とは今後それぞれの国を訪問し合う約束をして別れました。今から再会が楽しみでなりません。
最後になりましたが、今回このような貴重な経験をさせていただくにあたり支援して下さった名古屋大学の先生方、国際交流室の先生、学務の皆さん、フロンティア会の先生、先輩方に、深く御礼申しあげます。また、共に支えあった同級生のみんなにも感謝しています。本当に、ありがとうございました。