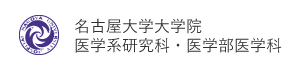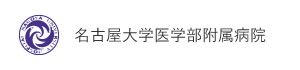研修・教育体制の紹介
研修風景1

研修風景2

研修風景3

留学体験記「Days in Adelaide as a PhD Student」
2014年卒
老年内科 医員 坂井智達
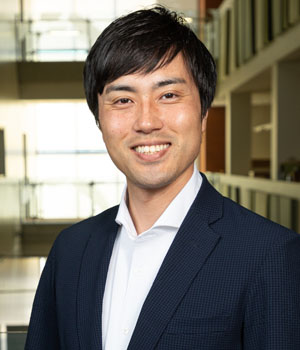
2022年4月から2023年10月まで、オーストラリアの南オーストラリア州にあるアデレードというところに研究留学していました。総じてとてもいい経験をさせていただきましたので、私の体験を酸いも甘いも含め共有させていただければと思います。
1. アデレード留学までのいきさつ
名古屋大学はにジョイントディグリープログラムという提携海外大学との共同学位プログラムがあります。簡単にいうと、大学院生の期間の一部(1年以上)を海外の大学で過ごし、学位取得を目指します。私は少し変則な流れでしたが、名古屋大学老年内科の大学院生として入学し、入学後にこのプログラムを知り、慌てて応募しました。幸い、当科で過去にこのプログラムを通してアデレードから留学生を受け入れた実績もあったことから、留学の話は比較的スムーズに進んでいきました。日本で大学院生として2年を過ごし、3年目よりアデレード生活をスタートしました。
2. アデレード
私が留学したアデレードは南オーストラリア州の州都であり、120万人都市です。20‐minute cityと呼ばれており、中心部は20分程度で歩いて周ることができ、中心部からは20分でビーチ、さらに20分でハイキングのできる山にアクセスができます。なんと2021年には世界で住みやすい都市の3位に入るなど、本当にちょうどよい場所です。気候は地中海性気候と夏は暑いですが日本に比べると快適です。加えてワインの産地であり、郊外にはワイナリーが点在しています。日本人はあまりいません。アデレードは学園都市であり、その中心にある、アデレード大学は世界大学ランキングでトップ100に入り、過去にノーベル賞を5人輩出するなどの研究実績のある大学です。
3. 研究生活
大学院生としての留学であったため、当たり前ですが、8時間/日×5日/週の繰り返しでした。大学とは少し離れた場所にある研究施設にデスクを設けてもらい、同じ研究室メンバーの部屋で作業していました。昼休みには、キッチンで他の研究室の大学院生や研究者の友人とランチをとっていました。研究生活を通して出会った研究の友人にはいわゆるオージーは少なく、様々な国籍の人が多かったです。オーストラリア以外では、イラン、中国、バングラデッシュ、フランス、ドイツ、トルコ、ブラジル、インドなど世界中の人とかかわることができ、多様性を目の当たりにしました。Adelaideには指導教官としてProf. Visvanathan and Dr. Agathe Daria Jadczakという2人がいて、基本的にはAgatheと週数回やりとりしながら、Renukaと2週に1度のMeetingの繰り返しでした。これも向こうでは当たり前なのかもしれませんが、まずはじめに驚いたのは、指導教官2人とも私のことを文字通り学生として扱ってくれたことでした。日本では何をするにもまず医師であることが前提にあるので、とても新鮮な感覚でした。更に、もちろん言語のせいもあったとは思いますが、一言一句チェックしてもらったと言っても過言ではないほど、手厚く指導してもらいました。研究時間外のことに口出しはないですが、研究時間内になすべき内容に関しても厳しく管理されました。例えば、アデレードでの老年内科の臨床も見学してみたかったですが、研究に支障が出るからという理由でNOの一点張りでした。一応大学院卒業したら見学していいよと言ってはくれましたが。苦笑 また、疑問の解決の方法も、方法論だけでなく、メンタルなアプローチも指導されたのもとても印象深かったです。アデレードでは、研究テーマである施設居住者のうつに関するスコーピングレビューと彼らのもつナーシングホームのコホートデータを用いた解析を行いました。と研究生活をまとめてみましたが、渡豪してすぐに、私自身が卒業要件を勘違いしていたことが分かり(しかも要件を少なく見積もっていた方に)、最初の数か月は割と絶望しながら卒論の計画をやり直していたことにも少しだけ触れておきます。
4. 家族での留学生活
アデレードでは、妻と幼児2人の家族4人で留学生活を送りました。住まいは中心街にほど近いカフェが立ちならずいわゆる富裕層が住むようなところの近くにアパートメントを借りました。歩くだけで気分の上がる通りで、アパートの裏には大きな公園があり、常に自由に使えるBBQ台を使って、友人とピクニックしたりしました。気候に関しては、冬はあまりよくないですが、夏は湿度が低く、うまれて初めて夏っていいなと思いました。一度自宅のバルコニーの目の前の木にコアラが迷い込んできて、通りすがりの人とコアラレスキュー(電話したら駆けつけてくれます)と協力して救助したこともありましたが、これがアデレード滞在中にあった、最もオーストラリアっぽい出来事になるかと思います。家探しに始まり、現地での生活のセットアップは、割と地獄でしたし、生活の何をするにも今までの数倍時間がかかるので不便もたくさんありました。しかし、妻の忍耐と子供たちの笑顔ですべて乗り切れましたし、家族と現地でできた友達との濃密な時間は今振り返っても控えめに言って最高だったと思います。平日5時以降と休日は家族の時間でしたし、月に1度は主に国内ですが、旅行もして回りました。グレートオーシャンロードを通る700㎞以上のロードトリップ、アウトバックを駆け抜けてたどりついたウルル(エアーズロック)、NZの大自然、タスマニアの自然と長崎のような綺麗な港町とあげればきりがありませんが、これらも控えめに言って最高でした。これも妻と子供たちのおかげですが、プレイグループと言って定期的に子どもと親が集まり交流する場や、子供の保育園幼稚園、研究関連でできた友達が徐々に増え、留学終盤は週末は毎週のように友人らと出かけて忙しくしていました。
5. 留学で得たもの
留学を経て得た研究スキルや経験、人脈はもちろんですが、もうひとつ私が得たかけがえのないものは家族との時間とその過ごし方でした。基本的には休日は一切Dutyはありませんし、メールみなくてよい(と最初に指導されました)状態でした。日本にいたころは、休日も少なかったですし、オフの時間であってもいつも臨床や研究のことを考えてしまっていました。そのようなスタイルが体に染みついていたのだと思います。ただ一方で、特に家族ができて、子供を授かってからはそのような仕事に頭を占領された生活にいつも疑問を持っていました。なので、留学してからは、研究の時間以外はそのことを考えないこと日々自分に言い聞かせながら生活をしました。留学してから半年くらいはなかなかその習慣から脱することができませんでしたが、帰国時には、オンオフの切り替えはだいぶうまくなり、子供たちとの上の空の会話もかなり減りました。結果子供たちとの関係性も随分変わったように感じます。
おわりに
順風満帆な留学生活であったとは言えませんが、とても実りが多い留学生活を送ることができました。それもこれも、なによりも家族、そして現地でできたたくさんの友人、献身的に指導してくれたSupervisorたち、両大学の関係者のおかげであり、大いに感謝します。また入局間もない私の留学を快く許してくれたとても寛大な医局にも感謝とともにこれからこの留学の経験から得たスキルを還元できたらと思います。

指導教官と同じ研究室のメンバー

いつも快晴、湿度の低い夏、ビーチ

自宅前、通行人との
コアラレスキュー

家からもより駅までの道。
歩くだけで気分が上がります。

家族旅行で道中のアウトバック