国際交流International
- Back
- Top > 国際交流 > 交換留学経験者からのメッセージ > 交換留学経験者からのメッセージ 2018年
交換留学経験者からのメッセージ 2018年
留学から学んだこと
岡本 峻幸(ジョンズホプキンス大学)
私は今回の留学で、アメリカのボルチモアにあるJohns Hopkins University Hospitalの腫瘍内科で4週間半、内分泌内科で4週間半の合計9週間実習させていただいた後、ボストンのHarvard Universityの系列病院であるMassachusetts Eye and Ear Infirmaryでobserverとして3週間眼科を見学させていただきました。今年3月の下旬に様々な不安を感じながらアメリカ行きの飛行機に乗ったのが今では懐かしく思い出されます。今回の留学を支えてくださった名古屋大学医学部国際連携室の先生、現地で私を教えてくださった先生方、現地で私をもてなしてくれたホストファミリー、家族、奨学金制度のトビタテ留学Japanには本当に感謝しています。有難うございました。
一つ目に回らせていただいた診療科は腫瘍内科でした。最初の3週間は固形腫瘍チームを、その後1週間半は白血病チームをローテートしました。腫瘍内科の実習は病棟中心で、常時約二人の患者さんを担当し、毎日データやカルテをチェックして患者さんを診察し、総回診でのプレゼンを行いました。腫瘍内科は一言でいうと壮絶な病棟で、非常に重篤な状態の患者さんが多くいました。私の担当した患者さんの一人は、進行食道癌に化学療法をおこなっておりましたが、シスプラチンによる強烈な吐き気が生じ、一晩に20~30回吐くような日もありました。また、PD1阻害薬のPembrolizumabによる副作用で慢性膵炎を生じた患者さんは、opioid系鎮痛薬の効きが悪くなり、10段階中10の強烈な痛みが何日も続いていました。
二つ目の診療科は内分泌内科でした。午前中の外来では、attendingの本診察の前に患者さんを診察し、attendingと患者さんの前でプレゼンを行います。初診の患者さんの診察やカルテ記載は難しく、送られてきたfaxの重要な情報を判断し、時系列順にまとめ、患者さんの話と総合してカルテに記載します。毎日私を担当してくれているattendingの外来に来る患者さんのカルテを一人一人チェックしてどのような疾患、経緯の患者さんなのかを予習しました。それでも、病歴聴取や身体診察を比較的上手にできた時もあれば、うまく情報を引き出せなかったり、病歴をまとめられなかったりした時もありました。また、午後のコンサルトサービスでは、他科からのコンサルトに対してfellowとともに患者さんを診察し、コンサルノートを書くのを手伝い、attendingの前でプレゼンをすることもありました。私がやらせてもらったコンサルト症例は、下垂体手術後のフォローアップ、高カルシウム血症、PD1阻害薬の副作用による副腎不全に対する対応などがありました。コンサルノートを書く際には、自分の医学的な知識の不足だけではなく、英語で長文を短時間で書く力、つまりwriting skillに至らなさを感じました。コンサルトで自分やfellowがプレゼンした際のattendingの指摘は、数多くのエビデンスを踏まえた非常に的確なもので、参考になりました。
最後の3週間は、Harvard University系列病院のMassachusetts Eye and Ear Infirmaryで眼科のobserverとして見学させていただきました。眼科の中でも網膜グループに配属され、外来では加齢黄斑変性、網膜剥離、Von-Hippel-Lindau病、Vogt-Koyanagi-Harada病、未熟児網膜症など様々な症例を見させていただきました。また、硝子体手術、強膜内陥術などを見学しました。年に一度開催されるHarvard Ophthalmology Annual Meetingでは、最新の手術法や網膜色素変性症に対するgene therapy、人工網膜など非常にexcitingなレクチャーを聞くことができました。
ローテート中にアメリカと日本の違いをいくつも感じました。一つ目は、アメリカでは各職業の分業が進んでいるということです。回診には必ずソーシャルワーカーが同行し、どのリハビリ施設やホスピスに患者さんを移すか、医師と議論していました。また、ナースプラクティショナーという資格が存在し、医師免許は持っていないものの、骨髄生険を行っていました。医師の仕事は、患者さんの診察を行い、情報を把握して処置や検査のオーダーを行うことであり、実際のライン確保や薬剤投与は看護師によって行われていました。このようなシステムにより、アメリカでは臨床医であっても研究やプライベートに時間を割くことができます。
二つ目は、痛み止めの使用頻度の多さです。特に強opioidのOxycodoneは非常に多く使用されており、痛風疑いの関節痛の患者さんにもOxycodoneを使用していました。また、骨髄穿刺や骨髄生検においても、局所麻酔薬のリドカインだけでなく、opioidのFentanylを使用する場面が多くありました。
三つ目の違いは、患者さんについてです。もちろん日本でもアメリカでもさまざまな患者さんがいますが、一般的な傾向としては、日本の患者さんは比較的従順で、治療法は医師にお任せという方が多いように感じます。腫瘍内科の外来での診察では、患者さんのご家族が様々な治療法を調べてきており、医師にこの治療法はどうなのかと質問する場面が多くありました。また、現在行われている臨床試験のリストを持ってきた患者さんもいました。一方、痛みを強く主張する患者さんも多くいて、日本ではリドカインのみで済ませるところにopioid系鎮痛薬を使用する場面もしばしばありました。
四つ目は、病棟と外来についてです。まず、病棟についてですが、アメリカでは病棟での滞在期間が非常に短く、状態が安定すれば即退院させるという印象をうけました。回診でも毎日いつ退院できそうか患者さんに話し、ソーシャルワーカーがどのリハビリ施設やホスピスに行くか患者さんと話し合うといった具合でした。また、骨髄移植を外来で行うIPOPと呼ばれるサービスが存在しました。一方、外来では反対に、アメリカの腫瘍内科の外来は一人の患者に対して1時間以上かけることも多くありました。内分泌内科でも先に学生やresidentの診察があるため、一人当たりの患者さんにかける合計時間は日本よりも多かったです。
さらに、医師に対する教育制度の違いがあげられます。アメリカでは医学部卒業後、residencyやfellowshipと呼ばれるプログラムに沿って医師に対する教育が行われます。各プログラムには同じ病院の同じ科でも異なる責任者がおり、プログラムの内容は第三者期間の定期的評価を受け、質が維持されます。また、residentやfellowが適切な教育を受けることができるように、attendingは積極的に症例を経験させます。日本では統一したプログラムがないため、後期研修の内容や質は病院によって異なってしまいます。
そして、アメリカで研究をやることについてですが、いくつかメリットがあります。一つは、設備が安く、様々な装置が日本よりも安く手に入ること、二つ目は他分野とのコラボレーションが多いことです。特に、日本のengineeringは世界トップレベルにあるため、日本でコラボレーションが少ないのはもったいないとおっしゃる先生もいました。さらに、chair of researchなど、寄付が非常に多くあり、研究に使える資金額が大きいようです。
最後になりますが、今回の留学は、私の人生を振り返っても最も大きなイベントの一つでした。留学で実際に現地を目の当たりにして初めて実感できたことや得られた情報が多くあり、自分の将来を考えるうえで非常に参考になりました。また、行く前はアメリカのほうが進んでいるイメージがありましたが、実際に行ってみると日本の医療のレベルの高さや、日本人の勤勉さ、モラルの高さを実感し、日本人として生まれ、日本の教育を受けて育った自分に誇りを持てるようになりました。自分の将来についてですが、自分の専門分野の臨床や研究をやっていく以外に、日本のシステムの改善や、日本の医療のすばらしさを世界に発信していく仕事ができればいいなと思っています。
それでは、留学を支えてくださったすべての方々に感謝申し上げます。有難うございました。
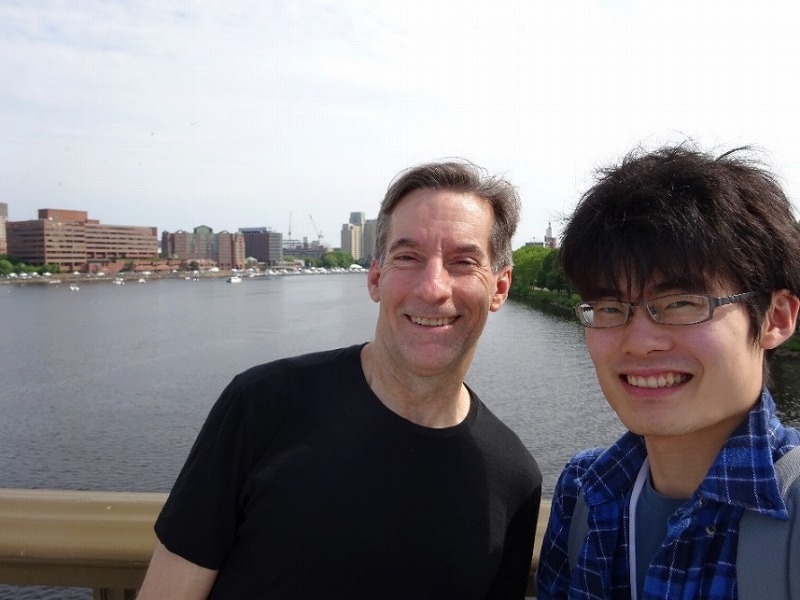 ボストンでお世話になったホストファーザーと
ボストンでお世話になったホストファーザーと 病院の橋をバックに
病院の橋をバックに 内分泌内科でお世話になっattendingと
内分泌内科でお世話になっattendingと Harvard Ophthalmology Annual Meetingのディナーでお世話になった先生達と
Harvard Ophthalmology Annual Meetingのディナーでお世話になった先生達と
JHU留学を通して医師のありかたについて考える
渡邊 裕斗(ジョンズホプキンス大学)
私は、理学部を卒業した後に医学部に編入したという少し遠回りの経歴を持っています。そして、「両領域を経験した自分だからこそできることはないか」ということを常々考えながら過ごしてきました。今回の留学では、米国Johns Hopkins大学への2か月の臨床留学および1か月の基礎研究室訪問を経験させて頂きましたが、自分の裏テーマとして、①新鮮で競争的な環境(かつ我が身を助けるのは自分のみ)の中で自分を「積極的」に動かす、②留学の中で自分を見つめ直し、今後の働き方の指針を見つける、ことを目的としていました。
最初の2か月間は神経内科・腫瘍内科で臨床実習を行いました。神経内科では神経変性疾患を扱うGeneral teamと脳卒中を扱うStroke teamに配属され、担当の患者さんの問診・身体診察・チームの医師へのプレゼンを主に行わせて頂きました。二次性多発性硬化症やMELAS、神経サルコイドーシス、バリント症候群等、国内の実習ではこれまで触れてこなかった種類の疾患の鑑別について考えたり、さらにその症例に関する論文について調べたりする機会を持ちました。他にも腰椎穿刺等の侵襲性の高い手技を医師監督下で行うことができました。腫瘍内科では血液腫瘍を扱うLeukemia teamと固形腫瘍を扱うSolid tumor teamに配属され、がんに対する治療の指針や保険のシステムの日本との違い、また末期のがん患者さんへの全人的ケアについて学んできました。ここで強く身に付いたのが「積極性」だったと思っています。留学当初は、毎朝の回診で求められるチームへのプレゼンひとつ取っても、他言語で実習をこなすことは容易ではありませんでした。また、現地の学生のレベルが高く、良い評価を得るための向上心やアピール力に圧倒されました。消極的な姿勢だといつまでもお客様扱いだと感じた私は、指導医に「自分ができること・できないが学びたいこと」を主張し、都度フィードバックを貰いました。そうした姿勢がチームに認められたのか、徐々にやらせて頂けることの幅が広がっていった(手技をはじめ、他科へのコンサルト、検体の提出、ショートトーク等)ことを実感できました。
協定校としての規定の期間は2か月間でしたが、Johns Hopkins大学で教授として活躍されている日本人研究者の井上尊生先生の研究室に自らアプライをし、留学中の残りの期間中、所属をさせて頂きました。私が現在名古屋大学で行っている基礎研究(大脳皮質層構造形成期に、分化途上細胞が神経幹細胞のエレベーター運動の範囲を制限し、正常な脳形成を助ける)についてプレゼン・ディスカッションを行ったり、同研究室のテーマである細胞走性の解析手法について学んだりしてきました。共同研究という形ではありませんが、帰国後、名古屋大学で行っている研究テーマに関する査読付き論文を国際誌Developmentに筆頭著者として発表することができました。また、期間中、製薬企業との連携部署を見学させてもらう、また米国で研究者として働く先生にインタビューをするなどの経験を経て、日本の病院の中だけではない働き方について目を向けることができたのも良かったと思っています。
そして今後の働き方に関して、ひとつ印象に残ったエピソードがあります。腫瘍内科での実習中に、20代の若さで末期の肝臓がん(日本では見られない特殊なタイプのがん)になった女性を担当させて頂く機会がありました。彼女のがんは10代から再発を繰り返し、とうとう抗がん剤不応・切除不能となってしまい、私の担当時には浮腫で歩くこともままならず、呼吸も満足にできず人工呼吸器で管理された状態でした。彼女の部屋にはご両親とごきょうだいが毎日通い詰めで、彼女を勇気付けていました。お母さまは彼女の前では決して涙を見せず、身の回りのお世話をなさっていました。彼女は緩和ケアを選択しなければならないという医療チーム判断が出ており、彼女とご家族はそれを受け入れなければなりませんでした。担当中のある日、チームでの病室回診中に、私は泣くことを我慢できませんでした。それを見たお母さまが、病室から出た私の後を追って、泣きながら私の手を握り「ありがとう」と言って下さったのです。言葉の壁はありませんでした。彼女がホスピスに行くその日まで、私は彼女とそのご家族を担当し、交流を重ねました。私は、医療人は患者さんに対し施せる全ての治療を施すべきと思っていますが、生き方を選ぶのは患者さん次第であり、その選択を同じ目線で考え、人生を見届ける姿勢を忘れてはいけないと感じました。今後も変容するであろう社会の中で、失われない医師の価値について考えさせられました。
 派遣仲間の岡本くんと
派遣仲間の岡本くんと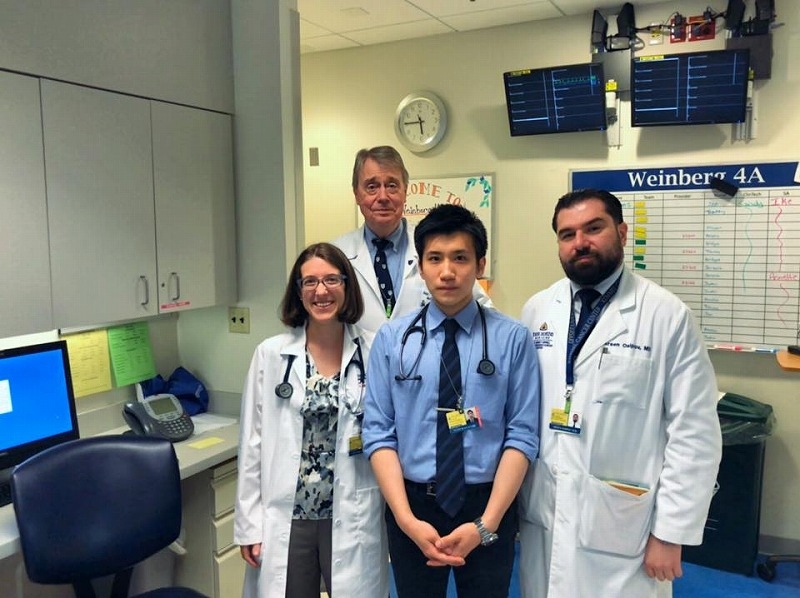 腫瘍内科のスタッフと
腫瘍内科のスタッフと 名大外科の先生にご飯に連れて行って頂きました
名大外科の先生にご飯に連れて行って頂きました 研究室のメンバーにもお別れ会を開いて頂きました
研究室のメンバーにもお別れ会を開いて頂きました
Duke University/McGill University 留学体験記
尾崎 遥(デューク大学)
私はNorth Carolina州のDurhamにあるDuke UniversityとMontrealにあるMcGill Universityにてそれぞれ1カ月間実習を行いました。どちらも医学分野以外においても世界的に名の通った大学であり、今回このような貴重な機会を頂けて非常に光栄に思います。この体験記では「Duke Universityでの実習」、「Durhamでの生活」、「McGill Universityでの実習」、「Montrealでの生活」、「実習全体を通して学んだこと」という大きく5セクションに分けて論じていきます。私の体験をなるべくありのままに語るため多少文章としての一貫性は失われますがご容赦ください。
Ⅰ.Duke Universityでの実習
DukeではHematology-Oncologyのプログラムということで、OncologyとHematologyのoutpatient clinicで1カ月間お世話になりました。実習内容について述べる前に、まずアメリカのOncologyのあり方について先に説明をしておきます。
アメリカではがん患者は全てOncology Departmentが診ています。もちろん外来患者の治療だけでなく、入院患者の管理も行っています。そしてOncology Departmentは臓器または疾患別にPulmonary OncologyやMalignant HematologyのようなDivisionに分けられており、それぞれの医師が自分の専門の腫瘍の診療を行っています。日本の場合だとまず臓器別に科を分けて、それぞれの科が悪性疾患も良性疾患も診ていますが、アメリカだとまず良性疾患と悪性疾患をスパッと分けてからそれぞれの専門分野に分かれていくという違いがあります。他施設でも大きな病院であれば同じだと思いますが、Dukeの場合だとDuke Cancer CenterというOncology単独の施設がクリニックと病棟に併設して存在していて、外来での診察と治療は全てここで行っていました。
実習の内容としては、基本的に曜日ごとに指定されたクリニック(月:GYN、火:GI、水、木:Malignant Hematology、金:Benign Hematology)に行き、attending(またはresident)のスケジュールから割り当てられる数人の患者の診察を行うというものでした。具体的には、割り当てられた患者の情報を電子カルテや他院から送られてくるファックスから事前に仕入れて診察室に向かい、問診と身体診察を行った後attendingにプレゼンを行い、attendingの本診察に同行するといったスタイルでした。(補足ですが、アメリカでは一人の医師が担当する診察室が複数あり、先に患者が部屋へ誘導され、医師が後から入って来て診察を行います。)本診察の後にはカルテ記載も行います。事前研修で何度も行ったH&Pそれそのもので、トレーニングしておいて本当に良かったと感じました。attendingのスケジュールのほとんどが再診患者なので当然再診患者を診る機会が多かったですが、新患を割り当てられること少なからずあり、その時は何十枚も送られてくるファックスの資料を必死になって読み漁って診察を行っていました。attendingは忙しそうにしていながらも皆フレンドリーで、プレゼンの後や本診察の後にはその疾患や患者背景についてフィードバックをもらえたので自分で経験しながら学んでいく実感が得られました。同じローテーションに他の学生がいなかったことと病棟業務にはノータッチだったことは少し残念ではありましたが、外来で多くの患者に触れることで癌患者の症状や副作用のプレゼンテーションや治療、フォローアップの流れをイメージを掴みながら学ぶことが出来たので非常に有意義だったと感じています。また、attendingが不在の日には他のクリニックにお邪魔することもあり、その一例として一度だけでしたがSickle cell diseaseのクリニックで実習を行う機会を頂きました。日本では滅多にお目にかかれない疾患で、ましてや専門外来があるなんて日本では考えられないので、本当に貴重な経験が出来ました。
Dukeでの実習は驚きに溢れたものでしたが、中でも特に驚かされたことが大きく3つあります。
一つ目はPhysician Assistant (PA)の存在です。Merriam-Websterの辞書で"physician assistant"と引いてみると"a person certified to provide basic medical services usually under the supervision of a licensed physician"と出てきます。定義を見た感じではPAの業務は多様なので他の病院でPAがどのような役割を担っているは分かりかねますが、少なくともDuke Cancer Centerではそれぞれのattendingに1人のPAがついて、その日のスケジュールの管理や事務作業だけでなく、予診や簡単なフォローアップまでも行っていました。分業化を積極的に行いcomedicalを増やすことで医療を円滑に効率よく進める工夫を垣間見えることが出来ました。
二つ目はclinical trialsが非常に活発に行われていることです。クリニックの廊下を歩けばclinical trialsへの参加を呼び掛ける貼り紙がそこかしこに貼ってあることに気づきます。さらに驚くことに、clinical trials専門の職種があり各フロアにオフィスがあるのです。その人たちは各trialのenrollment/requirementの管理や評価データの取得と管理を専門に行っていました。医師だけで通常の臨床業務をこなしながら、それぞれ異なるtrialの内容や適応、除外項目などを覚え、通常の治療より頻回の病勢評価を行い、同時に複雑で多い書類の記入や管理を行うというのはなかなか骨の折れる仕事です。従ってこうして再び分業化をうまく活用することによって多数存在するclinical trialsを推進力を落とす事無く進められているのだと実感しました。
三つ目はアメリカの保険制度についてです。アメリカでは低所得者向けのMedicaidや高齢者向けのMedicareなど一部公的保険もありますが、一般の人は民間の保険会社に入るのが基本です。しかも州ごとに保険会社や保険プランが異なるため、受けられる医療はその人の保険プランのカバー範囲や自己負担額に大きく左右されます。これは毎週火曜に行っていたGI Oncologyでの話なのですが、担当していたattendingはneuroendocrine tumor (NET)の患者を多く診ていました。NETの3 rd line以降の新しい治療としてLutathera®という放射性物質を結合させたソマトスタチンアナログがあり2018年1月29日にFDAの承認を得ています。しかし、私が実習を行っていた2018年4月当時ではNorth Carolina州のどの保険会社も治療費をカバーするかどうかの結論を出していなかったために高額な治療費を全額自己負担するほかに誰も治療を受けられないというのが現実でした。こうして治療が受けられず落胆して帰っていく患者を私は何人も見てきました。中にはDuke Cancer Centerを頼って郊外からはるばる片道5時間以上かけてセカンドオピニオンを求めに来た患者もいました。国の認可を得たからといって実際の治療に使えるとは限らない。新治療に期待を寄せる患者にとってなかなか残酷な現実でした。Lutathera®に関しては各保険会社が早急に態度を表明することを願って止みません。
Ⅱ.Durhamでの生活
毎年お世話になっているホストファミリーのJennyとFredの家に今年もお邪魔してアメリカのライフスタイルを満喫することが出来ました。ラボは違いますが2人ともDukeの微生物学の研究室で働いています。2人とも人当たりが良く優しくて、南部の名物であるポークのBBQやピーカンナッツパイを食べに行ったり、地元の食材を使った行きつけのイタリアンレストランに誘ってもらったり、一緒にエッグのデコレーションを作ってイースターを祝ったりと楽しく日々を過ごしていました。2人が週末にボランティアで遊歩道の整備を行っている郊外のEno River沿いの公園に連れて行ってもらって愛犬のBirdieの散歩をしたこともあります。
DurhamはDuke Universityによって成り立っている大学都市です。私は勝手に"Durham"の"D"は"Duke"の"D"だと思っています。街は落ち着いていて緑が多く、キャンパス外でもストリートやカフェには"DUKE"のロゴの入ったフーディーやTシャツを着た学生や大学関係者を多数見かけます。私は大学の図書館や街のカフェでDukeのステッカーがこれでもかというくらいに貼ってあるMacBookを広げて一生懸命課題に取り組む"Blue Devils"に日々刺激をもらっていました。勉強するのにこれ以上の環境を求めるのは罰当たりというものです。
Ⅲ.McGill Universityでの実習
McGillでもOncologyのoutpatient clinicで1カ月間実習を行いました。因みにですがMcGill UniversityはEBM発祥の大学としても有名です。私が通っていたのは第二のteaching hospitalであるJewish General Hospital (JGH)。ダウンタウンから地下鉄で5、6駅程度の比較的街中に位置しています。McGillがあるMontrealはフランス語圏のQuebec州ですが、McGillはEnglish系のルーツを持つ大学だからか医師同士の会話は英語、カンファも英語でした。患者もほぼほぼバイリンガルなので英語でのコミュニケーションに苦労することはほとんどありませんでした。Torontoがあるお隣のOntario州に行けば全てが英語なのでバイリンガルであるのも当然と言えば当然です。
率直に言うと、Oncologyのシステムに関していえば、アメリカとカナダとでは特に差が無いように思いました。JGHにもSegal Cancer CenterというOncology専門のクリニックと外来治療施設があり、良性疾患を診る一般のクリニックとは別で存在していました。また私が経験した限りでは治療法やclinical trialsの活発さにおいてもアメリカとカナダとではあまり違いが無いように感じました。実習の途中で、アメリカのMedical Schoolを出て2年間residencyをしてから出身のMontrealに戻ったresidentと話す機会があったのですが、少なくともOncologyの分野ではアメリカとカナダ(Quebec)で大して差は無いということをその人も言っていました。差があるとすれば、治療までのスピーディーさにおいてアメリカの方が優れているとのことでした。ただ、もちろん病院の規模やスタッフにもよるのでしょうが、Duke Cancer Centerと比較してJGHはよりGeneral Oncologyの色が強いように思いました。というのも、Segal Cancer Centerでは多くのドクターが複数のDivisionに所属しており、曜日により異なるがん種の外来を行っていたからです。例えば、私がお世話になっていたattendingの一人は月・金で乳がんとGIの外来を行い、水曜には肺癌を診ていました。少なくとも日本ではなかなか見られない光景なので私にとっては衝撃的でした。その先生には、「日本ではPulmonologistが肺癌の治療をしているのか?」と怪訝な顔をされたのを覚えています。やはり日本とカナダ(そしてアメリカ)には癌診療の体系に大きな違いがあるのだと再認識しました。
実習内容も基本的にDukeでのものと同じく、毎週曜日ごとに外来が入っているattendingのところに行きアサインされる患者の問診・身体診察、プレゼン、カルテ記載を行うというものでした。乳がん、GI cancer、肺癌、GU cancer、メラノーマなど、ここでも多様ながん種の患者を診察する機会を頂き大変勉強になりました。
ここまでの感じだとアメリカとカナダの医療に違いは無いのかと思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。おそらく最大の違いとして保険制度が挙げられます。カナダの医療費は無料で、全て税金で賄われています。ただ、治療薬代は自己負担になるため一般の人々は保険に入って自己負担額を軽減します。初めてJGHに行ったとき、診療を終えた患者が皆受付で次回の診察や検査の予約だけをしてそのまま病院をあとにする姿が印象的でした。しかし、この医療費無料というのも良いことばかりではないようで、患者の受診閾値が低いため医療機関での「待ち」が問題になっているようです。特に救急外来においてその問題が顕著化しているようで、私が診た1人の大腸癌術後の患者は以前腰痛で救急外来を受診した際に12時間以上も待たされたと呆れ顔で語ってくれました。骨メタの関与が否定されただけ幸いだったと思いますが。
Ⅳ.Montrealでの生活
Montrealは「北米のパリ」と呼ばれるだけあって、街はきれいでオープンテラスのカフェが随所に見られます。特にダウンタウンにある旧市街は趣深く、石畳の上を馬車が行き交い、どこからかストリートパフォーマーのサックスの音色がきこえてきます。旧市街の心臓部にあたるノートルダム大聖堂はパリのサント・シャペルを彷彿とさせる青を基調とした壮麗な装飾で有名で、一見の価値はあります。
Montrealでは民泊サイトのAirbnbを利用して病院から徒歩5分くらいの地下鉄の駅近くに滞在していました。同じ家には私と同じくロングステイしている3人の学生がいて、1人は同じくMcGillの病院実習に来ていたドイツ人の女の子で、もう1人はMontreal Universityの工学部のドクターコースに入っているイタリア人の男の子、残りの1人は同じくMontreal Universityで物理学を専攻しているフランス人の女の子でした。毎晩夕食の時間になると、ぞろぞろとダイニングルームに集まって来てはご飯を食べながらお互いの国の話をして楽しい時間を過ごしました。ドイツ、イタリア、フランス、日本。はたから見るとどこかの国際会議みたいです。G4とでも呼びましょうか。
Ⅴ.実習を通して学んだこと
最後のこのセクションではアメリカ、カナダでの合計2か月間の実習を通して学んだ大きく2つのことを取り上げたいと思います。
一つ目は、日本のポリクリが医学教育の全てではないということです。アメリカもカナダもですが、向こうでは"exposure"を非常に重視しているように思いました。学生に臨床の現場を見せるだけでoutsiderのまま終わらせるのではなく、学生を臨床の現場に置いて自分で考えさせ、この患者の現在の状態をどう評価するのか、その評価に従うと今後の治療はどうなるのかまで突き詰めることで実臨床での思考回路や実際の患者管理それそのものが身になっていくのだと感じました。またこの方式だと、求められるレベルが高いため、自分の出来ること、出来ないことが明白になり今後乗り越えていくべき課題がみえてくるという利点もあります。自らの経験の中から学びを生んでいく大切さを学びました。
二つ目は、EBMの本当の意味についてです。正直に話すと、私は今回の留学に行くまでは、EBMとはガイドラインに則った標準治療を厳格に行うことだと思っていました。しかし、実際には日々報告される臨床試験の結果から、患者特性や予後因子などのサブセットに分けた時に、現行の標準治療が必ずしもその患者にとって最良のアウトカムをもたらす治療になるとは限らないのだということを知りました。(もちろん後々にはそうした因子を考慮した標準治療が次々にガイドラインに反映されて、ガイドラインがより複雑で分厚いものになっていくのでしょうが。)McGillのOncologyにいた時に、毎週行われていたTumor Boardに参加していたのですが、そこでドクターたちが検討症例の治療方針について論文を引き合いに出しながら活発に議論していたのを鮮明に覚えています。このことから、EBMとは日々生み出されるエビデンスを正しく解釈して、患者の特性や希望と照らし合わせながら現状最適と思われる治療を提供することなのだと学びました。
最後に、今回このような留学という貴重な経験をサポートしてくださった長谷川先生、粕谷先生を初めとする国際連携室のスタッフの皆さん、受け入れ先のDuke、McGillの先生方、ホストファミリーのJennyとFred、そして両親にはこの場を借りて最大の感謝を捧げたいと思います。どうもありがとうございました。
 Duke West Campus
Duke West Campus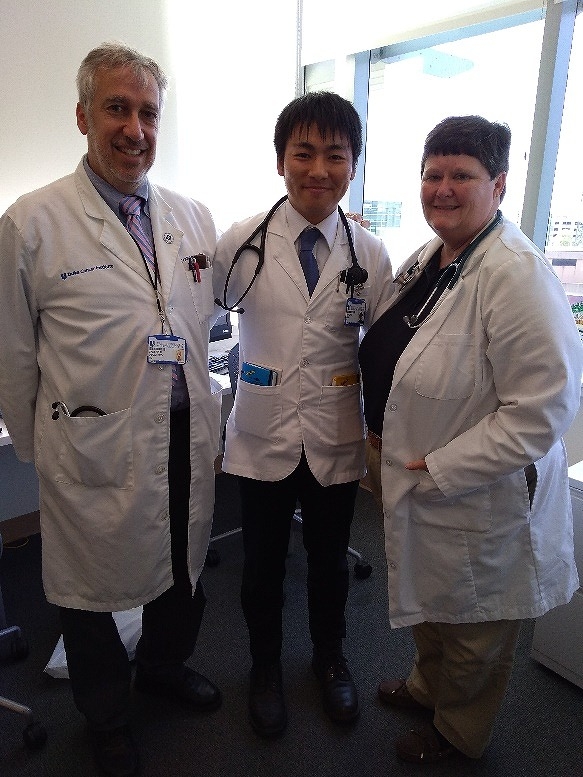 Duke Hematology Oncologyの先生方と
Duke Hematology Oncologyの先生方と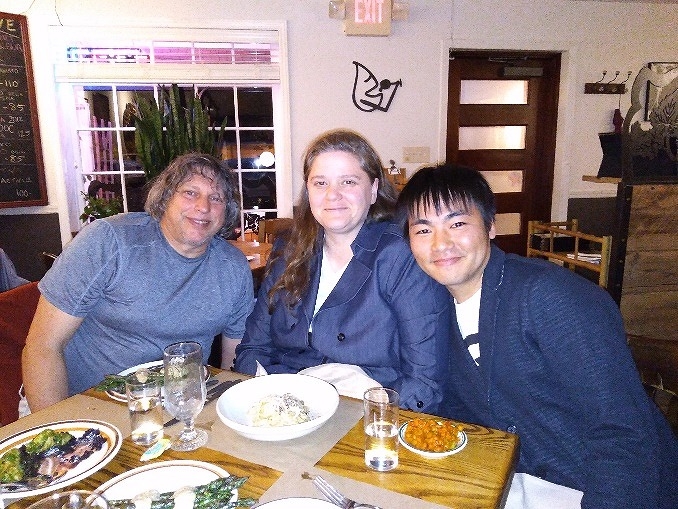 Jenny、Fredと地元のイタリアンレストランにて
Jenny、Fredと地元のイタリアンレストランにて Dr. PanasciとSegal Cancer Centerにて
Dr. PanasciとSegal Cancer Centerにて
Tulane大学留学記2018 ~音楽の溢れる街で~
落合 伸伍(チューレン大学)
『今日も、青く高い空を眺めつつ、オールドファッションな路面電車が行き交う大通りを進む。バーボン通りから二つ目の路地を曲がると、まず耳に飛び込んで来るのはトロンボーンとサックスの音である。強い日差しに汗ばむ背中、喉の渇きを潤すために冷たいコーヒーでもと思ったが、あちこちで聞こえるジャズの生演奏に思わず足を止めてしまうから、なかなか飲み物にありつけない。ついつい夢中になって3組目のバンドを聴き終え、「bravo!!」と心の中で唱えて1ドル札をさっとバケツに放る。そして気づくのだが、空の様子が打って変わっておかしい。灰色と黒の絵の具を掻き回したような曇天である。そこから、上半身の汗が大粒の水に流されるまでは数分で、直ぐに近くのカフェに逃げ込む。ここで出会ったピアノの演奏にも没頭していたら、オレンジ色の日差しがすでにピアノの足元まで伸びていたから、南部の偉大な大河に向かって散歩を再開することにする。土手沿いに歩くと、体に当たる風は強くもう体はすっかり乾いていた。茶色く濁った急流の端に停泊していた蒸気船から聞こえる汽笛は、この街の巨匠の名曲を奏でていて、とても素敵だった。What a wonderful world!』
ニューオーリンズでは、このような土日をよく過ごしました。休日は街の様子を"聞き"に出かけたくなる『音楽の街』のTulane大学にて、臨床実習に参加させていただきました。実習参加前の準備中、およびTulane大学での実習中にはたくさんの困難にぶつかることになりました。患者さんやドクターたちのクセの強いアクセントに苦労し、会話に追いて行くのがとてもストレスフルで、部屋に戻ると疲れてベッドに倒れこむこともありました。しかし、大胆に、そしてアクティブに行動することでこうした困難を乗り越えることができたのは、陽気な音楽の'力添え'あったからだと思います。(本当に。)
まだ少し肌寒い頃のニューオーリンズで、最初の実習科は血液・腫瘍内科でした。初めてのアメリカ臨床実習参加に興奮し、緊張していたからか、私の最初の挨拶はカミカミでした。挨拶Take2をお願いすると、フェローのドクターと学生たちは笑って許してくれ、それが良いアイスブレークとなった気がします。この科での学生実習は、コンサルチームに所属しフェローのドクターと一緒に入院患者の治療方針を考えることでした。血液・腫瘍内科には様々なチーム(良性血液疾患のグループ、白血病グループ、固形癌チームなど)があり、私は固形癌のチームに参加することになりました。学生の最初の仕事は早く、入院患者さんのアセスメントとプロブレムリストの洗い出しをさっとこなしておりました。聞くべきことは基本的に日本での実習と同じでしたが、患者さんの様々な表現や独自の現地アクセントに苦戦し、私はその2倍以上の時間を掛けてしまいました。ディスカッションタイムの後フェローと共に患者さんを尋ね、再度情報の確認をした後に、二度目のディスカッションタイムではプランの検討となりました。ここで苦戦を強いられたことは、治療戦略のアイデアを現地学生と比べて多く出すことができないことでした。ディスカッションについていくこと、質問をぶつけることはできましたが、自らのアイデアで議論することができず悔しい思いをしました。
肌に当たる風が暖かくなってきたころ、次のローテーション先は整形外科でした。アメリカの外科系の朝は早いと聞いていたし、アメリカ医療ドラマの早朝ラウンドにて患者さんをたたき起こすシーンを何回か見ていたので、「予習ばっちり準備満タン」といった感じでした。しかしながら、真っ暗なうちからラウンドに出て、1時間程度のカンファレンスの後に、ようやく明るくなったと思った時から手術がスタートするとなると、濃厚な朝の業務時間に既に体力の半分以上を持ってかれている状態でした。整形外科には、スポーツ、外傷、小児、再建の4グループがあり、1週間ごとにそれぞれのグループで学ばせていただきました。ガンショットの症例が多く、骨折と銃創の対応を整形外科の外傷グループにて勉強させていただき、日本ではほぼお目にかかれない銃創と骨折を見られたことは良い経験(お土産話)になりました。
ニューオーリンズに来て1か月以上も経てば、実習や生活にもすっかり慣れてきていました。ベニエ(恐ろしく甘い揚げ菓子)やポーボーイ(ボリューム満点のナマズサンド)などのニューオーリンズで有名な食べ物に挑戦しましたが、ただ一つ、回避し続けていたのはcraw fishでした(なんたって、ザリガニですから)。チュレーンの友人たちと参加したcraw fish partyでは、売り切れていたことにほんの少しだけ安堵し、野外のいたるところに積み上げられていたザリガニの頭の残骸を見て、少しだけ物怖じしていました。その後結局、招待していただいた夕食会で再びcraw fishに出会うことになったので、今度こそはという意気込みで掴んでみました。強い香辛料で煮込まれた彼らの殻は赤く硬く、苦労してはぎ取ると、食べられるのは人差し指の大きさにも満たないくらいのサイズでした。香辛料の味が強く、想像していたほどエビのような味はしませんでした。ニューオーリンズ周辺でとれる海産物は豊富(もちろんエビも美味しい)なのにザリガニたちの方が人気な理由は、ニューオーリンズの文化だから、ということでした。食べづらく小さな身をゆっくり時間をかけて取り出すことで、世間話を楽しむ時間を作るそうです。ニューオーリンズの人々ののんびりとした雰囲気や生活に根付いている食文化なんだなと感じました。
チュレーン大学医学部の新4年生がUSMLE Step2の受験を終えて新たな選択実習に参加するころ、私が次に向かった科は眼科でした。実習先としては想定外の科で勉強することになり、眼科特有の医学用語にかなり苦戦を強いられましたが、一緒に回っていた学生やレジデントのサポートもあり、学ぶことが多く大変実りある実習となりました。外来では初診を任されることになっていたので、眼底鏡や細隙灯の使い方にも苦労しましたが、糖尿病性網膜症、緑内障、白内障などの典型的所見を多く見ることができました。そして、体にまとわりつく熱気と少しばかり痛みを感じるような日差しに体力を奪われる季節になると、チュレーン大学での実習も最後のローテーションとなりました。最後はFamily medicineでの外来実習でした。さまざまな疾患と問題を抱える患者さんを総合的に診る科であるため、情報収集にかなり時間をかけることになりました。これまでに学んできたさまざまな臨床実技が役立ち、アテンディングのドクターにお褒めの言葉を頂くことができ、とても嬉しく思いました。
今回のチュレーン大学留学は、これまでの留学以上に充実し満足できるものとなりました。現地の学生だけでなく、海外の地で奮闘・活躍されている日本人の先生方や研究者の方々とも親交を深めることができ、いろいろな人達がお互いサポートし合って目標に向けて日々努力していることを改めて感じました。今回のこうした経験は、私の新たな目標へ向けた大きな土台、そしてモチベーションとなっています。今回の留学を支援して頂いた先生方・家族・友人の皆様には心から感謝しております。
 American College of Physicianの学会に参加して
American College of Physicianの学会に参加して 支えてくれた日本人ドクター・研究者の方達と
支えてくれた日本人ドクター・研究者の方達と Primary Careの実習を終えてDr.Bertha Danielsと
Primary Careの実習を終えてDr.Bertha Danielsと バーボンストリートのお気に入りのジャズバーにて
バーボンストリートのお気に入りのジャズバーにて
留学体験記
寺島 まり絵(チューレン大学)
1. はじめに
私はTulane大学に三カ月間留学させていただきました。指導医と研修医が専門的な内容を英語でディスカッションしている中参加するのは難しかったですが、事前研修で教えてもらった討論への割り込み方などを思い出しながら積極的に参加しました。ここにこの臨床実習留学で行ったことや感じたことを示します。
2. アメリカ内科学会
留学の中で最も印象に残ったことの一つにニューオーリンズで行われたAmerican College of Physicians Internal Medicine Meeting(アメリカ内科学会)に参加できたことがあります。広大な開場にアメリカ各地からのみならず世界各国から医師が集まり、普段の街も華やいである種、夢のようでありました。著名な内科医の方とお話しできたり発表を聞いたりできて、学生のうちに行けたことをとても光栄に思います。また、日本から参加された若手医師たちの姿もとても刺激的でした。研修医一年目にして自らの研究で学会発表を勝ち取った方や、Doctor's Dilemmaの日本代表として医学知識に関してネイティブと競った先生方を見て、やる気と努力により研修は如何様にでもなるということを再確認し身の引き締まる思いでありました。
3. 実習科
私は計4つの科で実習をさせていただき、その中には日本の実習にはない科もありとても興味深かったです。
(ア) ホスピス
ホスピスでの二週間の実習では、毎日看護師やボランティアの方の車に同乗し訪問看護を行い、身体診察や褥瘡のケア、服薬の管理を行いました。また、アメリカにはChaplainと呼ばれる宗教的側面から患者さんのケアを行う役職があり、葬儀に同行したこともありました。フォローしていた患者さんが亡くなることもあり、前の週に「もう一度来るので必ずまた来週お会いしましょう」と言ってお別れした分つらいものがありました。
(イ) Culinary Medicine
日本語をあてるなら料理医学となります。シェフから医師に転身した方が、医師や医学生があまりにも栄養学を知らないことを嘆き開設した料理教室で、医師や医学生、患者さんや一般の方々に向けて健康によい食事の作り方を教えています。例えば心不全の患者さんに塩分を2.4g/日以下に抑えた食事の作り方を教えるなどしました。また、大手コンビニの代表の方を招待し塩分と脂質を抑えたコンビニ食の提案をしました。実習の最後には不飽和脂肪酸について新しい論文をもとにプレゼンをする機会も与えられ実習の成果を出すことができたと思い満足しております。
(ウ) 整形外科
整形外科の実習はオペの見学がメインでした。Tulane大学は非常に大きなトラウマセンターとして機能しておりamputationのオペも術野に入れさせてもらいました。アメリカの研修医は全体として日本の研修医より年上なのですが、女性の研修医が術中ずっと患者さんの脚を引っ張って股関節の視野を確保しているのを見て体力と力強さに圧倒されました。しかし、人口膝関節置換術の術後翌日に退院させるなど本当に退院が早く、患者さんの不安が大きいのではないかと思う点もありました。
(エ) 病理
Tulaneの病理はSurgical pathologyとClinical pathologyに分かれていて、私はSurgical pathologyで実習をし標本の解説をしていただきました。日本でいうcarcinoma in situはアメリカでは癌と分類しない、など定義が異なるものもあり興味深かったです。また、Tulane大学ではカルテのdictationシステムを使っており、医師はカルテに記載したいことを録音し病院内にいる数人のカルテ記載担当の職員がタイピングするという仕組みになっておりました。ゆえに病理医は標本の切り出しをする際に両手がふさがっていても足元のペダルを用いて録音ができカルテの記録をすることができるというメリットがありました。しかし、一度録音がどの患者さんのものかわからなくなり翌朝カルテが書かれていなかったという事態が発生し、所見を述べる人と実際にカルテを書く人が異なることによるデメリットも見て取れました。
4. おわりに
アメリカに行く前はアメリカこそ医療先進国という印象がありそこで行われている医療が最も良いものであろうという漠然とした先入観を持っておりました。しかし、実際に三カ月間実習をさせてもらって、日本のほうが患者さんのための医療をしているという感想を持ちました。アメリカではグランドラウンドと呼ばれるカンファレンスがあり院内で行われている臨床研究の発表を聞いたり他院の先生を招いてレクチャーをしてもらったりする機会があり勉強になるとは思いました。しかし、研究で新しく得られた内容が臨床に反映されているかについては評価しがたく、病院同士の連携や術後の対応など患者さん側から見た時の医療の質は日本の方が優れていると思いました。ゆえに現在は、将来は日本で働きたいと思っております。
5. 謝辞
この留学を手配し支えてくださった粕谷先生、長谷川先生をはじめとする全ての方にお礼申し上げます。
 アメリカ内科学会receptionの様子
アメリカ内科学会receptionの様子
国立台湾大学病院
北村 柾騎(国立台湾大学)
私はこの度、3月から12週間、国立台湾大学で留学させていただきました。もともと英語が苦手であったため、留学すること自体全く考えていませんでした。しかし、学年が上がっていくにつれて、学生時代にしかできないことを何かしらしてから卒業したいと思い始め、また、留学にいった方々の話を聞いているうちに留学への憧れが強くなったため、留学を決意しました。
もともと、台湾は親日国で、毎年多くの台湾人が日本に来て、日本からの旅行者も多いと聞いていたため、一度行ってみたいと思っていました。そして、台湾では医療の大部分で英語が使われているらしく、実習で多くのことを学ぶとともに、非英語圏における英語でも医療教育とはどのようなものかを自分の目で確かめたかったため、今回私は国立台湾大学を選びました。
国立台湾大学病院は病床数2300床を超え、毎年6500人以上の外国籍患者が受診しに来るそうです。実際、私が実習しているときに何度も外国籍の患者を診る機会があり、そのたびに医師は慣れたように英語で診察していました。そんな中、私は産婦人科、皮膚科、家庭医学、内分泌内科、一般外科でそれぞれ2~3週間ずつ実習させていただきました。
まず初めの産婦人科は、産科、婦人科、不妊治療科をそれぞれ1週間ずつ回らせていただきました。産科では、日本ではあまり行われていない無痛分娩や、先天性心疾患を患った子の分娩といった特殊なケースの分娩をたくさん見ることができました。婦人科では、午前は手術見学、午後はカンファレンスに参加した後、現地の学生に混ざって外科実習などをしました。台湾大学では、婦人科手術においてロボット手術が頻繁に行われており、実際にダヴィンチを操作させていただきました。台湾では産婦人科におけるロボット手術は保険適応外であるにもかかわらず、週に3-4件ほどロボット手術が行われているそうです。日本では産婦人科疾患に対してあまりロボット手術は行われていなかったため、その違いに驚くとともに、ロボット手術を見学するよい機会となりました。また、その後の外科実習では現地学生のグループに混ざって実習を行いました。不妊治療科では、不妊治療に来る患者の数がすごく多く、毎日最後にその日の患者についてカンファレンスを行っていましたが、毎日数えきれないほどの患者について話し合っていました。日本からも多くの患者が受診に来るそうで、レベルの高さを実感しました。
皮膚科は台湾で一番人気の科で、美容皮膚科もカバーしているため、どのようなものか一度見てみたく、選択しました。実際、毎年成績上位の人しか皮膚科医になれないそうです。実習は基本的に外来とオペ見学でした。自分のやれることは少なかったですが、教科書でしか見たことがないような皮膚科疾患を事細かに教えていただき、とても勉強になりました。珍しい疾患だけでなく、大学病院であるにも関わらずニキビや肌荒れで受診する患者が多かったのには衝撃を受けました。台湾の美容皮膚科で一番有名で、独自の化粧品ブランドを立ち上げている先生の外来も見学させていただいきました。
次の家庭医学(family medicine)では一般病棟、緩和病棟、外来に分かれて一週間ずつ実習しました。病棟では、一つのグループに入れていただき、朝、レジデントの先生と患者の回診に行き、その後カルテを見ながら病状について話し合い、夕方から上級医の先生と再び回診といったものでした。患者は英語を話せないため、自分で問診等はできませんでしたが、レジデントの人と共に、毎日身体所見などは取らせていただきました。緩和病棟では、それに加えて、患者や家族の心のケアや疼痛管理といった、日本の実習ではあまり学ぶことができなかったことも学べました。外来では、緩和外来・禁煙外来・減量外来・旅遊外来など日本では珍しい外来の見学や、大学病院だけでなく、外のクリニックや訪問看護にも連れて行っていただきました。
内分泌内科では病棟、外来、甲状腺エコーなどをバランスよく実習できるようにスケジュールを組んでいただきました。台湾では糖尿病患者数が多いため、国が糖尿病スクリーニングを積極的に勧めており、日本ではあまり見ないような検査等を見せていただきました。また、駅のポスター等にも血糖測定器の広告がたくさん張り出されており、糖尿病患者の多さを物語っているなと感じました。しかし、台湾では糖尿病患者だけでなく内分泌疾患の患者数もものすごく多く、甲状腺エコーは毎日50件程度されていました。教授の外来に至ってはほぼ内分泌疾患の患者だけで一日約200人も来ており、驚くとともに、たくさんの症例を見ることができました。
最後の一般外科では、基本的に毎日、その日の手術で興味のあるものを1~3件見学させていただきました。ここでも婦人科同様、ロボット手術が行われており、ロボット手術の利点欠点を聞きながら手術見学をさせていただきました。ちょうど私が回り始めた週に新しい学年の実習が始まったため、医師、学生ともに忙しそうでしたが、時間を見つけては、なぜこの患者は手術をすることになったかなどを一緒に話し合うなどして、とても勉強になりました。
実習以外の生活についても触れておきたいと思います。私は、台湾大学の寮である景福会館というところに3か月滞在していました。そこは全部屋2人部屋であり、名古屋大学から一人で行った私は、他の留学生とそこに住んでいました。はじめはあまり乗り気でなく、ほかの寮を探したりもしました。しかし、ふたを開けてみると、ルームメイトと毎晩自分の国の話をしたり、休日は一緒に出かけたりと一人で生活するよりも楽しい日々を過ごすことができました。また、その寮にはたくさんの留学生がいたため、みんなで毎日のように夕食を食べに行ったり、時々飲みに行ったり、さらには誕生日会まで開いてもらいました。台湾にいながら世界中に友達ができるとは思ってもいませんでしたが、おかげで、暇を持て余したり、寂しさを感じたりすることなく、かけがえのない12週間となりました。
最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった粕谷先生、長谷川先生をはじめとする国際連携室とフロンティア会の皆様、国立台湾大学の皆様にこの場を借りて感謝の意を示したいと思います。本当にありがとうございました。
 他の国の留学生と共に
他の国の留学生と共に Family Medicineの先生方と
Family Medicineの先生方と
香港中文大学体験記
篠田 諭(香港中文大学)
名古屋大学医学部医学科6年の篠田諭です。私は中国、香港にある香港中文大学に2ヶ月間留学致しました。香港は1997年までイギリスにより統治されていた過去があり、今でもイギリスの文化が各所にみられます。香港中文大学付属病院の名前はPrince of Wales hospitalであり、これ一つ取りましても統治時代の面影が垣間見られます。なお世界史に詳しい方ならばPrince of Walesと聞くと、第二次世界大戦時のイギリス海軍主力戦艦の名前が想起されるのではないでしょうか。
香港での滞在先は病院に隣接した学生寮です。現地の医学生がメインで利用するため、必然的に留学生は相部屋です。私は同じ名古屋大学の近藤優樹君と一緒に二ヶ月間過ごしました。私は当然、家族以外の人とそのような長期間過ごした経験などなく、少し不安を覚えました。しかし幸運にもそれは杞憂で終わりました。当然ある程度の配慮は必要ですが、むしろ楽しく過ごすことができました。今では彼は私の親友であります。
私は耳鼻咽喉科と産婦人科にて各一ヶ月お世話になりました。香港中文大学の耳鼻咽喉科はイギリス人の教授を筆頭に9名のスタッフで運営されており、鼻腔内疾患から難聴、頭頸部癌などを治療対象としています。スタッフの皆さんはとても教育的であり、私に対し熱心に指導して頂きました。この点は日本での臨床実習と同じです。数々の問いかけをされましたが、中でもNPCは印象的でした。皆さんはNPCをご存知でしょうか。聞くとNPCはnasopharyngeal carcinomaの略であり、直訳すると鼻腔咽頭癌?とまではわかりましたが、皆目見当がつきません。先生曰く、香港ではかなりメジャーな癌とのこと。寮に帰り調べると上咽頭癌のことであり、確かに東南アジア、中国南部で多いとのことでした。いわれてみれば病棟にも外来にもNPCの患者は後を絶たず、なるほど多いなと実感したものです。さらに上咽頭癌はEBウイルスや家族歴が発症リスクとなりうるため、香港ではEBウイルス感染の有無、上咽頭癌の家族歴をルーティーンで記載しておりました。こうしたその土地特有の疾患や対処法を肌で実感できるのも留学の醍醐味ですね。
また耳鼻科には現地の医学生がたくさん実習に来ておりました。香港には医学部を設置している大学が香港大学と中文大学の2つしかありません。さらに土地の割に多い人口、地価の高さから中流階級以上しか住めないという土地柄、熱心な教育への投資から必然的に医学部に入学できる人たちは紛れもないエリートです。彼らの持つ医学の知識、英語の流暢さは日本の医学生の比ではありませんでした。しかしかれらはとても気さくで、拙い英語を話す私ともとても仲良くしてくれました。異国の地で心細い私としては大変うれしかったと記憶しております。現地の医学生との交流も、留学ならではと思います。耳鼻咽喉科の1ヶ月は過ぎれば一瞬でありました。
次の一ヶ月は産婦人科です。中文大学の産婦人科は腫瘍、周産期などの日本でも見られる部門から不妊治療、女性泌尿器科、出生前診断などの日本では比較的珍しい部門まで多岐にわたり、非常に盛んでありました。しかし、盛んであることと教えていただけるかは別物です。残念ながら腫瘍、女性泌尿器科、周産期の先生は多忙であり、海外からの学生にかまっている暇はありません。朝の回診でも挨拶したはいいが帰ってこないなどざらです。こんな時皆さんならどうしますか?私は事前に配布された予定表を完全無視し、興味のある手術や予定には一切組み込まれていない不妊治療外来を勝手に見学しました。ちなみに香港の不妊治療は有名であり、治療成績も日本より明らかに優れていました。先生も時間に余裕があるのかかなり教育的であり、いいことづくめでありました。こうして自由に過ごしているうちに最終週に突入し、残るは出生前診断を残すのみとなりました。出生前診断は先天奇形や染色体異常を出生前に見つけるのが主な業務です。ところで皆さんは日本でダウン症の人を見かけることが時折あるかと思います。今思い返しますと、香港でダウン症の人を見かけることは二ヶ月で一回もありませんでした。その原因が香港の出生前診断です。香港では全例ダウン症のスクリーニングとして妊娠11-13週にNT(Nuchal Translucency)と呼ばれる胎児後頚部の浮腫を計測しています。この結果ダウン症疑いがかかった妊婦は羊水検査を受け、ダウン症の確定診断を得ます。こうなるとほぼ全例の妊婦が中絶の選択をし、結果香港においてダウン症が淘汰される訳です。日本とは明らかに違う倫理観であり、心底仰天したものです。皆さんはこの是非をどう思われますか?彼ら曰く、「むしろなんで日本はダウン症の検査すらしないの?異常なのは明らかなのに。」とのこと。私は「倫理的にできない」としか返答できませんでした。彼らの腑に落ちない顔が今でも思い出されます。香港では一人の子供に巨額の教育投資をするのが一般的であり、それに見合った見返りが到底期待できない子供を養育する余裕などないこともこの食い違いの一因かもしれません。こうした倫理観の違いからくる治療方針の違いを実感できるのも、留学でしか味わえない経験です。
 ルームメイトの近藤君と
ルームメイトの近藤君と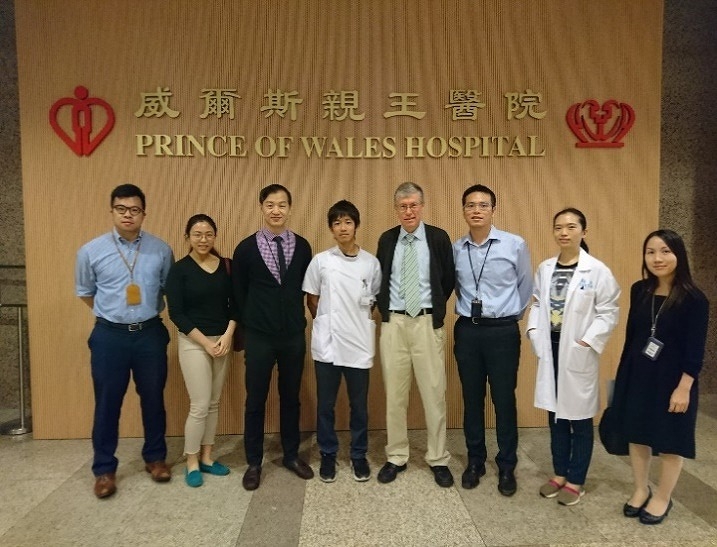 耳鼻咽喉科の先生方と
耳鼻咽喉科の先生方と
留学体験記
近藤 優樹(香港中文大学)
【香港について】
今回、私は香港中文大学に2か月間留学させていただきました。香港は愛知県と同じ位の人口にも関わらず医学部はたった2つしかないため、学生は優秀な人ばかりです。部活やバイトなどもしないそうです。また香港は高等教育が全て英語で行われており、医療スタッフや学生は英語がとても堪能です。が、上の先生は広東語訛りが強い事もあり、若い人ほど流暢な印象でした。香港の人々は基本的にみな親日で、先生も含め日本に何度も行ったことのある人が多くいました。看護師さんも「こんにちは」と日本語で挨拶してくれたり、「この前大阪行ったよ!」「ガンダム知ってるぜ」などと話題に困ることはなく、居心地よく過ごすことができました。
香港の医療制度で日本と大きく異なるのは、香港には大きく分けてPublic Hospital と Private Hospitalがある点です。
Public Hospital:一回受診料がHK$100で済み、入院費も1日あたり同額ほどだが、医療を受けるまでの待ち時間はとても長い。
Private Hospital:個人営業の病院であり、その医療費に国からの補助は出ないため、患者が払う医療費は莫大。だがすぐに診てもらえる。
といった違いがあります。実習した病院はPublicなのですが、例えば人工膝関節置換術では3年ほど待たないといけないと聞き、大変衝撃を受けました。
【実習について(上部消化管外科、整形外科)】
香港の公用語は広東語なので、患者に対して自分ひとりでは問診などはすることはできません。しかし外来や病棟では、学生や先生が患者の話を英訳して一緒に身体診察をさせてくれたり、「留学生がいるから英語でな」と回診やカンファを英語で行ってくださりと、非常に教育的に接していただけました。実習期間を通して、現地学生がいればそちらのディスカッションに参加したり、配属科の先生についたりと比較的自由に行動させていただけました。
上部消化管外科:ほとんどのオペで術野に入り、また比較的簡単な手技はやらせていただけ大変勉強になりました。疾患としては日本よりも胃がんの患者は少なく、食道がんが相対的に多い印象でした。ダビンチを用いたオペや、肥満患者に対して胃を意図的に切除するオペも行われていました。また、外科医が上部(食道~十二指腸)の内視鏡も行っており、EMRやESDなど日本では消化器内科の範囲の手技も見ることができました。内視鏡の技術に関しては日本のほうが進んでいるそうで、「よく日本にトレーニングしに行くよ」という先生が何人もいました。先生方はみな気さくで和気藹々としており、とてもよい雰囲気の科でした。現地学生からも評判がよいそうです。特に私のSupervisorだったProf. Teohは内視鏡室で日本の音楽をかけてくれたり、積極的に手技をやらせてくださりと、とてもフレンドリーに接していただきました。
整形外科:渡航前の希望では受け入れを拒否されていたのですが、「外科2ヵ月は長いし他の科も見たい」と直接現地で交渉したところ、なぜかあっさりと承諾されました。スポーツチーム2週間、外傷チーム2週間をローテートしてきました。スポーツチームの教授のProf. Yungは、スポーツドクターとして15年間従事してきたとても有名なスポーツ整形外科医で、教授の外来にはプロのアスリートが大勢やって来ていました。また、簡単な身体診察もやらせていただきました。外傷チームでは主にオペ室で過ごしていました。ここでもどの先生も親切に手術の解説をしてくださり、大変勉強になりました。
【香港での生活】
香港は物価が高く(特に地価)、感覚的に日本とあまり変わらないようでした。香港と聞くと100万ドルの夜景に代表されるように都会をイメージされるかもしれませんが、少し外れれば海や山もあり、ハイキングやカヤックなど、自然を楽しむこともできました。またアジアということでバドミントンも盛んで、留学中にいくつかの社会人サークルにお邪魔をしてきました。老若男女を問わず、たくさんの一般市民とも交流することができ、非常にいい思い出となりました。
【留学を終えて】
最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった粕谷先生、長谷川先生をはじめとする国際連携室の皆様、学務課の方々、先輩方、家族や香港中文大学の方々など、支えてくださった全ての方に心より感謝を申し上げます。そして2か月間寝食を共にしたルームメイトの篠田くん、本当にありがとうございました。
 Upper GIの教授と
Upper GIの教授と 現地の人とバドミントン
現地の人とバドミントン
University of Freiburg 留学体験記
伊藤 理樹(フライブルク大学)
私は2018/04/03-06/22までドイツのフライブルク大学に留学させて頂きました。フライブルクはドイツ南西部に位置し、シュバルツバルトに囲まれた自然豊かな街です。美しい旧市街を持ち、中世の雰囲気が色濃く残っています。ドイツ国内でも人気都市らしく、住居費はベルリンやミュンヘンといった大都市並みに高いと聞きました。治安も良く昼間は日本と変わらないくらいだったので実際とても暮らしやすく感じました。
実習に関してですが、4月は大学病院にて脳神経外科を4週間、5月はフライブルク市内の市中病院 (RKK Klinikum Loretto Krankenhaus) にて麻酔科を4週間、6月はまた大学病院に戻って神経放射線科を3週間回って実習を行いました。
最初の脳神経外科は、フライブルク大学病院の中の神経疾患センター (Neurozentrum) に入っており、脳外科専用のオペ室が6つあり、年間症例数は約3000件というヨーロッパでも有数の規模を誇る科であり、ドイツだけでなく、イタリア、スウェーデンなど様々な国から医師が学びに来ていました。実習はまず朝7時の朝カンファから始まり、その後はオペやICU管理の見学、そして時折先生がやって下さるレクチャーなどを受けていました。症例数が多いこともあり、脳腫瘍や脳血管内治療など、自分の興味のおもむくままに手術室に出入りしていました。カンファはすべてドイツ語だったので、理解できないことが多かったですが、後で先生方に英語で尋ねれば親切に教えてもらえました。お世話になったスウェーデンの先生には「言語の壁もあるし大変だろうけど、全部理解する必要はないから学生として何を学ぶべきか意識して取り組んでいってね」といった励ましの言葉もかけてもらえました。また、私の配属先のGeneral Neurosurgery とは違う Functional Neurosurgery という部門ではParkinson病に対する脳深部刺激療法 (DBS) などが行われており、所属は違ったのですが興味のある分野だったので、そちらも直接教授に交渉したところ快く見せて頂き、関連する論文なども交え丁寧に教えてくださいました。脳外科の先生は忙しく、向こうから世話を焼いてくれることはそこまで多くはなかったですが、自分から主体的に聞いていけば教えてくれるので、積極性が試される最初の実習となりました。
5月は前述のロレット病院という市中病院で麻酔科を回りました。ロレット病院はフライブルク大学関連の教育病院の内の1つらしく、現地の学生も結構訪れるということでした。キリスト教母体のレンガ建ての綺麗な病院で、大学病院よりもゆったりとしたアットホームな雰囲気でした。日本からの留学生は初めてらしくとても歓迎してもらえました。朝7時のカンファから始まり、そのあとは数件オペ室に入り上級医の先生につきっきりで、装置の使い方、投薬の仕方、心電図の読み方、身体所見の取り方などについて詳しく教えてもらいました。麻酔科の勉強は教科書だけでは全く頭に残らないのでマンツーマンで教えてもらえるのはとても貴重な機会となりました。また、市中病院ということもあり、先生の指導の下で気管挿管、用手マスク換気、ルート確保など手技も経験させていただくことが出来、実習が終わるころにはかなり慣れてきたので「とても上達したね!」といってもらうことが出来ました。空き時間は休憩室で温かいスープ(飲み放題)を飲みながら先生方やオペナースの方々と色々な話をしました。日本に以前留学されていた先生もいらっしゃり、休日にはビアガーデンに連れて行ってもらったりしました。この外病院では現地の学生との出会いもありました。ハノーファーやキールといったドイツの他の都市からも数人実習に来ており、実習後は近くのRock BarやMusic Festivalに出かけたりし、楽しい時間を過ごしました。
最後の3週間は再び大学に戻り、神経放射線科という日本にはない科を回りました。4月に回った脳神経外科と同じ神経疾患センター (Neurozentrum) に入った科であり、脳、脊髄の読影に加え、脳梗塞に対する血管内治療も行っている科ということで日本よりも細分化されている印象でした。朝のカンファ後、先生にいくつか症例を割り当てられ、自分で読影をし、所見をまとめプレゼンするなどして色々な症例を経験しました。脳卒中、アルツハイマーなど各種神経変性疾患などに加え、ヨーロッパということもあり、多発性硬化症 (MS) の患者さんが多かったのが印象的でした。読影に飽きたときはカテーテル治療の見学に入ったり、現地の学生に交じって脳卒中のレクチャーを受けたりと学び多き実習となりました。実は渡航前に6月の実習科は決まらずに現地入りしたのですが、脳外科の先生に相談したところ、この神経放射線科の存在を教えて頂きました。アポなしで直接教授室に交渉しに行ったのですが、即日でOKをもらえたので、この辺りも自分の行動次第かなと思います。
実習外の時間には、現地の学生とビアガーデンに行ったり、家に招いてもらいパーティーをやったりと充実した時間を過ごしました。また住んでいたのがシェアハウスということもあり、ドイツだけでなく様々な国の人と交流しました。5か国語を話せ、ヨーロッパ中を飛び回っているラトビア人エンジニアやNATOのスタッフとしてアフガニスタン勤務もしていたスロベニア人ナースなど、自分とそんなに年齢も変わらないのに、その視野の広さに驚かされました。まとまった休日があるときはドイツ国内や他のヨーロッパ諸国に旅行に出かけたりしました。スイスやフランスとの国境が近いこともあり、アクセスも良かったです。もともと西洋絵画や歴史に興味があったので、ヨーロッパ各地の観光地を巡り、とても贅沢な時間を過ごすことが出来ました。
振り返るとこの3か月は自分にとってとても貴重な経験になったと改めて感じます。現地の実習では事前の研修会などでの勉強が役に立ったと思うこともありましたが、語学力、知識共に自分の力不足を感じることの方が多かったです。これからの学びにぜひ生かしていきたいし、そういった刺激を得られたという意味でも大きな収穫がありました。
最後に、留学の準備から最中そして帰国後まで多大なサポートをしてくださった粕谷先生、長谷川先生をはじめとする国際連携室の先生方、学務の方々、フライブルクの先生方そして一緒に3か月過ごした大道君にこの場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
 フライブルク大学病院前で
フライブルク大学病院前で 外病院の先生方と
外病院の先生方と お世話になった神経放射線科の先生と
お世話になった神経放射線科の先生と 現地の学生と
現地の学生と
留学体験記
大道 卓也(フライブルク大学)
【留学を終えて】
私は、三か月間ドイツのフライブルク大学に留学させていただいた。名古屋大学に入学する前の高校2年の夏のオープンキャンパス時に聞いてから行きたいと感じていた留学に自分が参加できることになり、うれしかったのと同時に、身の引き締まる思いがしたのを覚えている。留学に行く動機は、ヨーロッパの医療を見たい、将来の自分のキャリアに向けての参考になればなど、なんとなくかっこいいとか漠然としたものだったが、留学を終えて、実際に肌で感じたことで、それ以上のものが得られ満足した留学となった。
【ローテ―ト科について】
私は、小児外科、麻酔科、放射線科をそれぞれ一か月ローテ―トさせていただいた。特にはじめの1か月間の小児外科はとても充実した日々の連続であった。月・水・金がオペ日、火・木が外来日であり、見ることができたオペは、鼠径ヘルニアや精巣固定術がほとんどであったが、腹壁破裂や胎便性イレウスなどの腸管の整復術が見られた。また外来日でよく見たのは鎖肛の診察であった。2年目の小児外科医になりたての若手医師がマンツーマンで教えて下さった。アメリカに18年住んでいたこともあり、英語で丁寧に教えてもらえたのがよかった。オペ日には、毎日手術に、3件清潔野に入れさせていただき、やらせてほしいといえば、実際に患者の閉創の際に最後縫わせてもらえたりもした。特に鼠径ヘルニアのオペは10回以上見たため、医師が4人しかいないため、バケーション休みの時は、戦力として数えられ、第一助手として手術に挑んだことも3回以上あった。縫合キットを自由時間の時には借りて積極的に練習ができたため、1回目の閉創の時よりよくなった!と言われた時には、自らの成長を感じるとともにチームの一員になれた時間があり素直にうれしかった。
【まとめ】
ドイツでの三か月間、様々な学生や医師の方とお会いした。そのなかでいろいろなことを学び、これからの医師としてのキャリアで指針となるようなことや糧になるようなことがたくさん得られた。その中でも特に、英語しか通じない環境で自分から言葉を発信して目の前のことを対処できるようになった精神力、異国の地でも信用を勝ち取れた、真摯に取り組む姿勢の二つはこの実習を通してでしか得ることのできない、これからのキャリアで精神的な支えとして私の自信となるものであった。最後に、このような貴重な経験を与えてくださった粕谷先生をはじめ、名古屋大学医学部国際交流室の皆様、受け入れてくださったフライブルク大学の皆様に心より感謝致します。
 小児外科の先生と
小児外科の先生と 放射線科の先生と
放射線科の先生と
アデレード大学留学体験記
丹生谷 究二郎(アデレード大学)
何をするために留学に行くのか。色々な人が色々な事を言っていて、僕は何だかわからないまま半ば勢いでオーストラリアに行くことを決めた気がする。先生には視野を広げるため、とありふれた事を言って、友人には日本での実習から逃げるためとうそぶいておいて、実際には視野を広げるということがどういう事かもよくわかっていなかったのだ。帰ってきて単純に思うのは、留学は大きく膨らんでしまった自我、自尊心を抑えるのには大変てきめんであったという事だ。とても恥ずかしいことを言うと、留学に行く前僕は自分をなんとなく「優秀」だと思っていた。実習中は、他の人と同じ勉強を他の人より早くやっていれば「優秀」という言葉でとりあえず褒められる。「pelvic inflammatory diseaseの既往がある患者が右上腹部痛を訴えている、何を疑うか?」「Fits Hugh Curtisです!」そういった何の意味があるかわからない問答で得た、空っぽな優秀という言葉に若干のむなしさを感じながら甘えていたのだと思う。もちろん海外でもこういった空虚な知識の応酬はある。最初のうちはそういったクイズバトルに参加してそれなりのプライドを満たしながらやりきれなさを感じていた。
僕はアデレードにあるWomen's and Children's Hospital(WCH)という小児病院での実習を行った後、WhyallaにあるBunyarraクリニックという3人の医師が勤める病院で実習を行った。WCHでの実習は日本でのポリクリに似ていて、手厚い指導と授業などを受けつつ、プレゼンテーションのやり方などを学ぶことができた。Bunyarraクリニックでの実習は放任と指導のバランスが素晴らしく、自分一人で患者の問診を行いながら病気に関して推論を立てた後、先生にプレゼンを行うというのが主な日課で、色々な患者さんとのコミュニケーションは、知識だけの勉強を続けていた僕にとって大変刺激的だった。その中で感じていたことは自分の実力のなさだ。うつ病の患者さんが泣いたとき、心筋梗塞疑いの患者さんが不安そうなとき、僕は何をすればいいか分からなかった。これ言っておけばいいだろうと思っていた"I'm sorry to hear that"は全く意味をなしていなかった。これは英語力の問題なのだろうか、患者さんと親身に話して心を開いていく先生を見て感じたのは英語力よりも人間力のようなものが自分にはまだ足りないという事だ。また傲慢にもそこそこはあると思っていた医学知識もほとんど診療に役立つものではなかった。ワイアラでの一か月は勉強不足と人間力不足を痛感させるには十分な長さだった。
そのように、ワイアラでの生活は僕に働くという事、人とかかわることの難しさ、重要さを僕に教えてくれた。またこれは逆説的に聞こえるかもしれないが、それと同時に知識の重要さも実感できたような気がする。例を挙げると、妊娠初期の患者さんが下痢を訴えていた時に担当医の先生がニューキノロンを処方しようとしていた、僕は下手な英語でそれは骨成長を抑制するから駄目だと思うと止めたのだが、それは不毛だと思っていた知識バトルで得たものだった。それまであまり意味がないと思っていた医学知識だが今までやってきたことにも少しは意味があったのかと感じることができた。
人に対する接し方はそれぞれによって変える必要があるが医学知識は確率的に多くの人に適応できるものが大半なので、ありていに言ってコスパがいいのだ。そんな単純なこともずっと一つの場所にいると見えにくくなってしまうのかもしれない。
留学が何かに似ていると感じていたのだが、それは大学に入った最初の一か月だ。僕は半ば実家が嫌になって名古屋で独り暮らしを始めたのだが、その後感じたのは実家の良さであり、親のありがたみであった。大変に月並みな感想ではあるのだけれど。それと同じように留学を通じて日本の教育の良さも少しわかった。実習中の講義は医師からの目線でみた医学、診療を教えてくれるし、なにより日本語なので分かりやすいし。長すぎる手術をずっと見る意味はよく分からなかったけれど。それ以外にも離れてみることでわかることはきっとあるし、大切じゃないと思っていたものが離れてみてから良く見えることや、その逆もある。留学を終えて、視野が広がるというのがどういう事かは結局よくわからないままだったけれど、もしかたら少し離れた所からみて良さも悪さも受け入れていくという事なのかもしれない。
最後になりましたが色々とご迷惑をおかけしました国際連携室の先生方、留学を色々な方向から支援してくださったフロンティア会、アデレード大学の先生方、本当にありがとうございました。
 ワークショップにて
ワークショップにて
留学体験記
森 将(アデレード大学)
私は3ヶ月間、オーストラリアのアデレード大学で実習を行いました。最初の2ヶ月はアデレードのWomen's and Children's Hospital、最後の1ヶ月はワイアラという田舎町のBunyarra Medical Clinicで実習をしました。アデレードはあまり大きい街ではありませんが、人と物が一点集中しているので、中心地は日を問わず絶えず賑わっています。その賑わいに目を向けると、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アボリジニなど多様な人種が入り混じっていることに驚かされます。その為、見た目がアジア人だからといって変に区別されることはなく、外国人でありながら快適に過ごすことが出来ました。また街には様々な国のレストランや店があるので(ダイソーもあります)、物価は少し高いですが食や生活用品に困ることはありませんでした。この多様性はアデレード大学医学部の学生にも見られます(写真参照)。例えば、私と一緒にアレルギー科を回った学生は、アイルランドで生まれフランスで数年暮らしてからオーストラリアへ来たという背景をもっていました。一緒に消化器内科を回った学生は、大学3年まではマレーシアの医学部で勉強していましたが、マレーシアは医者が余っていて卒後1年待たないと働き始めることが出来ないので、早く働く為に4年生からアデレード大学に編入して、将来はオーストラリアで働きたいとのことでした。このように多くの学生が様々な背景を持っているため、物の考え方が人によって大きく違いとても面白かったです。同様の理由で、英語のアクセントも人によって違うので、良い英語学習になったと思います。
アデレードでの実習内容は科や先生によって違い、積極的に患者さんに問診、診察を出来る時もあれば、先生の後ろについて見ているだけの時もありましたが、小児病院ということもあり珍しい遺伝病の患者さんを診ることが多く、貴重な体験が出来ました。その一方で炎症性腸疾患や川崎病などの日本と同様にコモンな疾患、セリアック病や囊胞性線維症などの日本では珍しいがオーストラリアではコモンな疾患を学ぶことも出来ました。ワイアラでの実習は、毎朝8:30の採血から始まり17:00までジェネラルに様々な患者さんを診ました。先生によっては、1日中1人で患者さんを問診診察しカルテに記載して先生にコンサルトをするということも出来ました。また、オーストラリアでは紫外線による皮膚病変が多く、先生の指導の下、液体窒素での凍結療法やメスでの切除・皮膚縫合などの手技を経験することも出来ました。最終週は現地医学生達と、精神・救急・麻酔・産婦人科のワークショップに参加しました。内容はかなり実践的で、精神科の模擬患者さんは突然部屋のエアコンを解体し、最後は激怒して(部屋だけでなく)建物から走って出ていくなど迫真の演技で驚きました。救急のシナリオは、専門医に電話でコンサルトして、その後応援に来た専門医の指示のもと患者さんの治療を行うという流れまで盛り込まれたかなり本格的なものでした。
異国で英語で病院実習というのは、想像以上に大変で困る事が沢山ありました。そんな時、いつも助けてくれたのが現地の医学生達でした。先生に何か言われて、分かったフリをして後から実はわからなかったと学生に聞く卑怯な私に、何度も笑いながら教えてくれました。実習だけでなく講義も受けたいしチュートリアルも参加したいという強欲な私の為に、一緒に先生にお願いをしてくれました。No extra students! と先生に何故か激怒された時は、皆で慰めてくれました。2ヶ月小児科実習をすることになったけど本当は産婦人科志望だからせめて婦人科外来だけでも見たいとぼやく私に、「何曜日の何時にここにいけば先生がいるから直接頼めば絶対大丈夫。事務に頼むと断られるから先生に直接ね。」と具体的な策略を教えてくれ、先生の連絡先までくれました。車がないと散歩しか出来ない田舎町ワイアラでは、車で買い物や観光に積極的に連れていってくれました。また、ワイアラではクリニックのスタッフの方々も、日本からはるばる田舎町に来たのに休日の予定が料理しか無い私達の為に、極寒の海で大量のイカと1時間泳ぐツアーの予約をして下さったり、とても気にかけて下さいました。以上の様に、何度も何度も何度も優しさに救われて3ヶ月を楽しく無事に乗り切ることが出来ました。今回の留学を通じて、過去の優しくなかった自分を反省し、今後は人にも野生動物にも優しくなろうと誓いました。同時に、周りからのサポートを最大限享受する為の人間関係構築や交渉術など様々なことを学ぶことも出来ました。
このような機会を与え、サポートしてくださった国際連携室や学務科の皆様に心から感謝しております。本当に有難うございました。英語圏で、優しく協力的な人々と可愛い動物に囲まれた穏やかな実習を送りたいという方にアデレード大学はおすすめです。
 「様々な国出身の現地学生たち」
「様々な国出身の現地学生たち」 「Whyallaでの家とクリニックの間の道。」
「Whyallaでの家とクリニックの間の道。」
西オーストラリア大学への派遣留学を終えて
内田 岬希(西オーストラリア大学)
西オーストラリア大学の本拠地であるパースで1ヶ月、西オーストラリア州最南端の街アルバニーで1ヶ月の実習を行いました。
パースでは、Sir Charles Gardner Hospitalにて膠原病内科と臨床免疫内科でそれぞれ2週間ずつ実習しました。手技が少なく入院患者の少ない科ということもあり、外来見学と身体診察が主な実習内容でした。名古屋大学にはどちらも系統だった診療科としてないこともあり、今まで教科書でしか見たことのなかった疾患について、患者さんの生の声、身体所見と共に学ぶことが出来ました。回診の際には、カルテの記載をする機会も幾度かありました。600床を超える大きな病院にも関わらずICUを除くほとんどの部門で紙カルテが使われており、手書きの文字を解読するのに苦しむことも多々ありましたが、システムの違いを楽しむことができました。また、臨床免疫内科では、研修医対象の勉強会に参加したり、アレルギーの抗原特定テストの補助、免疫蛍光染色された腎臓や皮膚の標本を見たり、と様々な角度から免疫にまつわる疾患について学ぶことができました。西オーストラリア州全土から患者の集まる病院であるため、症状の落ち着いている患者さんは400km離れた街からビデオ通話による遠隔診察を受けており、その様子を見ることが出来たことも印象に残っています。
アルバニーでは、地域医療の現場で学ぶ学生と共に、総合診療クリニック2カ所をそれぞれ1週ずつ、また地域中核病院での2週間の実習を行いました。この街は、南極海に面した西オーストラリア州最南端の街で、人口は37000人ほど。車を5分も走らせればエメラルドブルーの海、白い砂浜に着くとても素敵な街でした。総合診療と専門医との間の連携を知りたい、という希望を伝えていたため、本来は留学生の受け入れ期間外であるのにも関わらずこの希望を叶えられるプログラムを組んでいただきました。この街では西オーストラリア大学とノートルダム大学から合わせて10人の医学生が1年間実習をしています。先生方、学生ともに魅力に溢れており、忘れられない日々を過ごしました。
オーストラリアでは、総合診療 general practice が非常に発展しており、全ての患者さんがまずは総合診療のクリニックを受診します。受診理由は非常に多岐に渡り、血圧や糖尿病のコントロールから耳に入った異物、避妊用ピルや経口妊娠中絶薬の処方、皮膚ガンに対するスキンチェックや子宮頸がん健診まで、様々な理由で患者さんが訪れていました。また、高齢者に対するヘルス・アセスメントなどの様子も見学し、総合診療が地域で暮らすこと、予防医療を広めることにとても大きな意義を持っていると実感することが出来ました。簡単な問診や予防接種、子宮頸がんのスメア診、初期の皮膚ガンの切除など実際に自分が患者さんに関わる機会を多くいただきました。受診した患者さんの容態が悪く、救急車で中核病院の救急科へ搬送するといったこともあり、急性期の患者さんがどのように引き継がれるかを身を以て体感することもありました。地域中核病院では、総合内科チームに2週間お世話になりました。学生向けの教育プログラムがとても充実しており、週に2回教育回診という学生と先生が1対1で、問診や身体診察、検査結果の解釈、症例プレゼンテーションを練習する機会がありました。私もこれに数回参加し、ほかの学生の優れた姿に圧倒されながらも、先生の監督のもと問診や身体診察の練習が出来ました。これ以外にも、現地の学生が出来るだけいい実習ができるようにと、毎日特徴的な所見のある患者さんを探してくれ、問診・身体診察・プレゼンテーションの練習をしてくれました。また、緩和ケア専門の先生の外来を見学し、抗がん剤治療の継続の可否を決める現場に立ち会ったことも強く記憶に残りました。
アルバニーでは、自分のロールモデルとなる素敵な医師に出会い、「いつでも帰っておいで。私の病院で雇うから。」というとても嬉しい言葉をかけていただきました。先生方も学生も患者さんも、英語が第2言語であるということに理解があり、私が言葉に詰まっても誰一人嫌な顔せず、「ゆっくり考えて。君が話せること知ってるから」と温かい声をかけ待ってくれたのがとても心に残っています。
派遣留学提携の歴史が浅い大学であることに加え、今年度の派遣学生は私一人だけと、出発前は不安を感じることも多くありましたが、オーストラリアの人々の温厚な人柄、美しい大自然に支えられ、無事留学を終えることが出来ました。この派遣留学への挑戦は、6年間の大学生活で一番価値ある決心だったと心から思います。
充実した留学となるようご尽力いただいた、西オーストラリア、名古屋両大学の先生方に深く感謝いたします。
 地域医療実習を共に過ごした学生・先生と
地域医療実習を共に過ごした学生・先生と
留学体験記 Medical University of Vienna
髙田 秀人(ウィーン医科大学)
私は、オーストリアのウィーンにあるウィーン医科大学の附属病院Allgemeines Krankenhaus (AKH)で3か月実習をしてきました。AKHは1800床ほどあるヨーロッパ最大の病院で、科や医療関係者、設備が充実していることから西欧から東欧まで様々な国から患者さんがやってくるそうです。そこで、私は耳鼻咽喉科、移植外科、整形外科をそれぞれ一か月ずつ実習させて頂きました。
まず、耳鼻咽喉科で実習をしました。耳鼻咽喉科は日本の担当医制とは全く異なり、病棟担当や手術担当、外来担当とに分かれており、もちろん病棟担当の先生が手術をすることや、手術担当の先生が術前や術後に回診をすることもありますが、基本的にはカンファレンスや総回診で情報を共有する体制をとっています。私は、病棟担当の先生に担当して頂き、先生について病棟の管理を見学したり、現地の学生と診察や採血、症例について考察したりして過ごしていました。また、外来見学や手術の見学も自由にできましたが、外来ではドイツ語のため、手術はマイクロサージェリーが多いため、見学が難しく病棟がメインの実習だったように思います。
移植外科では、耳鼻科とは異なり、担当の先生はいなかった為、自分で何を学びたいか考え、行動しなければいけませんでした。AKHの移植外科は、腎移植を週に1,2回、肝移植を月に2回ほどの頻度で行っており、死体臓器移植が主流です。一般外科と病棟を共有しているため、一般外科の手術も自由に見学できました。毎朝のカンファレンスに参加し、その日の手術予定を把握した上で、自分が参加したい手術が始まる前に手術室で待機し、直接先生に参加してもいいか伺って参加しました。術野では第2助手としてカメラ持ちをする機会も多く、あまり慣れないカメラを持ちながら、先生がドイツ語で話す中、たまに聞こえてくる英語の指示を逃さないといった貴重な体験が出来ました。また、一緒にローテートしていた6年生がとても気さくだったので、手術がない時は入院のファーストタッチを手伝ったりして大変充実した実習ができたように思います。
整形外科では、名古屋大学と同じようにいくつかの班に分かれていました。私は膝・股関節班に配属され、週3回は手術を、週2回は外来の見学をしていました。手術では主に人工骨頭置換術の見学を行いました。とても気さくで賑やかな先生が多く、1か月を通して楽しく実習をすることが出来ました。
この実習を通して、医療知識や英語力が向上しただけでなく、様々な面で成長するきっかけとなりました。まず、言語の壁や受動的な姿勢では相手にされない環境でもやり遂げる自信や積極性を得ることが出来ました。また、現地の学生は、6年生で既にルートや採血、入院のファーストタッチを行うほど非常にレベルが高く、大きな刺激となりました。
こうした経験はこれからの研修医、医師になる上で必ず役立つものだと確信しています。
最後になりましたが、留学前の準備期間から留学中、帰国後まで多大なるサポートをして下さった、粕谷先生と長谷川先生をはじめとする国際連携室の先生方、AKHの先生方、フロンティア会のOB/OG の先生方、学務の方々、その他多大なるご支援を下さった様々な方に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
 耳鼻科でお世話になった先生と
耳鼻科でお世話になった先生と 外科の学生と送別会にて
外科の学生と送別会にて
留学体験記
島村 司(グダンスク医科大学)
私は Medical University of Gdańsk に宗宮君と2人で3ヶ月留学させて頂きました。元々英語があまり得意でなかった私にとって今回の留学はある種の挑戦でした。部活の先輩方が毎年どこかに留学されていたので大学初期より自分も留学したいと思っていました。私がポーランドの地を選んだ理由は、昨年度同じく Medical University of Gdańsk に行かれた先輩方が非常に楽しそうでかつ、英語での実習が充実していると感じたからです。毎年の先輩方の人間関係の積み重ねの助けもあり、最後まで良い留学生活が送れました。そんな留学生活を紹介したいと思います。
まず実習内容ですが、私は1~2週間毎に違う科を回らせて頂きました。具体的には新生児科、産婦人科、高血圧糖尿病科、血液内科、小児科、眼科、小児外科と多くの科を回らせて頂きました。実習形態としてはまず各科の講義があり、その後ベッドサイドでの実習を行いました。講義は日本と大差無い内容でしたが、疫学が大きく異なるため重点的に解説される疾患が日本と異なることが何回かありました。また、新生児科、産婦人科、小児科、小児外科で感じたのは日本の医療が想像以上に進歩していることです。日本では死亡率が1桁の疾患でもポーランドでは半数近く亡くなっていました。今まで滅多に死なない疾患と思っていたものが状況が変われば簡単に亡くなるものだという事実は驚くべきことでした。日本にいると麻痺してしまう有難みが実感できたことは今後の糧になるかと思います。
患者自身は英語が喋れない方が多いので先生に通訳してもらいながらの診察となりましたが、先生方の忙しい中多くの患者を診させていただきました。ポーランドでは問診が重要視されていて、よく先生側から何を聴取すれば良いか問われる事もしばしばありました。国がそこまで裕福では無いため出来るだけ安価に診断し、治療することを目指している印象を受けました。各薬剤の選択においても効果時間や副作用と並んで薬価が話題になっていました。この様な点で多くの日本の医療事情との差を感じられたことは大きな価値があったと思っております。各科の最後には試験があり、それに向けて勉強する日々だったので適度に刺激がありました。このようにやる気を維持したまま実習生活を送れたこともこの大学で良かったと思える点でした。
留学中の生活では出来るだけ現地の人になったつもりで生活する事を心掛けていました。出来るだけ自炊をし、また誘われたら断らず様々な事に参加してきました。先輩方が残してくださった生活用品のお陰で快適に三ヶ月生活する事が出来ました。この留学をさせてくださっているWozniak 教授や助教授のAdam には食事に連れて行って頂いたり、ポーランド語が必要な場面で助けて頂いたりとお世話になりました。Wozniak 教授主催の緑茶の効能についてのプレゼン発表をさせて頂いたり、先生のお宅で伝統料理を振舞って頂きました。
その他、多くの現地学生に遊びや飲みに誘ってもらい、毎日充実した生活を送らせて頂きました。また現地のバドミントン団体に連絡して毎週練習に混ぜて頂きました。言語の壁は厚かったですが、英語を話せる方とは一緒にご飯や飲みに行く機会もあり積極的に参加して良かったなと思っております。週末や連休では他の国に旅行へ行きましたが、その中でも現地の方々や他の旅行者の方々と交流ができ、非常に楽しいものとなりました。
英語が少し話せるだけでこんなに世界が広がるものかと驚くと共に大事な情報は殆ど英語でしか手に入らないという事を痛感した留学となりました。ここには書ききれない程様々な経験を3ヶ月の間にする事ができ、本当に行って良かったと思っております。最後になりますが、国際連携室をはじめ、この留学を支えて下さった方々、本当にありがとうございました。
留学体験記
宗宮 大輝(グダンスク医科大学)
私は2018年3月から約3か月間、ポーランドにありますグダニスク医科大学に留学させていただきました、宗宮大輝です。こうして振り返ってみると本当に充実した数か月間であったと改めて感じています。今回の留学を踏まえ、グダニスク医科大学での実習についてや留学を通して感じたことなどを記させていただきます。
〈グダニスク医科大学について〉
ポーランドの公用語は当然ポーランド語なわけですが、このグダニスク医科大学にはPolish Division と English Division という2つのコースが存在しています。前者は名前の通りポーランドの学生向けであり、対して後者は様々な国からの留学生を対象に英語で医学教育を行っています。English Division の学生はスウェーデン、サウジアラビア、イギリス、アメリカ、インド、スペイン、イタリア、イラク、スリランカなど非常に多岐にわたります。他の留学先と比較して、これほどたくさんの国々の学生と関わることができるのはグダニスク医科大学の大きな強みであると感じています。実際、イタリアやサウジアラビア、スウェーデン、ポーランドの学生たちと自国の医療、宗教や習慣などについて語り合うという非常に貴重な経験もできました。
(実習について)
私は、English Divisionの学生たちと共に1~3週間の長さで糖尿病・高血圧科、循環器内科、心臓外科、アレルギー科、呼吸器内科、小児科、産婦人科をローテートしました。一日の流れとしては基本的にはまず午前中に講義があり、その後病棟や外来に移動して実習を行うというものでした。患者は基本的にはポーランド語しか話せないので問診や身体診察を自分たちだけで行うのは難しいのですが、どこの科でも担当の先生がこちらの質問や患者の話したことを翻訳してくださりました。また、さまざまな科をローテートしたので多くの医学英語を覚えなければなりませんでしたが、それぞれの科で講義があったおかげでそれらを通して少しずつ英単語も覚えることができました。さらに、どの科においても実習の最終日に筆記試験や口頭試問がありこれらの試験に合格しなければならなかったのでそれに向けて対策をするため非常に良い勉強になりました。特に、循環器内科の試験は "ECGs by Example" という教材の100個以上の心電図の中から2つが出題されるというもので、この試験のおかげでいぜんよりもかなり心電図が読めるようになったと思います。
実習中に強く印象に残ったことの一つとして女性医師の多さがあります。実習させていただいたどの科においても約半数を女性が占めており日本との大きな差に驚きました。ポーランドでは出産休暇や育児休暇などが充実しており、これにより女性が働きやすい環境が整っているのだと感じるとともに、日本もポーランドから学ばなければならないと思いました。
(グダニスクでの生活)
・気候
3月上旬に到着したころは最低気温が-5℃くらいで、暖かくなり始めた名古屋から来たこともありとても寒く感じました。しかし、私が到着する1週間前には-15℃くらいだったと言われ衝撃を受けました。3月中は寒さの厳しいグダニスクですが、4月になると10℃を超え、暖かく過ごしやすい気候になってきます。到着したばかりのときは茶色で殺風景だった景色が4月・5月になるにつれだんだんと緑に色づいていき、まるで違う場所かのように大きく変化します。
・治安・物価
非常に治安が良く、夜中に出歩いていても全くトラブルに巻き込まれることはありませんでした。そしてヨーロッパの中でも非常に物価が安い(日本の2分の1から3分の1)ため生活費を抑えたい私にとっては非常にありがたかったです。
・現地の学生との交流
他の留学生に混ざって実習を行うためたくさんの学生と関わることができます。また普段生活する寮も留学生やポーランドの学生が住んでいるので彼らと関わる機会もたくさんありました。一番の思い出としては、各々が自分の国の食事を作って持ち寄るインターナショナルパーティーです。日本から持ってきたラーメンを作ってみんなに喜んで食べてもらえたのは良い思い出です。これ以外にもさまざまな飲み会が開催されているのですぐにたくさんの友人ができます。
〈課外活動〉
この留学で今しかできないことをやりたいと思い、Wozniak教授に紹介していただいたダンス教室に毎週月曜日と水曜日に通い、ポーランドの伝統舞踊を習いました。ダンス教室のメンバーのほとんどはポーランド語しか話せないのですが、身振り手振りでなんとか教えようとしてくれて、急に日本から来た学生に優しく接してくれて非常に嬉しく感じました。彼らの丁寧な指導と練習の甲斐あってKrakowiakという伝統舞踊を少しながら踊れるようになり、人生でまたとない非常に良い経験となりました。
また、同じ場所で歌のレッスンもやっておりポーランド国歌も学ぶことができました。
〈留学を終えて〉
この3か月間は間違いなく、今までの人生の中で最も充実した時間でした。実習、普段の生活、課外活動などすべてにおいて刺激のある毎日でした。そして今回の留学を通して最も強く感じたことは、現地の学生のレベルの高さです。この大学のEnglish Divisionでは臨床実習が始まる4年生になるまでに難易度の高いテストをいくつも通らないといけないようで、その影響もあって4年生であっても非常に知識豊富であると感じました。また彼らはみなとても向上心が強く、世界中の国から優秀な生徒が集まっているのだということを強く感じるとともに、日本人として自分も彼らに負けないように頑張らなければいけないと思うことができ、非常に良い刺激になりました。この3か月間で学んだことはこれからの人生においてかけがえのないものとなりました。
〈最後に〉
留学前の準備期間から帰国後まで長きにわたり多大なサポートをしてくださった、国際連携室の先生方、Frontier会のOB、OGの先生方、学務の皆様、Gdansk大学の先生方、一緒に3か月間の留学を乗り切った島村君、その他多大なるご支援を下さった様々な方には本当に感謝しています。ありがとうございました。
 実習班のメンバーと
実習班のメンバーと インターナショナルパーティ
インターナショナルパーティ
留学体験記
福田 ミルザト(ルンド大学、ダルハウジー大学)
私はまず2か月スウェーデンのルンド大学にいきました。最初の月は外科をローテし、おもに膵臓癌と食道癌の症例を見ていきました。オペ中にティータイムがあったりと日本と違うところがあっておもしろかったです。病院を集約化して医師のマンパワーを確保して、ワークライフバランスを両立しているところも印象的でした。実際外科にもかかわらず半分ほどが女医さんでした。
2か月目は小児科をローテしました。出生児の標準体重が3500gであったり日本との体格の差を感じました。実習は外来や回診を回るだけというのが多かったですが、小児科循環器の先生がとっても熱心に教えてくれて、その分野にはかなり強くなれました。スウェーデンの実習の感想としては手技的なことは日本のほうが学べることが多いかもしれません。しかし、ルンドはいろんな国からたくさんの留学生がくる街です。さまざまな国の文化、考えに触れることができ、見識が広まるという面ではルンドに勝るところはないでしょう。事実、スウェーデンで高まったモチベーションをもとに今でも日本で頑張ることができています。
ルンドの後はカナダのダルハウジー大学にいきました。この大学は協定校ではないのですが、英語圏の大学にもいってみたいとの思いから必死に探しアプライしました。カナダでも外科をローテしました。こちらでは学生に手技を学ばせようとする雰囲気があり、私はほとんどのオペに第1助手として参加し、縫合などの手技をたくさん学べました。またネイティブの英語についていくのに必死になる中で英語力もかなり上達したように思えます。またカナダはとても自然豊かな国です。普段自然にあまり感動しない自分でさせ感動するほどの観光地がたくさんありましたので、是非みんなにもこの感動を共有してほしいです。
最後に、留学を考える際まわりからいろいろとデメリットなどを言われることが多いかと思います。しかし留学にいった同級生、先輩はみな口を揃えて行って良かったと言っている人がほとんどです。私も自信を持ってとても有意義な経験だったと言えます。留学に行きたいと思った方々はまわりの雑音を気にせずぜひ行って欲しいなと思います。
ルンド大学 留学体験記
丸山 昭洋(ルンド大学)
私は、4月・5月の2ヶ月間をルンド大学でICUと内科の実習を行ってきました。留学先が決まる前からなんとなく提携校の内でルンド大学になるだろうと思っていたので、名古屋大学に来るルンド大学の学生と仲良くなっておきました。スウェーデンにはフィカというコーヒーブレイクの文化があり、とても重要視されています。どちらの科でも30分くらい昼食の時間とは別にそういう時間がありました。
ICU
医者の数は多くて覚えていませんが、ベッドは8床でした。ICUでの基本的な1日を紹介します。朝7時半からカンファレンスがあります。そこで昨日夜に起こったこと、新しい患者について情報を共有します。その後、回診があり、個々の患者の状態を確認します。そこで毎回、2人の患者を割り当てられました。回診が終わり次第、カルテで情報を細かくインプットします。ここで大変だったのは、カルテはスウェーデン語だったので、指導医に翻訳してもらわなくてはいけなかったことです。そして、11時半から小さめのカンファレンスがあり、担当患者について発表しフィードバックをしてもらいます。午後は救急外来を見学したり、現地の学生と議論したりしながら時間が過ぎていき、16時のカンファレンスで夜勤チームに引き継いで終わりです。カンファレンスは私のために英語で行なってくれました。和気藹々とした雰囲気でとても楽しかったです。
内科
ルンドから電車で1時間かかるイースタッドという町に病院がありました。毎日朝8時から、カンファレンスがありましたが、全部スウェーデン語で意味がわかりませんでした。その後、現地の学生と共に外来患者の予診をとり、身体診察し、カルテ記述をしていました。また、病棟回診を指導医と学生とともに行い、その都度色々と教えくれました。だいたい15時か16時に実習は終わりました。電車はちょいちょい遅れるので電車通学は少し大変でした。
寮生活
全員で28人の寮で、キッチン、トイレ、シャワーは共同で使う形式でした。寮は世界各地からルンド大学に各分野で留学に来ている大学生・大学院生が集まる寮でした。様々なバックグラウンドをもつ人々との交流はすごく楽しかったです。困った時にはお互いに助け合えるので良かったです。
余暇
平日は基本的に実習が終わればテニスをしていました。日照時間が長く、無料のテニスコートが多かったので大変良かったです。日本で友達を巡って、スウェーデン国内をめぐる旅をしました。留学に行った期間がちょうどお祭りシーズンだったので、休日はお祭りにも参加しました。もちろん、その他のヨーロッパ諸国へも旅行に行きました。
最後になりましたが、派遣留学を支援してくださった粕谷先生、長谷川先生をはじめとする皆様に感謝の意を申し上げます。
 名古屋大学に来ていたエリック家で飲み。
名古屋大学に来ていたエリック家で飲み。 エリックのみpart2
エリックのみpart2 寮のウェルカムパーティー
寮のウェルカムパーティー  スウェーデンの伝統お菓子セムラ
スウェーデンの伝統お菓子セムラ
上海交通大学医学院への派遣留学
服部 展幸(上海医科大学)
私は今年度の派遣留学において上海交大学で約二ヶ月の実習を行いました。
まず瑞金医院の中国伝統医学科において二週間の実習をさせてただきました。いわゆる中医学(TCM: Traditional Chinese Medicine)は日本でも漢方や鍼灸が広く用いられています。しかし、実際のところ中医学の基本的な考え方や本場中国での扱いを知る人はあまり多くはないと私は考えます。私はそのギャップを今回の留学で埋めるべく、この科を選択いたしました。中医学科の医師の方々は丁寧にその考え方や中医学的な診断・治療を説明してくださいました。さらに、現地の学生には市中病院にも案内していただき実際の鍼灸治療に参加いたしました。
次に仁済医院東院の腎臓内科での実習に参加いたしました。ここでは学生に混じってレクチャーを受け、PDやHDのオペの見学の機会がありました。透析室は非常に巨大、60台はあろうという透析装置が同時に稼動する様は圧倒的で、中国という国の規模を感じました。
最後に、引き続き仁済医院の消化器内科での実習をいたしました。この病院の消化器内科は中国でも指折りの、権威有る科であるとのことでした。おおまかに、「消化管疾患」、「肝炎」と「内視鏡」の3チームに分かれており、私はそれらを一週間ずつローテートさせていただきました。各チームでそれぞれ多くのことを学びましたが、私が非常に感銘を受けたのは内視鏡検査のテンポの速さです。医師の方々は日本では考えられない異常な速度で内視鏡検査をこなしていました。午前中だけで一部屋で40人近くもの患者さんをこなしていたことは今でも信じ難いです。
以上は実習についての感想を述べさせていただきましたが、週末や実習後の生活も非常に充実したものであったと思います。交通大学の学生にはいろいろな場所を案内してもらい、親睦を深めることができました。また、他国から同じように留学していた学生とは境遇が似ていたこともあり、非常に懇意にさせていただきました。時に宗教的・政治的な議論を共有することは、私の価値観を広げるものであったと感じています。上海という都市は現在バブルにあり、経済状況が街を歩く人々からも窺い知れました。また、日本とは異なる国家政策が国民の生活や町並みにも影響を与える様を肌で感じることができました。他にも上海だけでなく多くの都市や山に旅行に出かけました。
総じて、非常に実りの有る留学をさせていただいたと感じています。国家的な政策の違いにより、医療のレベルや高度医療を提供できる病院はまだまだ不足しているというのは現実であると思います。しかし、先に挙げた中医学の経験や中国独特の医療感覚は今後の医師としての人生に幅を持たせてくれると確信しています。また、慣れない中国での生活、社会主義の現実、他の留学生や現地の学生との交流は私にとって刺激になりましたし、自身を見つめなおす良いきっかけともなりました。実際には危険なことにも多く遭遇しましたが、それらすらも良い経験になりました。非常に感謝しています。
 キャンパスの様子
キャンパスの様子