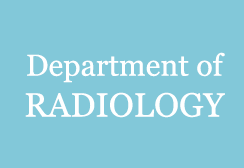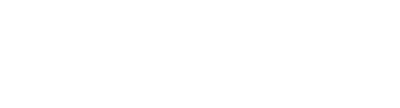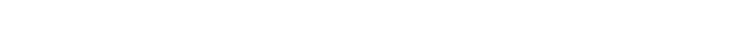ご挨拶
名古屋大学医学部放射線医学教室について

名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻高次医用科学講座量子医学分野担当の長縄慎二(ながなわしんじ)です。旧称は名古屋大学医学部放射線医学講座です。
通称では、名古屋大学医学部放射線医学教室と言うことも多いです。当教室は、
大学院の量子医学分野、量子介入治療医学分野、放射線治療学分野と、附属病院の
放射線科、放射線部から構成されています。機構上は複雑で、それぞれ所属の教員、医員がいますが、実際は仲良く一つの教室として診療、研究、教育を行っています。
このたびは、当教室のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当教室の沿革
当教室は、1954年6月16日開講で、初代教授は、X線CTの基本となった回転横断撮影法の開発やX線拡大撮影、原体照射法などの開発で有名な高橋信次先生です。高橋先生は文化勲章を受けられています。ノーベル賞候補と言われつつも、残念ながら受賞の前にお亡くなりになりました。
2代目教授は高橋先生の研究の臨床応用を行い、その後、MR, PET, PACSなどの研究で成果をあげ、病院長や
医学部長を務められた佐久間貞行先生です。
3代目教授は医療情報のデジタル化やモニター診断などで有名な石垣武男先生です。石垣先生は日本医学放射線学会学術集会会長や日本ラジオロジー協会の理事長も務められました。2006年7月1日より、私が4代目主任教授を担当しています。
何事も楽しくなければ、上達しません。初期研修、専攻医としての研修中には、もちろん皆で丁寧に指導しますが、自分で物事を考えられるように誘導しなければ、本当の仕事の楽しさはわかるようにはなりません。
教育においてはそこが重要と思っています。
なにより、仕事は楽しく行うというのが私のモットーで、教室員にも浸透しています。Enjoy Radiology! が
当教室の基本ポリシーです。
当教室の特徴としては関連施設の豊富さです。多数の大学、研究所、大病院が関連施設で活発に人事交流を
行っています。全国から優秀な人材も続々と集まってきています。キャリアパスは量も種類も豊富です。
海外とのコネクションも多くあり、希望に応じで留学もできます。現在、日独放射線医学交流計画の代表を私が務めてもいます。
診療、研究内容
本教室は高橋先生や佐久間先生の時代は新規技術の開発が研究の主体でしたが、最近は、診療に重点をおいて
いますので、臨床的な研究を幅広く行っています。最近のテーマとしては、脳や感覚器の老廃物排泄機構
(glymphatic systemなどの間質液動態)の解明(世界をリードしています)、高磁場MRIの臨床応用(特に、腹部4D-flow, 内耳内リンパ水腫、乳腺など)、高精度放射線治療(特に頭頸部腫瘍、食道腫瘍、前立腺がん、子宮腫瘍、不整脈など)、先端CT画像と病理の対比(特に、胆膵、肺、大腸など)、新規IVR技術の開発と応用、異種モダリティ画像の融合による治療への応用、人工知能(AIを含めた)コンピューター診断支援法開発やRadiomics、医療におけるITソリューションの開発、新規核医学診断法開発と評価などです。対象臓器は脳、頭頚部、甲状腺、胸部、腹部、骨盤などほぼ全身にわたる臨床、研究を行っています。研究の方向性としては、被曝低減、低浸襲の追求(低侵襲診断、低侵襲治療をめざしており、まさに現代医療のベクトルと完全に合致しています)が第一です。第二に単に新しい技術の評価のみでなく、画像から疾患の本態へせまる世界で唯一の
オリジナルな仕事をめざしています。つまり従来、観察不能であったものを可視化することや各科との協力に基づく臨床研究に重きをおいています。私のライフワークであった、メニエール病の内リンパ水腫の可視化も2007
年に名大耳鼻科の前 中島務教授との共同研究により世界ではじめて達成出来ました。また第三に機器メーカーと共同での新技術開発も行っています。これは自国民のための医療機器を作っていないような国は先進国とは
言えないので、日本が先進国であり続けるために努力し、海外の流行を後追いするようなことは極力しないように心がけています。
まとめ
最近は、放射線科は入局先として、学生や初期研修医、他科の専攻医からのコンバート組の間で人気も急上昇してきていますが、まだまだ放射線科医は日本では不足しています。どこの病院でも引く手あまたです。
これから、次世代を担う皆さんと共に、日本の医学、医療の発展のために、力を発揮していきたいと思います。放射線科の領域は拡大が続いており、若い方が国内外で臨床でも研究でも活躍できる機会にものすごく恵まれています。ぜひ一緒に、放射線医学を楽しみながら未来を創っていきましょう。現在、当教室は優秀な指導者、
臨床医、研究者に多数恵まれた国内でも有数の放射線医学教室になっていると自負しております。
大まかな目標を示すとしても、自主性を尊重しつつ、若い人の進む方向の微調整をするのが私の役割と思っています。なにより、若い時点で成功体験を積ませることがなによりの指導と考えています。
また組織として、構成員の多様性を最大化することも、組織が変化し、さらに成長するために必須であるとも
考えています。
長縄慎二