専門としている病気の種類
大腸外科
大腸がんについて
大腸がんは食生活の欧米化とともに増加傾向にあり、2003年の統計データでは、がんによる死亡者の中で男性では肺がん、胃がん、肝臓がんに次いで第4位、女性では胃がんを抜き第1位となっています。また2020年には大腸がん罹患率(病気にかかる率)においても、男性で肺がんに次いで第2位、女性では乳がんを抑えて第1位となると予測されています。
大腸の解剖
大腸は図に示すように、結腸(盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸S状部)と直腸(上部直腸・下部直腸)の2つに大別できます(図1)。結腸の解剖は比較的単純で、治療に際しても大きな問題になることは少ないです。一方、直腸は狭い骨盤内に位置し、男性では膀胱・前立腺・精嚢など、女性では子宮・膣などの臓器に取り囲まれています(図2)。また直腸の周囲には骨盤神経叢と呼ばれる大切な神経の束が存在し、これが排尿機能や男性の性機能をつかさどっています。こうした狭い空間で、重要な隣接臓器や神経を可能限り温存しつつ行う直腸がんの手術は難度が高く、結腸がんと比較して再発率が高く、生存率も低いのが現状です。
大腸がんとは
大腸がんの多くはポリープが悪性化したものと考えられています。大きさが1cmを越えるようなポリープは、近い将来にがん化する可能性が高く、この段階で治療することをお奨めします。最近、大腸がんの一部はポリープからではなく、正常な大腸粘膜から発生することが分かってきました。このようながんは‘デノボがん’と呼ばれますが、詳細な頻度などはまだ明らかになっていません。
大腸がんは進行するとともに大腸壁深くに浸潤していきます。がん浸潤の深さ(深達度)により大きくSMまでの早期がんとMP以深の進行がんに分けることができます(図3)。
また他臓器のがんと同様に、大腸がんでも病期(ステージ)が決められています。これは深達度とリンパ節への転移の程度、遠隔転移(肝臓、肺、腹膜など他臓器への転移)の有無によって決められます(図4)。このステージの違いでがんの治る確率は随分と変わってきます(図5)。
大腸がんの症状
早期がんで症状がでることはほとんどありません。多くは便潜血検査陽性や腹部愁訴などのため精密検査を行い発見されます。
進行がんでは様々な症状を認めます。上行結腸などの右側の結腸では腹痛が最も多く、次いで腫瘤触知・腹部膨満感・貧血などが多いです。右側結腸では便が液状~泥状で管腔も広いため腫瘍がかなり大きくならないと腸閉塞症状は起こりません。このため発見が遅れ、進行がんで発見されることが多いのです。S状結腸など左側結腸では血便が最も多く、次いで腹痛・便秘などで、直腸になると血便、便通異常(便秘・頻便・便柱狭小化)などの頻度が増えてきます。
大腸がんの診断
- 大腸内視鏡検査
内視鏡検査は病変の存在診断に欠かせない重要な検査の1つで、病変の型や大きさを観察すると同時に、生検(病変の一部を採取する)を行い‘がん’の確定診断をつけます(図6)。 - 注腸検査
大腸全体の走行、がんによる狭窄・圧排像などの情報が得られます。がんの正確な場所がわかる検査です(図7)。 - CT
がんの拡がりを見るための重要な検査です。特に進行がんではがんの局在・周囲臓器への浸潤、リンパ節転移、肝・肺などの他臓器転移の有無が診断可能です(図8)。 - MRI
直腸がん症例では骨盤部のMRIが有用です。特にリンパ節転移、周囲臓器への浸潤(男性では前立腺・精嚢・膀胱など、女性では子宮・膣など)の診断能はCTより優れています。また肝転移を認める症例における肝臓のMRIも有用です。 - 腫瘍マーカー
大腸がんではCEA、CA19-9が一般的に使用されています。早期がんの発見には不向きです。高値の場合は遠隔転移のある可能性が高くなります。
大腸がんの治療法
大腸がんの治療法は主に手術療法・化学療法(抗がん剤)・放射線療法の3種類です。しかし化学療法や放射線療法のみでの治療効果は不十分であり、手術療法の補助的療法と考えられています。治療は原則として‘がん’の切除を行います。
手術の方法は一部の早期がんに対する内視鏡的切除と早期がん、進行がんに対する外科的切除の2つに大きく分かれます。外科的切除は通常の開腹手術と腹腔鏡下手術について、また解剖学的な相違から結腸がんと直腸がんについて別々に述べます。
1.内視鏡的切除
適応病変は粘膜内がん(Mがん)または粘膜下層にわずかに浸潤するがん(SM浅層がん)です。内視鏡的に切除した標本を顕微鏡で確認し、切除断端にがん細胞を認め取り残しがあると判断される場合、がんが粘膜下層へ高度に浸潤する場合(SM深層がん)、静脈・リンパ管へのがんの浸潤を認める場合、がんの分化度の低い場合(低分化腺がん)ではリンパ節郭清を含む外科的追加切除が必要となり、腹腔鏡下手術が選択される場合が多いです。
2.開腹手術
- 結腸がん手術
がんの存在部位、リンパ節転移などの進行度に応じて、腸管の切除範囲・リンパ節の切除範囲が決められます。右側結腸がんに対しては回盲部切除術・結腸右半切除術、横行結腸がんに対しては横行結腸切除術、下行結腸がんに対しては結腸左半切除術、S状結腸がんに対してはS状結腸切除術がおもに施行されます。リンパ節は‘がん’の部位に応じて1群から3群に分けられており、通常早期がんでは1-2群までの切除を、進行がんでは3群までの切除を行います。結腸切除は基本的な手術で、手術時間も短く、術後の機能障害もほとんど認めません。術後は9-12日で退院可能です。 - 直腸がん手術
前述のように直腸は非常に狭い骨盤腔内に存在します。このため‘がん’が肛門に近いほど手術の難易度も高くなり、手術時間もかかります。手術は肛門機能を温存する前方切除術(図9)または永久的な人工肛門が必要となる腹会陰式直腸切断術(マイルズ手術)(図10)が行われます。最近では肛門縁により近いがんに対して超低位前方切除術が行われるようになっており、永久的な人工肛門が必要となる腹会陰式直腸切断術の症例は減少しています。肛門挙筋・肛門括約筋への浸潤がない症例であれば、肛門管にかかる程度のがんまで自然肛門を温存することが可能で、肛門側から腸と肛門管を縫うこともあります(経肛門吻合)(図11)。しかし超低位での吻合は縫合不全の危険が高いので、吻合部の安静を保つために一時的な人工肛門造設が安全です。当科では回腸末端から約40cm口側で回腸瘻を造設し、3-4ヵ月後に閉鎖手術を行うこととしています。
膀胱・前立腺・精嚢などの周囲組織へ浸潤を認める進行がんでは尿路変更を伴う骨盤内臓全摘術が選択されることがあります。この場合、左側腹部にS状結腸による永久人工肛門、右側腹部に尿路変更(回腸導管)による人口膀胱と2個の腸瘻が必要となります(図12)。
直腸がんの場合、人工肛門の問題以外に性機能障害・排尿障害も大きな問題となります。性機能障害は女性については明らかにされていませんが、男性の場合は射精障害と勃起障害があります。また排尿障害とは尿意を感じられない、残尿があるなどの症状で、神経因性膀胱と呼ばれています。これらは直腸の周囲を取り巻く骨盤神経叢などの自立神経を切除するためによって起こりえます
今日ではこれら自律神経温存手術が標準術式となっていますが、がんが神経に浸潤あるいは近接する時にはやむなく合併切除を行います。また前述の様に直腸は狭い骨盤内に存在するため、手術の技術的難易度は結腸がんに対するより高く、手術操作に伴う損傷も起こり得ます。術者の技量に依存するところも大きく、直腸がんの手術は専門施設で行うことが望ましいです。
1990年代前半に始まり、現在では内視鏡的切除適応外の早期結腸がんに対しては標準的治療となっています(図13)。開腹手術と比較し、腹腔鏡手術の利点は手術侵襲が小さいこととされています。創が小さいため術後疼痛が少なく、早期の離床が可能です。また腸蠕動の回復も早く、退院は術後7-10日目で可能です。欠点は手術時間がやや長くなることです。
術後補助化学療法(術後抗がん剤治療)
ステージIIIの患者さんでは標準治療となっています。当科ではUFT(ユーエフティー)を中心とした5-FU(ファイブエフユー)系の内服薬を中心に、半年~1年の術後補助療法を行っています。
術後の経過観察
5年生存率というように再発する人の多くは5年以内に再発します。したがって最低5年間の病院通院が必要です。この間、年に1-3回程度のCT検査などを行い再発の有無をチェックします。しかし経過観察中の検査は主に再発の発見を目的とされており、他の病気の早期発見には不向きでということを忘れないで下さい。一般の定期健診などはしっかりと受けることをお薦めします。
転移・再発大腸がんの治療
大腸がんの転移先は肝臓が最も多く、直腸がんでは肺転移・局所再発も多くなります(図14)。転移・再発がんに対する外科治療は時に非常に侵襲が大きく困難を伴う場合もありますが、治癒が期待できる唯一の治療法と考えられています。放射線治療や抗がん剤の発達により延命も期待できるようになりましたが、いまだ治癒を得るのは困難な状況です。
最後に
大腸がんは早期発見と適切な治療を行えば、治癒する可能性が非常に高い病気です。まず検診を行いましょう。便潜血陽性や腹部症状がある方は是非、注腸検査もしくは大腸内視鏡検査を受けてください。直腸がんや再発がんの治療方針は施設により異なることも多く、専門施設での専門医による治療をお薦めします。

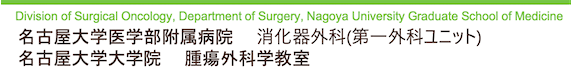
 胆道外科
胆道外科