 人間の体温は約37度に保たれていますが、これより高すぎても低すぎても体の機能に支障を来し、生命が維持できなくなります。そこで、暑い環境では汗をかいて体温の上昇を防ぎ、寒い環境では筋肉を震わせて熱を作ることで体温の低下を防ぎます。このような体温を一定に保つ反応のコントローラー(神経回路)は脳の中にあり、私達はその仕組みを研究しています。そして、体温を「37度」に設定する脳の仕組みを解き明かしたいと考えています。
人間の体温は約37度に保たれていますが、これより高すぎても低すぎても体の機能に支障を来し、生命が維持できなくなります。そこで、暑い環境では汗をかいて体温の上昇を防ぎ、寒い環境では筋肉を震わせて熱を作ることで体温の低下を防ぎます。このような体温を一定に保つ反応のコントローラー(神経回路)は脳の中にあり、私達はその仕組みを研究しています。そして、体温を「37度」に設定する脳の仕組みを解き明かしたいと考えています。名古屋大学医学部・中村研究室の研究内容(研究室についてはウェブサイトを御覧下さい。)
私達は、体温調節など、生命を保つ脳機能の仕組みの本質を解き明かすべく研究を行っています。
体温の調節について
 人間の体温は約37度に保たれていますが、これより高すぎても低すぎても体の機能に支障を来し、生命が維持できなくなります。そこで、暑い環境では汗をかいて体温の上昇を防ぎ、寒い環境では筋肉を震わせて熱を作ることで体温の低下を防ぎます。このような体温を一定に保つ反応のコントローラー(神経回路)は脳の中にあり、私達はその仕組みを研究しています。そして、体温を「37度」に設定する脳の仕組みを解き明かしたいと考えています。
人間の体温は約37度に保たれていますが、これより高すぎても低すぎても体の機能に支障を来し、生命が維持できなくなります。そこで、暑い環境では汗をかいて体温の上昇を防ぎ、寒い環境では筋肉を震わせて熱を作ることで体温の低下を防ぎます。このような体温を一定に保つ反応のコントローラー(神経回路)は脳の中にあり、私達はその仕組みを研究しています。そして、体温を「37度」に設定する脳の仕組みを解き明かしたいと考えています。
感染性発熱について
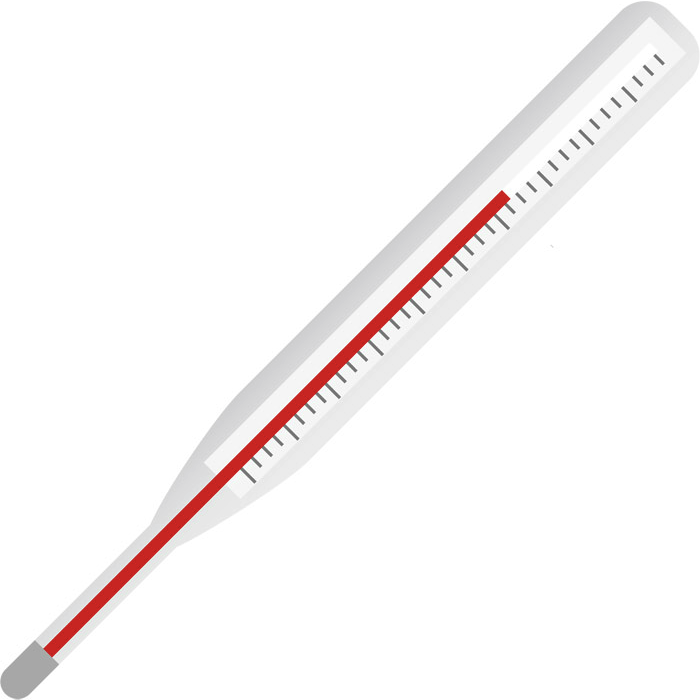 風邪やインフルエンザのような感染症にかかると発熱が起こります。これは、体温を上昇させることで、体内に侵入した病原体の増殖を抑える生体防御反応です。感染のシグナルが脳に伝わると、プロスタグランジンE2という物質が作られ、それが脳の体温調節の神経回路に作用することで一時的に体温を上げるのです。発熱は古代ギリシャのヒポクラテスの時代から知られる症状ですが、発熱の仕組みはまだ不明な点が多く、私達は発熱を指令する脳の神経細胞を研究しています。
風邪やインフルエンザのような感染症にかかると発熱が起こります。これは、体温を上昇させることで、体内に侵入した病原体の増殖を抑える生体防御反応です。感染のシグナルが脳に伝わると、プロスタグランジンE2という物質が作られ、それが脳の体温調節の神経回路に作用することで一時的に体温を上げるのです。発熱は古代ギリシャのヒポクラテスの時代から知られる症状ですが、発熱の仕組みはまだ不明な点が多く、私達は発熱を指令する脳の神経細胞を研究しています。
心理ストレスについて
 ストレスを感じたり、緊張すると心臓がドキドキし、体温が上昇します。これは誰もが経験する生理現象ですが、その仕組みは未解明です。私達は、心理ストレスによる生理反応を起こす脳の神経回路の解明を目指しています。特に、心理や情動が脳の生体調節システムに影響する「心身相関」の仕組みを研究しています。この研究で「ストレス」の科学的実体を解き明かすとともに、「病は気から」のように精神ストレスで起こる疾患の発症機序を解明したいと考えています。
ストレスを感じたり、緊張すると心臓がドキドキし、体温が上昇します。これは誰もが経験する生理現象ですが、その仕組みは未解明です。私達は、心理ストレスによる生理反応を起こす脳の神経回路の解明を目指しています。特に、心理や情動が脳の生体調節システムに影響する「心身相関」の仕組みを研究しています。この研究で「ストレス」の科学的実体を解き明かすとともに、「病は気から」のように精神ストレスで起こる疾患の発症機序を解明したいと考えています。
肥満(中年太り)について
 体温の調節は、脂肪を燃焼するなど多量のエネルギーを使うため、うまくいかないと肥満になります。私達は加齢に着目し、私達が発見した体温調節の神経回路が加齢によってどのように変容し、加齢性肥満(いわゆる中年太り)につながるのかを研究しています。加齢性肥満は、糖尿病や高血圧などの様々な生活習慣病につながるため、その根本的な原因を明らかにすることによって、「生活習慣病のない」健康長寿社会の実現に貢献します。
体温の調節は、脂肪を燃焼するなど多量のエネルギーを使うため、うまくいかないと肥満になります。私達は加齢に着目し、私達が発見した体温調節の神経回路が加齢によってどのように変容し、加齢性肥満(いわゆる中年太り)につながるのかを研究しています。加齢性肥満は、糖尿病や高血圧などの様々な生活習慣病につながるため、その根本的な原因を明らかにすることによって、「生活習慣病のない」健康長寿社会の実現に貢献します。
自律神経系などの生体調節システムに障害が生じると生命を脅かす問題につながるため、その仕組みを明らかにする研究は基礎医学のみならず臨床医学においても重要です。しかし、生体調節を担う脳の神経回路は複雑な構造を持つため、未解明の部分が多く残っています。私達は、最新の研究手法を従来法と融合させるユニークな方法論を用いて、これまで解明できなかった本質的な問題に迫ろうとしています。そして、基礎医学的な革新的研究を進めることで、生体調節に問題を抱える患者さんを救うことにつながるような成果を挙げたいと考えています。
Copyright (c) 2009-2025 Department of Integrative Physiology, Nagoya University Graduate School of Medicine