| ���É���w�����ȗՏ����C�v���O�����i2006�N�x�Łj(PDF�AWord�`���j |
![]()
�͂��߂�
���É���w�����Ȃɓ��ǂ��A���É���w�����Ȋ֘A�{�݂ɂď����ȗՏ����C���s����t�������I���~���ȏ����ȗՏ����C���s����悤�u���É���w�����ȗՏ����C�v���O�����v���쐬�����B�{�v���O�����𗘗p���āA�L�Ӌ`�ȏ����ȗՏ����C�ɗՂ�ł������������B
�Ȃ��A���{�����Ȋw�����������ď����Ȑ���̌��C�J�n�ƂȂ�̂ŁA���{�����Ȋw��ɑ��₩�ɓ���邱�Ƃ����߂�B���{�����Ȋw�����ɂ��ẮA���{�����Ȋw��̃z�[���y�[�W�ihttp://www.jpeds.or.jp/�j���A���É���w�����ȓ��ǂɂ��Ă͖��É���w�����Ȃ̃z�[���y�[�W�ihttp://www.med.nagoya-u.ac.jp/ped/�j���Q�l�ɂ��Ă������������B
2005�N1��
���É���w��w�@�����Ȋw�@��������
�@���É���w�����ȗՏ����C���l���郏�[�L���O�O���[�v
2006�N�x�ł̉����ɂ�����
��N�A�{�v���O�������쐬���A�����̈�w���w���A���C��̕��X�ɗ��p�����Ă����������B2006�N�x�ł́A�P�ɐ���/�w����̈ٓ����̕ύX�����ł͂Ȃ��A�����Ȋe����̃T�u�X�y�V�����e�B�[�Z�\�K���̋L�ڂ������ꂽ�B��w�@���w�ɂ��Ă��]���^�̑�w�@�R�[�X�ƎЉ�l��w�@�R�[�X�ɂ킯�āA�����Ɗe�������擾�̗������}��A�܂������悭�T�u�X�y�V�����e�B�[�Z�\���K���ł���悤�Ƀ��f���R�[�X������B�{�v���O�������Q�l�ɂ��āA������ẪX�y�V�����X�g�ɂȂ��Ă������������B
2006�N5��
���É���w��w�@�����Ȋw�@��������
�@���É���w�����ȑ��㌤�C�ψ���
���É���w�����ȗՏ����C�v���O�����ڎ�
���É���w�����ȗՏ����C�v���O����
�E���L��������ÁE�����ی��ɍv�����邽�߂ɁA�����ꂽ�����Ȉ���琬���A�n��̏�����Â̏[����}��A������w�̐i���Ɋ�^����B
�E��ʖڕW�̎�����ڎw���Ĉȉ��̎������H����B
�P�j���L���Տ��\�͂��������Ȉ���琬����B���ꂩ��̏����Ȉ�́A�o���O���琬�l�Ɏ���S�ے��𑍍��I�ɂƂ炦�A�����Â̎��_�ɗ�������Â̎��H��S�|����B
�Q�j��w�����a�@�A�֘A�a�@����̂ƂȂ�A�e����ɂ�����ō������̐�[��Â𐄐i����ƂƂ��ɁA����ɂ�����l�ނ̈琬�B�m�ۂɓw�߂�B
�R�j�����̈�w��n��o���̂ɕK�v�ȏ��𐢊E�ɔ��M����ƂƂ��ɁA�����\�͂�L����l�ނ��m�ۂ���B
�S�j�Љ�ɑ��A������ÁA�����ی��̏d�v����i���A����ɏ����Ȉ�̎Љ�I�n�ʂ̌���ɓw�߂�B
�T�j3�̎g���ł���A����A�f�ÁA�����̐��i�ɂ��č����̑��{�݂Ƌ������A����ɃO���[�o���Ȏ��_�ɂ����A���ی𗬂�}��B
II�D���É���w�����ȗՏ����C�v���O�����̖ړI
�E �{�v���O�����͏�L�́u���É���w�����Ȃ̈�ʖڕW�v�̎��H��ڎw�����߂ɍ쐬���ꂽ�Տ����C�v���O�����ł���B
�E �����Ȉ�Ƃ��ĕ��L���Տ��o����ς݁A�����Ȑf�Â̊�b�I�m���E��Z���K�����A�����Ȑ�����擾���邽�߂̌����悢�Տ����C�����B
�E �����Ȑ�����擾��ɁA�e�������擾�̂��߂̌��C�ɑ��₩�Ɉڍs�ł���悤�ɁA�e��啪��̐���擾�ɂ��Ă̏����ɒ���B
�E �����ȗՏ����C��ʂ��āA�Տ���Ƃ��Ă̊�{�I�p���A�a���Ƃ��̉Ƒ��ɐڂ���ԓx���K���ł���悤�ɂ���B
III�D���É���w�����ȗՏ����C�v���O�����̊Ǘ��^�c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
�E �{�v���O�����̊Ǘ��ӔC�҂͏�������i���É���w��w�@�����Ȋw�����j�Ƃ���B
�E �֘A�a�@������Ȃǂ�ʂ��āA����I�ɖ{�v���O�����̌��C���e�]���A�Č����������Ȃ��B
�E ����֘A�̏��ɂ��ẮA1�N��1��̍X�V�������Ȃ��B
�E �{�v���O�����̏C���A�����Ȃǂ́A���É���w�����ȑ��㌤�C�ψ���𒆐S�ɍ�Ƃ��s���B
IV�D�����ȗՏ����C�ɂ���
�P�j�W���I�ȏ����ȗՏ����C�R�[�X
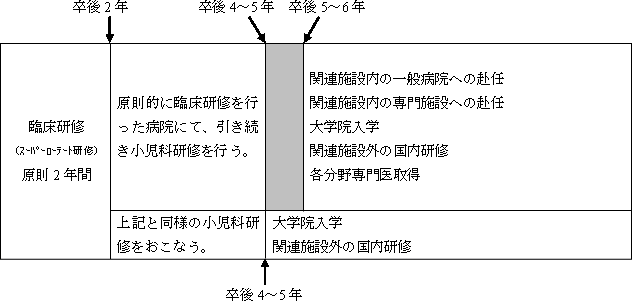
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�h�ׂ������͖���a�@���C�̊���
�E ����2�N�Ԃ͊e���C�a�@�̗Տ����C�v���O�����ɉ����A���[�e�[�g���C���s���B
�E ���[�e�[�g���C�I����́A�����I�Ɍ��C�a�@�̏����Ȃɂď����Ȍ��C���J�n����B�����Ȍ��C�ɓK���Ă��Ȃ��a�@�ł���ꍇ�́A�ٓ����l������B
�E �����I�ɐV�������C�͕K�{�Ƃ���B���C���ɐV�������C���s���Ȃ��ꍇ�͕K�v�ɉ����Ĉٓ����l������B
�E �����I�ɑ���4�`5�N�i�����Ȉ�Ƃ���2�`3�N�o����j�ɁA���É���w��w�������a�@�����ȂɂČ��C�i�ȉ��A����a�@���C�j���s���B����a�@���C�ɂ��Ă̌��C���e�ɂ��Ă͕ʂɋL���B
�E ����4�`5�N�ɑ�w�@���w�A�����a�@�Ȃǂւ̍������C���Ƃ�R�[�X���݂��邪�A������݂��āA���̌l��]�������̏�ŋ������鎖�������Ƃ���B
�@ �V���ǎ҃I���G���e�[�V����
�V���ǎ҂�ΏۂɁA2��3���̏h�����C����J�Â���B�I���G���e�[�V�����ł͏����ȁA�֘A�f�Éȁi�����O�ȁA���@��A�ȁA�畆�ȁA���_�_�o�ȂȂǁj�̊�b�I�u�`�������Ȃ��B
�u�V���ǎ҃I���G���e�[�V�����v�̎���i2004�N�x���{�j
�� ���F����16�N11��12���i���j�`14���i���j
�� ���F���������N�v���U�i���m���m���S���Y���厚�X��������R1�Ԓn��1�j
|
�� �� |
�� �� |
�u �t |
�� �e |
|
11/12 |
17�F00 |
|
���N�h����1�K�ɏW���@�`�F�b�N�C�� |
|
18�F00�`19�F00 |
|
�[�H�i11�K���X�g�����E�����|�[�l�j |
|
|
19�F00�`20�F00 |
���쏹�O |
�����E�V�����h���@ |
|
|
20�F10�`21�F10 |
��{���Y |
�A�����M�[�u�` |
|
|
�u�`�I����` |
|
��������@�e�r�� |
|
|
11/13 |
07�F30�` |
|
���H�i3�K���X�g�����E�T���[�e�j |
|
09�F00�`10�F00 |
�������v |
�_�o�u�` |
|
|
10�F10�`11�F10 |
�勴���� |
�z��u�` |
|
|
12�F10�` |
|
���H�i���R�j�t���[�^�C�� |
|
|
13�F30�`14�F30 |
�����F�F |
�����O�ȍu�` |
|
|
14�F45�`15�F45 |
��𗲎i |
������u�` |
|
|
16�F00�`17�F30 |
|
���R���ԁi�����Ȃǁj |
|
|
17�F30�`18�F30 |
�������� |
���t�w�u�` |
|
|
19�F00�`21�F00 |
|
���e��i4�K�a���j |
|
|
11/14 |
07�F30�` |
|
���H�i3�K���X�g�����j |
|
09�F00�`10�F00 |
�s�z��v |
�t�����u�` |
|
|
10�F30�`11�F30 |
���c���t |
��ӎ����u�` |
|
|
�u�`�I���� |
|
���U |
�A ���É���w�Տ������ȃZ�~�i�[
�e��啪��̑��l�҂������O���珵�ق��čs���Ă���u���`���̃Z�~�i�[�ŁA�N����J�Â��Ă���B�Z�~�i�[�̌�ɍ��e����J���āA�u�t�Ƃ̐e�r��[�߂Ă���B
�u���É���w�Տ������ȃZ�~�i�[�v�̎���
��15�É���w�Տ������ȃZ�~�i�[�@
�u�@�t�FProf. Anton H. Sutor�iFreiberg University�j
���@��FGuideline for Treatment of ITP
��16�É���w�Տ������ȃZ�~�i�[
�u�@�t�FDr. Charlotte M. Niemeyer�iFreiberg University�j
�Ǘጟ����`��
��17�É���w�Տ������ȃZ�~�i�[
�u�@�t�FProf. Mirko Diksic�iMcGill University�j
���@��FA study of the brain monoaminergic systems using PET
��18�����É���w�Տ������ȃZ�~�i�[�@
�u�@�t�FDr. Tong Wu�i�k����w�j
���@��FHaploidential Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) Compared with Matched HCT from Family Donors: Report of 216 Cases
�@
�B ���É���w�������֘A�a�@�Տ��Ǘጟ����
�֘A�a�@�𒆐S�Ƃ���������ł���A����P�̃e�[�}�����߁A���̎����E�a�Ԃɂ��ċc�_��[�߂Ă���B�N��2��J�Â���Ă���B
�u���É���w�����Ȋ֘A�a�@�Տ��Ǘጟ�����v�̎���
��43�É���w�����Ȋ֘A�a�@�Տ��Ǘጟ����
�e�[�}�F�����̎��a�ƃT�C�g�J�C��
���b�l�F����s���a�@������
��44�É���w�����Ȋ֘A�a�@�Տ��Ǘጟ����
�e�[�}�F�E�C���X�����ǂ̍�����
���b�l�F�g���^�L�O�a�@������
�C �ؗj��
�֘A�a�@���玡�ÁA�f�f�ɓ�a���Ă���Ǘ�A��L�ȏǗ�A����t�̋����L�v�Ǝv����Ǘ�����R�ɂ������C���t�H�[�}���ȏǗጟ����ŁA2�J���ɂP��A�ؗj���̗[���ɖ��É���w�����Ȃ̈�ǂōs����B�Ȃ��A2�����Ԃɖ��É���w��w�������a�@�ɓ��@�����Ǘ�̏Љ�������Ȃ��B
�u�ؗj��v�̎���
��@���F���É���w�����Ȉ��
�ǁ@��F
�i1�j�K�X�g���O���t�B�������ɂ��L�ߗ����𒎂̋쒎�ɂ��ē��ITP��1��
�i2�j�D���������ǂ�1��
�i3�j���x�̊̋@�\��Q�𗈂������a�s�S�^�i�H�j��1��
�i4�j���b�P���e���������ǐ��E�̌����ł������V������1��
�i5)����a�@���@������
�D ���É���w�������֘A�a�@�V�����J���t�@�����X
�֘A�a�@�Տ��Ǘጟ����Ɠ��l�ɖ���1�̐V�����̈�ɂ�����e�[�}�����߁A���̎����E�a�Ԃɂ��ċc�_��[�߂Ă���B�N��2��J�Â���Ă���B
�u���É���w�����Ȋ֘A�a�@�V�����J���t�@�����X�v�̎���
��9���֘A�a�@�V�����J���t�@�����X
�e�[�}�F���Y���E��o���̏d���̉h�{�Ǘ�
���b�l�F���É����ԏ\���a�@�@�������Y����q��ÃZ���^�[
��10���֘A�a�@�V�����J���t�@�����X
�e�[�}�F�V�����]��Q�A�������ɂ���
���b�l�F��_�s���a�@�@�V������
�E ���S�Ҍ�������
������C���̈�t��ΏۂƂ�������v���O�����ł���B�����Ȃ̊e����̊�{�I�Ȓm�������N�`���[����B1�N�Ԃ�4��i8���ځj���s���B
�u���S�Ҍ�������v2006�N�x�\�蕪
�E�ŐV�̚b���̎��Á@�@�|�V�K�C�h���C�����ӂ܂��ā|
�E�����̉摜�f�f�@�@�@�|����CT�AMRI�̓ǂݕ�
�E�S�d�}�̓ǂݕ��@�@�@�|�d�v�ȕs�����̐f�f�Ǝ���
�E�\�h�ڎ�@�@�@�@�@�@�|MR���N�`���A��E�������̃X�P�W���[���|
�E�����̓�����I�����@�|�����l�̉��߂Ɛf�f�E���Á|
�E���Z�̓ǂݕ�
�E�]�g�̓ǂݕ�
�E��V���S�����ɂ���
�@
�F �����S�Ҍ����V��������
�֘A�a�@�̎���t�A�Ō�t��ΏۂƂ��āA�V������Â̊�{�I�Ȓm�������N�`���[�������ł���B1�N�Ԃ�4��s����B
�u�����S�Ҍ����V��������v2006�N�x�\�蕪
�E�A�t�E�h�{�ɂ���
�@�@�@�E�ċz�Ǘ��ɂ���
�@�@�@�E�h���ɂ���
�@�@�@�E��o���̏d���̊Ǘ��ɂ���
�G ���S�Ҍ����u�K��
������Ẫg�s�b�N�X�ɂ��āA���̕���̑��l�҂̍u�t�������āA����t��ΏۂƂ����u�����s���Ă���B1�N��2��s����B
�u���S�Ҍ����u����v�̎���
�ŐV��PALS�ɂ��ā@�|�K�C�h���C��2005���ӂ܂��ā|
���������ÃZ���^�[�@�W�����Éȁ@���쑏�搶
�@�@�����ȗՏ����C�̒��Ŗ���a�@���C�������Ȃ��Ӌ`�́A��w�����E����E��w�@���Ƃ̂Ȃ���i�c�̂Ȃ���j�Ɠ�����̂Ȃ���i���̂Ȃ���j���`�����邱�ƂƁA�e���C�a�@�Ԃ̎��Â̕W������}�邱�ƁA���ۉ��ւ̓����A�����ւ̓����ł���B�܂��A���C�a�@�Ōo���ł��Ȃ������Ǘ���o�����āA�����Ȑ���擾�̂��߂̌��C��⊮���邱�Ƃ��ړI�̂P�ł���B�Z�����C���Ԃł��邪�A�L�Ӌ`�Ȍ��C�ł���Ɗm�M���Ă���B
�E ���C�����E���C���ԁF
�����Ƃ��đ���4�`5�N�i�����Ȉ�Ƃ���3�`4�N�ځj�ɁA6�`12�J���Ԃ����Ȃ��B
�E ���C���@�F
�`�O���[�v�i���t�E��ᇁj�A�a�O���[�v�i�_�o�A�A�����M�[�A�E�C���X�A�Ɖu�A�z��j�A�b�O���[�v�i�V�����j�̊e�f�ÃO���[�v�����[�e�[�V��������`�����Ƃ�B�e�O���[�v�̃��[�e�[�V�����̊��Ԃ́A���C�a�@�ɂ����錤�C���e���l�����Č��肷��B
�E �w��\�F
���C���Ԓ��ɁA���{�����Ȋw��C�n������͂��߁A�e����̊w��A������ɂČ������\�A�Ǘ�������Ȃ��B
�E ����a�@���C�ɂ������ȋ����֘A�s���F
�@ �V���@���҃v���[���e�[�V����/������f
���T�ؗj���̌ߌ�1������a��5�K�̋���X�y�[�X�ŁA1�T�Ԃ̐V���@���҂̏Ǘ�������Ȃ��A���̌��5E�a���i�������ȕa���j�̋�����f�������Ȃ��B������ʂ��āA�u�Ǘ�̋Z�p����v�Ɓu�e���C�a�@�ɂ����鎡�Â̈Ⴂ�̕W�����v���s���B�܂��A�O���l���w���A�O���l���C�����Q������ꍇ�́A�p��ɂ��Ǘ�A���_�������Ȃ��A���ۉ��ɑΉ��ł��鏬���Ȉ�̈琬���s���Ă���B
�A ��Ǐ��lj�
�����Ƒ�w�@�������S�ƂȂ��AScience�A Nature�ACell�Ɍf�ڂ���Ă���_���̏��lj��1�J����1���Ȃ��Ă���A���q�����w�I����̃g�s�b�N�X�ɂ��Ă̒m����[�߁A��b�����ւ�exposure��}��
�B ���@�����Ǘጟ����
������f�Ɉ��������A�Տ����K�̈�w���w���������āA�u�T���ɏ����Ȉ�ǂōs���Ă���B���@���҂̒����狳��I�ȏǗ�����グ�āA�P�Ǘ�ɂP���ԂƏ\���Ȏ��Ԃ������ďǗጟ�����s���Ă���B�Տ��f�f�Ɏ���ߒ���ӕʐf�f���d�������J���t�@�����X�ł���B
�C �֘A�a�@�Տ�����
�u�֘A�a�@�Տ��������[�L���O�O���[�v�v�����S�ƂȂ�A����f�ÂŔ�r�I�悭�f�鎾�a��ΏۂƂ����Տ������𗧂��グ�Ă���B���C���Ԓ��Ƀ��[�L���O�O���[�v�ɎQ�������āA�Տ������̊��A�^�c�ɂ��Ă̕��@�_���K������B
�D ��w�@�������\��
��w�@�d�_����͑�w�@���������Ȉ�ǂ̔����ȏ���߁A�w�O���܂ߌ����������s���Ă���B������w�@���̌����̐i�s����ъe�������Ԃł̏�������ړI�Ƃ��āA�u�����ɑ�w�@��������s���Ă���B��w�@���͊e���̌����̔w�i�A���@�_�A�����ߒ��ɂ��Ċ֘A�a�@�̈�Lj����܂ތ��J�̏�Ō������\�������Ȃ��B
�E �S���w��E���ۊw���
�e�������̍ŐV�̐��ʂ���邱�ƂŁA��Lj��S�̂Ɋe����̌����̓������Љ�A�m���̋��L��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ċu�����Ɋw�����s���Ă���
�E �e�f�ÃO���[�v�̐f�Â̓����ɂ���
�����t��������
�Đ��s�ǐ��n���┒���a/���������p��Ƃ��������t�����ɉ����āA�_�o��זE���E�C�����X��ᇁA�]��ᇂ⍜����ȂnjŌ`��ᇂ̊��҂����@���Ă���B�����̎����ɑ��āA�W�w�I���Â�ڎw���A���w�Ö@�③�����זE�ڐA���s���Ă���B2005�N�ł́A�������זE�ڐA�͍����o���N�h�i�[����̔��Ҋԍ����ڐA7��A���`�ь��ڐA3��A�����Ҋԍ����ڐA9��A���Ɩ��������זE�ڐA6��̌v25��̎��тł���B�O���ł́A�t�@���R�j�n�����V���D���������ǁiKostmann, myelokathexis�j�Ȃǂ̋H�Ȏ����⌴���s���̕n���A�����s�S�nj�Q�̊��҂��Љ��Ă���B�܂��A�����ƗՏ�����������������ڎw���Ă���A�Đ��s�ǐ��n�����N�^���������������a���ǂ̃��f�������̍쐬�A�����a���ǂɊ֗^����GATA1��PTPN11��`�q��́A�������זE�ڐA��̃E�C���X�����ǂ̉�́A�E�C���X���ٓI�זE��Q��T�����p���̑̊O�������̗Տ��������i�s���Ă���B���ɍ��N�x�́A���x��i��ÊJ���o��Ō��݂����Z���v���Z�b�V���O�Z���^�[��ISO9001�AISO13485���擾�������Ƃ���A�{�i�I�ȉғ����\�肳��Ă���B�����זE�ڐA�̎��Ð��т̌����ڎw�����זE�Ö@�̎��{���v�悳��Ă���B
���A�����M�[��������
�f�Ï�/�s���a�@/�ی���������u��v�Ƃ��ďЉ��Ă����A�����M�[�������ҁi�b���A�H���A�����M�[�A�A�g�s�[���畆���A�����@���]�Ȃǁj�𒆐S�ɐf�Â��Ă���B�������A�^�̓�Ǘ�͏��Ȃ��A�Ǐ�c���𐳊m�ɍs���A����Ɋ�Â��ĕW���I�Ȏ��Â���邱�Ƃő����̏Ǘ�ŗǍD�Ȏ��Ì��ʂ������Ă���B
���E�C���X��������
�@����E�C���X�����i����������EB�E�C���X�����ǁA���}���d�����S�]���Ȃǁj�̎��ÂƊ̉��i���ɃE�C���X���j�ɑ���f�f�i�̐����j�A���Ái�C���^�[�t�F�����j�𒆐S�Ƃ����f�Â��s���Ă���B�܂��A�l�X�ȃE�C���X�����ǂ̈�`�q�f�f���s���Ă���A���ɑ���ڐA���ҁi���̊̈ڐA�Ǘ�j�A�������זE�ڐA���҂ɑ���E�C���X���j�^�����O�V�X�e���Ƒ������ÃV�X�e���͑��{�݂ɂ͂Ȃ���[�I��Âł���B
���_�o��������
�O�����҂ł͓�Ă�̏ǗႪ���|�I�ɑ����A��ʕa�@�̊��ґw�Ƃ͒������قȂ��Ă���B�܂��A�s���a�@�ł͎��{����������Ȑ_�o�����w�I�������{�s���Ă���B���ɁA���쎞�r�f�I�]�g�����L�^�͔N��100����̎��т�����B�Տ�����ʂł́A�u�����]�g����v���s���Ă���A�����]�g�����ǂł���悤�Ɏw�������Ă���B�܂��A�_�o�w�I�����̂Ƃ肩���A�Ă҂ւ̖�f�Ȃǂ̎w�����s���A�����_�o�����ɑ��闝����[�߂���悤�ɂ��Ă���B
���V������������
�@�@�@�W�w�I���Y����Â��K�v�ȏǗႪ�����B��̓I�ɂ́A�َ��f�f�����Ă����V�����u���փ��j�A��َ�����Ȃǂ̏Ǘ���Y�ȂƂƂ��ɑَ�������Ǘ������Ă���B���ɐ�V�����u���փ��j�A�ɂ͗͂�����Ă���A2005�N�ł�9��̎��Î��т�����A�����ł��L���̏Ǘᐔ�ł���B�܂��A���Y���݂̂Ȃ炸�A�����O�ȏǗ�A�]�_�o�O�ȏǗ�A�d�ǂ̖��n���Ԗ��ǏǗ�ȂǑ��ʂȎ��������C���邱�Ƃ��ł���B
���Ɖu��������
�{�������ł͏ڍׂȖƉu�������`�q�f�f���s�����Ƃ��\�ł���B����s�����Ƃɂ��A�v���Ɍ��ʂ邱�Ƃ��ł��A�O�����ҁA�a�����҂̐f�f�y�ю��Âɖ𗧂ĂĂ���B �܂��A�{�M�ɂ����Ă̌������Ɖu�s�S�ǂ̐f�f�A���ÁA�����̓p�C�I�j�A�I���݂ł���A�Ǘ�̏W�ς͍����ł̓g�b�v���x���ł���B�Տ��f�f�A��`�q�f�f�A���Âƈ�т��čs���鍑���ł������Ȃ��{�݂̂P�ł���B
���z�팤������
��Ƃ��Đ�V���S�����̐f�f��t�H���[�A�َ��S�G�R�[�Ȃǂ������Ȃ��Ă���B��V���S�������̒��ɂ͐S�����ȊO�̍����ǂ����ꍇ�����邽�߁A���Ȃ⑼�{�݂Ƃ̋����Ō��ʓI�Ȉ�Â��s���悤�ɂƂ߂Ă���B
�E �e�f�ÃO���[�v�̏Ǘጟ����A����Ȃǂ̃X�P�W���[��
�����t��������
�Ǘጟ����F���T�Ηj���i�ߌ�4��00���`�j
�@�����J���t�@�����X�F���T�Ηj���i�ߌ�6��00���`�j
�@���t�W�{������F���T�ؗj���i�ߑO11��00���`12��00���j
�@���lj�F���T�Ηj���i�ߑO8��15���`�j�Տ��I���e�Ɋւ��镶���ɂ���
�@�@�@�@�@���T���j���i�ߑO8��00���`�j��b�I���e�Ɋւ��镶���ɂ���
�@�@�@�@�@���T�ؗj���i�ߑO8��00���`�j�����ɂ���
���A�����M�[��������
�Ǘᑊ�k��t�F�u�T���j���i�[���j
����F�u�T���j���i�ߌ�6��30���`�j�����������ی���Ñ����Z���^�[�ƍ���
���E�C���X��������
�@�@�@�Ǘጟ����F���T���j���i�ߌ�6��00���`�j
�@�@�@���lj�F���T���j���i�ߌ�7��00���`�j
���_�o��������
�@�Ǘጟ����F���T���j���i�ߌ�5��00���`�j
���쎞�]�g�����F���T���j���i�Ǘጟ����̌�j
���lj�F���T���j���i�ߌ�6��00���`�j
�摜���ǁE�֓lj�F���T�ؗj���i�ߑO8��00���`�j
�֘A�a�@����������F1�`2�����ɂP��i�ߌ�7��30���`�j
���V������������
�Ǘጟ����F���T���j���i�ߌ�6��30���`�j
�@�@�@���Y���J���t�@�����X�F�u�T���j���i�ߌ�6��00���`�j�Y�Ȃƍ���
���lj�F���T�`���j���i�ߑO8��00���`�j
���Ɖu��������
�@�@�@�Ǘጟ����F�s����i�K�v�ɉ����čs���Ă���j
����F���T�P��
V�D�o������ׂ��nj�E�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
�@�@���C���́A�l�X�Ȏ��a���Ȃ��o�����邱�Ƃ��d�v�ł���B���C���Ɍo������ׂ��nj�E�����ɂ��ẮA���{�����Ȋw����s���Ă���u�����Ȑ���@�Տ����C�蒠�v��19�`37�łɋL�ڂ�����B����21�N�ȍ~�͏����Ȑ��㎎���ɍۂ��āA�u�����Ȑ���@�Տ����C�蒠�v�̒�o���`���Â����邽�߁A�u�����Ȑ���@�Տ����C�蒠�v�𗘗p���āA�o�������nj�E�������L�^���Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�@�@�Տ����C�ł́A���ȕ]�����s�����Ƃ��K�v�ł���B�����Ɏw����]�����s�����ƂŁA���C���e�̌��������͂�����B���C�̎��ȕ]���A�w����]���ɂ��Ă����{�����Ȋw����s���Ă���u�����Ȑ���@�Տ����C�蒠�v��8�`9�ŁA12�`17�łɋL�ڂ����邽�߁A����𗘗p���邱�ƂƂ���B
�u�����Ȑ���@�Տ����C�蒠�v�́A�����Ȍ��C���J�n����ۂɁA�e�{�݂̐ӔC�҂���z�z�����Ă��炤���ƁB
VI�D����擾�v���O����
�����Ȃ̐��㐧�x�ɂ́A�����Ȑ���̂ق��ɏ����Ȋe����ɐ��㐧�x�����݂���B�����ȏ������C�̖ړI�̂ЂƂɁA�����Ȑ�����擾��ɃT�u�X�y�V�����e�B�[���琬���邱�Ƃ���������B�{�w�����Ȃł̌��C�v���O�����ɁA�e��啪��ɂ�������㐧�x�Ɋւ���������̂ŁA�e����̐���擾�ɗ��p���Ă������������B
�@ �����Ȑ��㐧�x
���@�́F�����Ȑ���
����F��w��F���{�����Ȋw��ihttp://www.jpeds.or.jp/�j
�T�@�v�F���{�����Ȋw��F�肷��B�]���̔F�萧�x���A2002�N�ɏ����Ȑ��㐧�x��V���Ɏ{�s�����B�����Ȑ���͏����ی������鏬����ÂɊւ��Ă����ꂽ��t���琬���邱�Ƃɂ��A������Â̐�������i�����W��}��A�����̌��N�̑��i����ѕ����̏[���Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A����̑��㌤�C���I����������ɑ��A���������{���A���i��F�߂Ă���B���i��5�N���ƂɐR���̂����X�V�����B
������18�N�܂ł͏]���̔F��㐧�x�����{�B����14�N����18�N�ɔF���ɂȂ������̂́A�o�^���ꂽ�ȍ~��1�N�Ԉȏ�̐E���A���C���e��Y�t���Ď����^�c�ψ���ɐ\������B�����^�c�ψ���ŐR�����A����ɑ�������5�N�ȏ�̌��C���Ԃ��I�������ƔF�߂�����̂����i�Ƃ��A������ŏ��F����B
�K�v�����F�@
A�j���������Ɋw�����ł���A�w����������������3�N�ȏ�A�������͒ʎZ����5�N�ȏ�ł�����́B
B�j2�N�Ԃ̑���Տ����C���A���̌コ��ɏ����Ȑ��㐧�x�K����15���ɋK�肷�鏬���ȗՏ����C��3�N�ȏ�����́B�������͏����ȗՏ����C��5�N�ȏ�����́B
a�j�����ȏ������C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�l�����͋K��Ȃ�
�@b�j����֘A�ł̐���F��{��
�@�@�E����F��{��
�@�@�@�@���É���w��w�������a�@�A�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�A�t����s���a�@�A����s���a�@�A���������a�@�A�ɓ�s���a�@�A���É����ԏ\���a�@�A���É��t�ω�a�@�A�Љ�ی������a�@�A�g���^�L�O�a�@�A���m�������_�Ƌ����g���A������Εa�@�A���m�������_�Ƌ����g���A����a�a�@�A�J�������@�\�����J�Еa�@�A���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�A���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�A���ƌ��������ϑg���A�����a�@�A�����������ی���Ñ����Z���^�[�A���_�s���a�@�@
�@c�j�����Ȑ�����擾���邽�߂̉ߒ���擾�����F
���C��5�N�ԂŁA����F��{�݂ł̌��C�ƂȂ�B
�@d�j�����Ȑ�����擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
2�N�̗Տ����C�Ɉ��������āA�����Ȃ̎w�茤�C�{�݂�3�N�ԏ����Ȍ��C�B�����Ȃɓ��nj�́A�����ɓ��{�����Ȋw��ɏ��������C���J�n����B
�i�w���������p��3�N�ȏ�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�w���̑ؔ[������ƔF���擾���������ꍇ�����邽�߁A�w���̑ؔ[�ɂ͒��ӂ��邱�ƁB�j
�A �����Ȋe����̐����i�F���j���x�ɂ���
�ȉ��̊e���ڂ��e����̐��㐧�x�ɂ��ڏq����B�ŐV�̏��ɂ��Ă͋L�ڂ��Ă���w��z�[���y�[�W���Q�Ƃ��ꂽ���B
����i�F���j�̖��́A�F��w��A�擾�K�v����
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���i�F���j�@
b�j����֘A�ł̐���i�F���j�F��{�݂Ɛ���i�F���j�E�w����̐l��
c�j����֘A�a�@���Ƃ̓����i�����̍ۂ̖���֘A�Ƃ́A�W���錤�C�\�Ȏ{�݂��܂ށj
d�j�e�������i�F���j���擾���邽�߂̉ߒ���擾����
e�j�e�������i�F���j���擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�����{�������t�w��@����������Ɋւ��Đ���i�F���j���x�͌��ݏ������B
���́F���{���t�w�����i������)
����F��w��F���{���t�w��ihttp://www.jshem.or.jp/�j
�K�v�����F
�E�����ȔF���擾��A���{���t�w��̔F��{�݂ŗՏ����t�w�̌��C��3�N
�E���{���t�w��̉����3�N
�E�Տ����t�w�Ɋւ���w��\�܂��͘_����2�ȏ�
�E�������@���҂̂���10���̐f�Î��ыL�^�̒�o�B�Ǘ��3�̈�i�Ԍ��������A�����������A�o�����𐫎���)�̂��ꂼ��ɂ����ď��Ȃ��Ƃ�2����܂ށj
�E����F�莎������
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F
�E�F��{�݂̂��߂̐���̐l���̋K��͂Ȃ�
�E�F��{�݂Ƃ��Ė��N���ސR������
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�E����F��{�݁F�i���{���t�w��F��̖��召���Ȋ֘A�a�@�j
�@�@�@�@���É���w��w�������a�@�A���É����ԏ\���a�@�A�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�A���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�A����s���a�@�A���S�a�@�A���É��L�O�a�@�A���m�������_�Ƒg���A����a�a�@�A�튊�s���a�@�A�Љ�ی������a�@�A�g���^�L�O�a�@�A���É��t�ω�a�@
�E����F
������w��w�������a�@�@������ �@�@�@�@��������
�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�@������ �@�@�@�@�x���h�O
���É����ԏ\���a�@�@������ �@�@�@�@�@�@�@�@��������
���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�@�����ȁ@�@�{���Y��
���S�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@��
�E�w����F
������w��w�������a�@�@������ �@�@�@�@��������
�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�@������ �@�@�@�@�x���h�O
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�E���É���w��w�������a�@�F�Đ��s�ǐ��n���E�_�o��זE��𒆐S�Ƃ��āA�L�͂ȓ���̌��t�E��ᇎ������J�o�[����B�Ǘ�������B���זE�ڐA�Ǘᐔ�F25��i2005�N�j�B�S����w�����a�@�̏����Ȃ̒��ł͍ł������B�Đ��s�ǐ��n�����Ì�����̑S�������ǁB�P��{�݂ł̏����Đ��s�ǐ��n���̎��ÏǗᐔ�͐��E�L���B���t�E��ᇂɊւ���Տ������b�I�����܂Ŏ{�s�B�q�g�ւ̍זE���Â��\�ɂ���GMP��ɍ��v�����Z���v���Z�b�V���O�Z���^�[�݁B
�E���É����ԏ\���a�@�F�e��̓���̑������זE�ڐA����j�I�ɐ������肪���Ă���A���ɗݐψڐA�Ǘᐔ�͑S�����w�B�܂��}�������p�������a�A�}�������������a�A���������p��A�Ō`��ᇁA���ᇐ��̌��t�����̖L�x�ȏǗᐔ��L����B
�E�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�F�����J���Ȃ��w�肷�錌�t�E�����펾������̍��x����Î{�݂ł���A�����Ȃɂ����Ă��}�������p�������a�E���������p��E�Ō`��ᇂ����߂Ƃ��āA�L�͂Ȍ��t�E��ᇎ����������ǗႠ��B�����̗Տ������Z���^�[�ɂ́A���{���������a�����p����O���[�v(JPLSG)�̃f�[�^�Z���^�[������A�S�����珬���������ᇂ̃f�[�^���o�^�W�v����Ă���B
�E���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�A����s���a�@�A���S�a�@�F�Ǘᐔ�͏�L3�a�@�Ɣ�r���ď��Ȃ��B
�@d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�E�����Ȑ���擾��A3�N�ȏ�̔F��{�݂ł̌��C���K�v�B�Տ��ł͌����I�ȍl�������K�v�ł��邽�߁A��w�@���w�����߂Ă���B��w�@�݊w���ɏ����Ȑ���̎��i���擾���Ă���A�ŒZ�ő�w�@�C�����Ɍ��t����̎��i�邱�Ƃ��\�ł���B
�E��w�@�R�[�X�F�ŏ��̔��N�`1�N�Ԃ͑�w�ŗՏ����C���s���A�c��̊��Ԃ͐f�Ãt���[�Ō����ɐ�O����B�]���^�̃R�[�X�B
�E�Љ�l��w�@�R�[�X�F��w�i�g���͈���ɏ�����j���邢�͊֘A�{�݁i���É����ԏ\���a�@�A�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�Ȃǁj�ŁA���t�w�̕����3�N�ȏ�̗Տ��o����ς݁A�����6��������1�N�̌������ԂŋƐт��܂Ƃ߁A�w�ʂ��擾���Đ��㎎��������R�[�X�B
�Ȃ��A��w�@�I����A������擾������͊C�O���w�A���t���{�݂ւ̏A�E�A�����ւ̔C�p�A���̓����J����Ă���B
�����{�����A�����M�[�w��ihttp://www.iscb.net/JSPACI/�j������2�K�����x�ֈڍs��
���́F���{�A�����M�[�w�����@�u���{�A�����M�[�w�����i�����ȁj�v
����F��w��F���{�A�����M�[�w��ihttp://www.js-allergol.gr.jp/�j
�K�v�����F
�E�F�苳��{�݂ɂ����ĒʎZ2�N�ȏ�̓��@���҂̐f�Âɏ]�����Ă��邱�ƁB
�E����I�ȊO���f�Â������Ȃ��Ă��邱�ƁB
�E�A�����M�[��������100��ȏ�̐f�Î��т����邱�ƁB
�@�@�E�u�����Ȑ���A���{�A�����M�[�w��̉����7�N�v�i�������j
a�j ��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F
�@�@���{�A�����M�[�w��F��w����1���ȏオ���
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�E�֘A�a�@�ɂ��������F��{�݁F
���É���w��w�������a�@�A�����������ی���Ñ����Z���^�[�A
���c�ی��q����w
�@�@�@�i�����Ȑ���Ɋւ��āA���ʂ͐���F��{�݂ł̌��C�͗v������Ȃ��j
�E����F
���É���w��w�������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@��{���Y
�����������ی���Ñ����Z���^�[�@��ٷް�ȁ@�@�ɓ��_��
�J�������@�\�����J�Еa�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�R�c�����A��ؐ��q
���É��t�ω�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɓ��a�]
�ɓ�s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�� ��
�������z�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�r �N
���������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X����j
�E�w����F
�����������ی���Ñ����Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�ɓ��_��
�J�������@�\�����J�Еa�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�R�c����
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�@���㌤�C�̉\�Ȏ{�݂́A�w���オ�Ζ����邠���������ی���Ñ����Z���^�[�̃A�����M�[�Ȃ̂݁B
�@d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@�@�����A�����M�[�̎w���オ�ݐЂ���{�݁i����֘A�ł͂����������ی���Ñ����Z���^�[�̂݁j�ŏ��Ȃ��Ƃ�1�N�Ԃ̗Տ����C���s���������ŁA�ł����2�N�ȏ�̌����������o������i����֘A�ł͖��É���w��w�@�̂݁j�B
e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�E��w�@���w�R�[�X�F1�N�Ԃ������A�����M�[��匤�C�ɂ��Ă邱�Ƃ��]�܂����B���̏ꍇ���C���\�Ȋ֘A�{�݂́A�֘A�a�@���ł͂����������ی�������ÃZ���^�[�݂̂ł���A�����ւ̍������C���K�v�ȏꍇ������B
�@�E�Љ�l��w�@�R�[�X�F�����������ی�������ÃZ���^�[�ɐg����u���A1�N�ԑ�w�ɋA�ǂ���R�[�X�̂ݗL�p�Ǝv����B��w���̈���̃|�X�g�ɂ��Ă͌����ɂ��Q������R�[�X�̓A�����M�[�O���[�v�ɂ͔F�߂��Ă��Ȃ��B
�@�E��w�@�ȊO�̃R�[�X�F��ʏ����Ȍ��C���I�������シ�݂₩��2�N�Ԃ̏����A�����M�[���Տ����C�ɂ��Ă邱�Ƃ��]�܂����B�f�ÁE�X�^�b�t�̋K�́A�g���ۏᓙ���l������ƁA����ɂӂ��킵�����C�{�݂͊֘A�a�@���ɂȂ��A�����ÃZ���^�[�A�����a�@�@�\�����a�@�Ȃǂ֍������C���K�v�ƂȂ�B
���́F���{�����NJw�����
����F��w��F���{�����NJw��ihttp://www.kansensho.or.jp�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���F���6�N�ȏ�A���{�����NJw��̉����5�N
�E�����ǂ̗Տ��Ɋւ��ĕM���҂Ƃ��Ă̘_�����\1�сA�w��\2�сA�v3��
�@�E�F�莎������
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�K��Ȃ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�E����F��{�݁F�K��Ȃ�
�E����F
�@�@�@���É����q��w�Ɛ��w�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�鑺�v��
�@�@�@���S�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��䒼��
�@�@�@�@���m�������_�Ƌ����g���A����a�a�@�@�����ȁ@�@���藲�j
�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ēc����
��{�s�������s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�G
���́F���{�����_�o�w�����
����F��w��F���{�����_�o�w��ihttp://www.yo.rim.or.jp/~JSCN/jscnhome.html�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���A���{�����_�o�w��̉����5�N
�E�Ǘ�v��30�Ǘ�ƏǗ�ڍו�5��
�@�E�M�L�����E�ʐڂ���
�@�@�E���{�����_�o�w���E�n����ɏo�Ȃ������v��20�P�ʈȏ�
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F1���ȏ�̐��オ�K�v
�@b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�E����F��{�݁F�K��Ȃ�
�E ����
�@�@�@�@���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�@�����_�o�ȁ@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���q�A�F�J�r���A�O�Y���M�A�����݂�
�@�@�@�����������ی���Ñ����Z���^�[�@�_�o�ȁ@�@�@�@�@�@�����a��
�@�@�@���m���X���_�Ƌ����g���A������Εa�@�@�����ȁ@�@�@���c���t�A�Ό����q
�@�@�@����������Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����K�O�Y�A�H��i�q
�@�@�@�@����s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���앶�Y�A��؊
�@�@�@�@�s�����c�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������q�b
�@�@�@�@�����a�@�쐶���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�����v
�@�@�@�@���É����ԏ\���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ێR�K��
�@�@�@�@������w��w�������a�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�������q
�@�@�@�@���É���w��w�������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ėځ@�~
�@�@�@�@�O�H�����a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����q�i���j
�@�@�@�@���É��L�O�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���]���q
�@�@�@�@���m���X���_�Ƌ����g���A�������X���a�@�@�����ȁ@�v�ۓc�N�v�@�@�@
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E���É����ԏ\���a�@�F�]�ǂ₯�����d�ςȂǂ̋}�����������A�]����ჁE�Ă�Ȃǂ̖��������������BMRI�APET�Ȃǐ_�o�摜��p�����������\�ł���BNICU�������ߐV�����]�g�̋L�^������
�@�@�E����s���a�@�F�]�ǂ₯�����d�ςȂǂ̋}�����������A�]����ჁE�Ă�Ȃǂ̖��������������B�V�����]�g���n�߂Ƃ���V�����_�o�w�ɗ͂����ėՏ��E�������s���Ă���ق��A�T�C�g�J�C���ƒ����_�o�����Ƃ̊֘A��A�_�o�摜�ɂ��Ă��Տ��E�����Ŏ��т�����B
�@�@�E���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�F�V�����_�o�̏Ǘᐔ�͊֘A�a�@���ōő��ł���B�]�ǂ₯�����d�ςȂǂ̋}�����������A�]����ჁE�Ă�Ȃǂ̖��������������B�V�����_�o�w�ɍł��d�_�������ėՏ��E�������s���Ă��邪�A�Ă��_�o�摜�̕���ł����т������B
�@�@�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�F�d�x�̏�Q���������A��Q���̕�I�P�A�����C����̂Ɍ����B�܂��A�֘A�a�@�̒��ŋ؎����̌��C���ł���B��̕a�@�ł���B�܂��A��V�ُ펙�������A��`�������ɂ��Ă̌��C���\�ł���B�����ʂł͈��m���S�g��Q�҃R���j�[���̌������Ƃ̃R���{���[�V�������ł���\��������B
�@�@�E������Õ����Z���^�[�F���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@��������ɗÈ�{�݂Ƃ��Ă̐��i�����B��Q����Âɐڂ��ė�������@��ɂȂ�Ǝv����B
�@�@�E�����������ی���Ñ����Z���^�[�F�n��̒��S�{�݂Ƃ��āA��V�ُ킩��Ă�܂ő����̏ǗႪ�W�܂����B����͌��C�{�݂Ƃ��ċ@�\�ł���\�����������A���݂͏�X�^�b�t1���ł���A�\���Ȍ��C������ł���B���2���m�ۂł���A��Ȃ����C����̂ɗǂ��{�݂ɂȂ�Ǝv����B
�@d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@�@�������C�a�@�ł̌��C���e�ɂ���邪�A�����Ȑ�����擾��2�`3�N���x���É���w��w�������a�@���A��L�̂悤�Ȍ��C�ɓK�����a�@�ł̃g���[�j���O���K�v�ł���Ǝv����B
�@�@�@����擾�Ɋւ��ẮA1�����̕a�@�ł�����x�̊��Ԍ��C����Ή��Ƃ��Ȃ�Ǝv���邪�A�����_�o�Ȉ�Ƃ��Ă�neurologically sick children, neurologically handicapped children�̕�Ȃ��f�Âł��邱�Ƃ��]�܂�邽�߁A2�`3�����̌��C�{�݂Őf�Âɏ]������̂����z�ł��낤�B
�@e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E��w�@�ɐi�w����ꍇ�F�Œ�1�N�͖��É���w��w�������a�@�ł̗Տ��Ɩ��ɏ]������B�㖱�Ő_�o�O�����p���I�ɒS������B
�E��w�@�ɐi�w���Ȃ��ꍇ�F��L�̂悤�Ȍ��C�ɓK�����a�@��2�`3�N���C���邩�A���É���w��w�������a�@�ň���Ƃ��ėՏ��Ɩ����s���B
�E�_�o�������Ƃ��ẮA�w���ł����t��K���ȕa�@�ɔz�u���邱�Ƃ��K�v�ƍl���Ă���ANICU�̂���a�@���ׂĂɎw���͂̂����t���Œ�1�l�A�ł���Ε����z�u�������B������z�u���闝�R�́A�_�o�����̐f�Âɂ����Ă͕����̖ڂŌ��ċq�ϐ��E�Ó������m�ۂ���K�v�����邩��ł���B�]�g�̔��ǂЂƂ��Ƃ��Ă��A��l�ōs���Ă���ƕ肪�ł��Ă��܂��͔̂������Ȃ��B
���́F���Y���V��������
����F��w��F���{���Y���E�V������w��ihttp://plaza.umin.ac.jp/%7Eneonat/�j
�K�v�����F
�E���{�����Ȋw�����
�E���{���Y���E�V������w��������3�N�ȏ�
�E�F�茤�C�{�݂ɂ�����3�N�Ԃ̌��C�i6�J���͎w�肳�ꂽ��a�@�ł̌��C���K�{�j
�E�w��F�߂���Y����w�C���Y����ÂɊ֘A���錴���_�� 1 �҈ȏ��M�����҂Ƃ��č��ǐ��x�̂���G���ɔ��\���Ă��邱�ƁB
�E�w��F�߂���Y����w�֘A�w��ɏ���̉C�Q�����C���M�����҂Ƃ��Ĕ��\���s���Ă��邱�ƁB
�E�M�L��������
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�@
�E1���ȏ�̎w���オ�K�v
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�E�b����Ԓ��̂��߁A����F��͕���19�N�ȍ~�ƂȂ�B�w����͓��{���Y���E�V������w��̐���ψ���I�l�����b��w����ł���B
�E���C�F��{�݁F
�@�@��{�݁F���É����ԏ\���a�@�������Y����q��ÃZ���^�[
���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@������
��_�s���a�@����ȁi�����z��E�V�����ȁj
�w��{�݁F���É���w��w�������a�@���Y��q�Z���^�[�A���������a�@�����ȁA�g���^�L�O�a�@���Y����q��ÃZ���^�[�A����s���a�@�����ȁA���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�V������
�⊮�{�݁F���c�s�����c�a�@������
�E�w����i�b��w����j�F
���É����ԏ\���a�@�@�������Y����q��ÃZ���^�[�@�@��ؐ�ߎq
���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�@�����ȁ@�@�@�@���쏺��
��_�s���a�@�@����ȁi�����z��E�V�����ȁj�@�@��� ��
���É���w��w�������a�@�@���Y��q�Z���^�[�@�@�@�@�@���쏹�O
���������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɠc�P�q
�g���^�L�O�a�@�@���Y����q��ÃZ���^�[�@�@�@�@�@�@�@���c����
����s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���앶�Y
���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�@�V�����ȁ@�@�@�@�@�R�c����
c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�E���É����ԏ\���a�@�������Y����q��ÃZ���^�[�F���m�����F�肷�鑍�����Y���Z���^�[�ł���B�N��500�Ǘ������@���т�����B����o���̏d�����͂��߁A���Y���Ǘ����K�v�ȏǗႪ�L�x�ł���B
�E���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�F�N��30�Ⴟ�����̒���o���̏d���̓��@���т�����B���㌤�C�ɂ������a�@�ł���A���O�͒n��̒��S�I�a�@�Ɉʒu�Â�����B
�E��_�s���a�@�F����o���̏d�����͂��߂Ƃ��āA�d�ǐV�����̏ǗႪ�������B�����z��Ȃ����邽�߁A��V���S�����̏Ǘ���L�x�ł���B���ɂ����āA�V�����A�����z��A�V�����O�Ȃ̕��傪������Ă���B��̕a�@�ł���B
�E���É���w��w�������a�@���Y��q�Z���^�[�F���Y��q�Z���^�[�Ƃ��āA�W�w�I���Y����Â��s���Ă���B�َ��f�f���ꂽ�V�����O�Ȏ����ǗႪ�L�x�ł���A���ɐ�V�����u���w���j�A�Ǘ�͑���������A���т��ǍD�ł���B��_�����f�z���Ö@�A�̊O�����^�l�H�x��p����Ǘ���������A�O���~���̌��C���\�ł���B�܂��A�֘A�{�݂̂܂Ƃߖ�I���݂ł���A�֘A�{�݂���̃f�[�^�Ǘ��A���͂Ȃǂ������Ȃ��Ă���B
�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�V�����ȁF���m�����B��̐V����������p�~�}�Ԃ������A�����O����N�Ԗ�400��̓��@������B����o���̏d���̎��Â��n�ߔ]��̉��Ö@�A�̊O�����^�l�H�x�A�l�H���́A��_�����f�z���Ö@�ȂǐV�����̏W�����Â�S�Ċw�Ԃ��Ƃ��ł���B
�E����s���a�@�A�g���^�L�O�a�@�A���������a�@�F�n��̎��Y���Z���^�[�ł���A����o���̏d�����͂��߂Ƃ���f�Î��т͗D��Ă���B
�E�֘A�a�@���̃f�[�^�[�x�[�X���\�z���A�C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ċ֘A�{�݊Ԃŏ������L���Ă���B����o���̏d���̓o�^�ɂ��ẮA�֘A�{�ݑS�̂ŔN��100��̒���o���̏d���̓��@�o�^������A�Տ������ɂ�����\���ȏǗᐔ���p�ӂ���Ă���B
d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�E���C���Ԃ�3�N��
�E����C�{�݂܂��͎w�茤�C�{�݁E�⊮���C�{�݂Ō��C�ƂȂ�B
�E3�N�Ԃ̌��C���Ԃ̂����A6�����͊�a�@�i���É����ԏ\���a�@�E���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�E��_�s���a�@�j�ł̌��C���`���t�����Ă���B
�@e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�E�����ȏ������C�I����i�����Ȑ���擾��j�ɁA���C�\�Ȏ{�݂ɋΖ������āA���㌤�C���J�n����B���C���A�Œ�6�J���͊�a�@�֕��C���邱�ƂƂ���B
�E�֘A�{�݂Ō��C�Q���\�����āA�����I�Ȍ��C���ł���悤�ɁA�V�������C�v���O���������ŁA�{�݊Ԃɂ����錤�C���e�̈Ⴂ���ɗ͏��Ȃ�����w�͂��s���Ă���B
�����{�����z��w� �������z����㐧�x�������� (http://jspccs.umin.ac.jp/)
���́F���{�z��w�����@
����F��w��F���{�z��w��ihttp://www.j-cire.or.jp/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���A���{�z��w��̔F��{�݂�3�N�A�����6�N
�@�E�z�펾���ɂ���30�Ǘ�B��p�����ƖU��������킹��3��
�@�E�F�莎������
�@�E�i�����S���Ǖa�̊댯���q�ł��邱�Ƃ�F�����A�։��̌[���ɓw�߂����
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F���㐧�x�Ȃ�
�@b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l���F���㐧�x�Ȃ�
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E��_�s���a�@�F�x�b�h����888�Ő��Z�n��40���l�̋~���~�}��ÁA��O����Â�S���Ă���B���Ȃ͏z��A�V�����̈�ɓ������������Ȃ�15����NICU��L���Ă���B��t�͏����z��3�A�V����4�A3�`4�N�ڏ����ȃ��[�e�[�^�[����������\������Ă���B�V������V���S�����̎��ÁA�J�e�[�e�����ÁA�����̕s�����̐f�f�Ȃǂ𒆐S�Ɏ��Y�����獂��҂܂ŏz�펾���ɑΉ����\�ł���B 2005�N�̎��т͏����S�J�e��129�A�J�e�[�e������46�A��V���S������p64�i�J�S�p50�j�ł���B
�E���É����ԏ\���a�@�F���Y���Z���^�[������ׂɁA�َ�������̐S�����̐f�ÂɊւ�邱�Ƃ������A�o���O����̐S�����Ǘ����w�Ԃ��Ƃ��ł���B���̗̈�َ͑��S���a�w�Ƃ��Ĕ��W�r��ł���B�܂��V�����S���̐S�����X�N���[�j���O�G�R�[���s���Ă��邽�߁A�G�R�[�f�f���e�ՂɏK�����邱�Ƃ��ł���B�ܘ_�A�O�Ȏ��Â��s���Ă���̂ŁA�����Őf�f�����S�����̈�т����o�߂𗝉����邱�Ƃ��\�ł���B2005�N���т͏����S�J�e����90�A�J�e�[�e�����Ö�10�A��V���S������p75���ł���B�O�Ȏ��Âɂ��Ă��V�����̎�p����17���A��o���̏d����24����NICU�����邽�ߒ�o���̏d���������A�܂��A�S���ȊO�̎��a�����������q�������̂������Ƃ�����B
�E�����������ی���Ñ����Z���^�[�F2003�N4������S�J�e���p���n�܂�A�J�@�ȗ����Ґ��͏����ɑ������Ă���B2004�N�x�̐S�J�e��228���A�S����p122���A2005�N�x�̐S�J�e��270���i�\��j�S���O�Ȃ̎�p��130���i�\��j�̎��т�����B�S�G�R�[�������N��3000���ȏ�A�z���^�[�S�d�}���N��500�����Ă���B��V���S���������łȂ��s������S�؏ǂȂǂɂ��͂����Ă���A�����z�펾���S�̂���������f�Âł��邱�Ƃ�ڕW�Ƃ���������s���Ă���B�w����������ɍs���悤�ɐS�|���A2005�N�x�A2006�N�x�Ƃ��w��\����50��i�܋������ҁj�A���㔭�\��20�i�܋����j����A�V�m���̐ϋɓI�Ȕ��\���s���Ă���B
�E����a�@�F�Â����珬���S���a���҂ɑ��Ď��g��ł��Ă��邽�߁A�o�߂̒������l�ɒB�������҂��������Ƃ������ł���B���݁A����̉ۑ�ƂȂ鐬�l��V���S�����̊��҂���ɐS���O�ȁA���ȁA�]�O�ȁA�Y�w�l�ȁA���`�O�ȓ��l�X�ȉȂƘA�g���Ď��ÁA�o�ߊώ@�ɓ������Ă���B�܂��A�s�����Ǘ��A�J�e�[�e�����Ó��������Ȃ��Ă���B�S�J�e������50�����x�A��V���S������p15�����x�ł���B
�E�Љ�ی������a�@�F�Ώۊ��҂�8������V���S�����ŁA���Q�������a�A�S�؏ǂȂǂ̌�V���S�����A�s�����Ȃǂł���B�J�݈ȗ����C�n��ő��̎�p���s���Ă���A���݂͔N150��O��̎�p���ł��B�S���J�e�[�e�������͐S�G�R�[��RDCT�̐i���ƂƂ��Ɍ��点�Ă���A���Ă͔N��400��ł��������݂�280��O��ƂȂ����B����ɔ����ăJ�e�[�e�����Ð����������A��N��59��{�s�����B���̎��т���S�[���u�����ǂɑ���J�e�[�e�����É\�̎{�ݔF����A2006�N4���̕ی����ڈȌ�{�i�I�ɊJ�n����\��ł���B�َ����琬�l�܂ł̐����Âɂ��͂�����Ă���A�َ��S�G�R�[��N�Ԗ�20��ɍs���A�Y�ȂƋ��͂������Ɏ��Ñ̐�����邱�Ƃɍv�����Ă���B�N�X�����鐬�l��V���S�����ɂ͐S���O�Ȃ�A�z����ȂȂǂƋ��͂��Đf�Âɂ������Ă���B�Ƃ��ɂ��̕���ő������Ă���A�s�����̃J�e�[�e���ċp�p���\�ɂȂ莡�Âɕ��������Ă����B
�����{��V��ӈُ�w��ihttp://www1.neweb.ne.jp/wa/jikei-ped/jsimd2.html�j
���́F���{�l�ވ�`�w�����
����F��w��F���{�l�ވ�`�w��ihttp://www6.plala.or.jp/jshg/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���s�v�i���W�j
�E���{�l�ޓ`�w��w�肵�����C�{�݁E�֘A�{�݂ɂ�����3�N�ȏ�̗Տ����C
�E��������A��3�N�ȏ�
�E��`��w�ɊW�����M���҂Ƃ��Ă̊w��\�܂��͘_����2�҈ȏ�
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�K��Ȃ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�E����F��{�݁F�K��Ȃ�
�@�@�E����F����֘A�a�@�ɂĊY���҂Ȃ�
�����{�����t���a�w��ihttp://nephron.med.tohoku.ac.jp/jspn/�j
���́F���{�t���w��F���i�����ȁj
����F��w��F���{�t���w�� (http://www.jsn.or.jp/jsn_new/index.html)
�K�v�����F
�E�����Ȑ���ł��邱��
�E5�N�p�������ē��{�t���w��̉���ł��邱��
�E���{�t���w��w�肷�錤�C�{�݂ɂ����Č��C��3�N�ȏ�s���Ă��邱��
�E����̌o���Ǘ�̋L�^�y�їv��̒�o���\�ł��邱��
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�ȔF���F�@
�E�w����1���ȏエ��єF���1���ȏオ��B
�E�g�̏�Q�ҕ����@�̋K��ɂ��X����ÒS����Ë@�ցi�t�@�\��Q�j�Ƃ��Ďw��B
�E��Ö@�Œ�߂����@�\�a�@�A�����a�@�܂��͓��{�t���w��F�߂����͗Ö@�̌��C�{�݂Ƃ��ēK�ȗL���{�݂ł��邱�ƁB
b�j����֘A�ł̔F���F��{�݂ƔF���E�w����̐l��
�@�@�E�F���F��{�݁F�i���{�t���w��F��{�݁j
�@�@�@�@���É���w��w�������a�@�A�����J�Еa�@�A�t����s���a�@�A����s���a�@�A���É����ԏ\���a�@�A���m�������_�Ƒg���A����k�a�@�A���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�A�Љ�ی������a�@�A���ƌ��������ϑg���A�����a�@�A���É��t�ω�a�@�A�g���^�L�O�a�@
�@�@�E�t���w����F
�@�@�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�s�z��v
�E�t������F
�@�@�@�@������w��w�@�@�������B��w�@�@��c�T�i
�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�s�z��v�@�@
�@�@�@�@���É����ԏ\���a�@�@�����ȁ@�@�@���ڐ�ߎq�@
�@�@�@�@�ɓ�s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@����O���@�@�@
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E�Љ�ی������a�@�F�����̐t�s�S�𑽐��ስ���B�t������������B�������͂̃t�H���[�A�b�v�Ǘ�������B
�@�@�E���É����ԏ\���a�@�F�����̐t�������������A�a�@�������Ɋւ��Ă͂R����Ë@�ւɂ����邽�߁A�}�����ɔ����t�����������B
�@d�j�e����F�����擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@�@�����Ȑ�����擾��A���{�t���w��w�肷�錤�C�{�݂ɂ�����3�N�ȏ㌤�C���{�s����B
e�j�e����F�����擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E��w�@�ȊO�̃R�[�X�F�����Ȑ�����擾������ɁA���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���s���B�Ȃ��A���{�t���w��̉������5�N�ȏ�K�v�Ȃ��߁A�t����I�l����ƌ��߂��珬���Ȃ̌�����C���s���Ă��邤���ɓ��{�t���w��ɓ���Ă������Ƃ��]�܂����B
�@�@�E��w�@���w�R�[�X�F�݊w���͌����ɐ�O���A���̌�A���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���J�n���邱�ƂɂȂ�B
�@�@�E�Љ�l��w�@�R�[�X�F���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂ɍݐЂ��Ȃ��猤�����s�����ƂɂȂ�B
�����{����������w��ihttp://edpex104.bcasj.or.jp/jspe/�j
���́F���{������w��@�������Ӊȁi�����ȁj����
����F��w��F���{������w��ihttp://square.umin.ac.jp/endocrine/index.html�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���
�E�p��4�N�ȏ�̉�����A���C����6�N�ȏ�
�E�������ӎ����Տ��Ɋւ���w��\�A���͘_�����\��5�҈ȏ゠��A���Ȃ��Ƃ��@2�҂͕M���҂ł��邱��
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�K��Ȃ�
�����ȂɊւ��ẮA�w���エ��єF�苳��{�݂̐����������Ă��Ȃ��̂ŁA�F��{�݂͓��肵�Ă��Ȃ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�E����F��{�݁F�K��Ȃ��i����20�N�܂Łj
�@�@�E����
�@�@�@�@�������q���N���j�b�N�@�����ȁ@�@�@�X ��
�@�@�@�@�J�������@�\�����J�Еa�@�@�����ȁ@�@���� ��
�@�@�E�w����
�@�@�@�@����N���j�b�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���쐳��
�@�@�@�@�Ȃ��₩���ǂ��N���j�b�N�@�@�@�@�@�@�㞊���i�@
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�@���{������w��F�苳��{�݂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A����4�a�@�ŏ��������厾���̐f�Ái���@�j���s���Ă���B
�@�@�E����s���a�@�����ȁF�b��B�����⏬�l�ǂȂǂ̐f�Â��s���Ă���B
�@�@�E�J�������@�\�����J�Еa�@�����ȁF���A�a���܂߂�����������̐f�ÁB
�@�@�E������ѓc���a�@�����ȁF���l�ǂ̎��Â�B����t�����̐f�Â��s���Ă���B
�@d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@�@�����Ȑ���擾��A3�N�ȏ�̌��C�B�F�肳�ꂽ�ȊO�̎{�݂ł��A�������ӎ����̗Տ��o�����\���ɐς݁A���������ӉȎw����̏��F�̂���ۂɂ͐���̎\�����ł���i����20�N�܂Łj�B
e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�E���ʂȃ��f���R�[�X�͍��̂Ƃ��둶�݂��Ȃ����A��L3�a�@���܂���֘A�a�@�Ő���A�w����ƘA�������Ȃ��珬�������厾���̌o��������̂���̕��@�ƍl������B�S���̂��ǂ��a�@�⑼��w�ŏ�����������w�ԂƂ����I���������肤��i�������w�j�B�܂�������E��`�̊�b�������d�v�ŁA��]������A�������w�������E�������ӕ���i�����v�Y�����j�ł̌������\�ł���B
�@�@�E����20�N�܂łɂ͖��É��s�ŏ��Ȃ��Ƃ���͓�����w��F��{�݂���肽���ƍl���Ă���B
�����{�����S�g��w��ihttp://jisinsin.umin.ac.jp/�j�������Ȃł͐��㐧�x�Ȃ�
���́F���{�S�g��w�����
����F��w��F���{�S�g��w��ihttp://www.interq.or.jp/japan/shinshin/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���s�v�i���W�j�A
�E���{�S�g��w��̔F��{�݂�3�N�A�����3�N
�E�S�g��w�Ɋւ���w��\3��ȏ�A�w�p�_��3�҈ȏ�
�E�w��i�x�����܂ށj�Ŏ�Â����S�g��w��u�K����u
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F 1���ȏ�̎w����
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�E����F��{�݁F�Ȃ�
�@�@�E����F���݂̂Ƃ���֘A�a�@�ł͕s��
e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E���s�ł̓��f���R�[�X�����肷�邱�Ƃ͍���ł���B
�@�@�E�����������ی���Ñ����Z���^�[�ɂēƎ��́u�S�Éȃ��W�f���g���C�v���O�����v������B�v���O�����̏ڍׂ́Ahttp://www.achmc.pref.aichi.jp/5010/5010.html���Q�Ƃ��ꂽ���B
�����{�����Տ��w��@�������Ȃł͐��㐧�x�Ȃ��B
���́F���{�Տ��w�����
����F��w��F���{�Տ��w��ihttp://www.jade.dti.ne.jp/~clinphar/�j
�K�v�����F�����Ȑ���s�v�i���W�j
�����{������`�w��@�@�@
���́F�Տ���`����
����F��w��F���{�l�ވ�`�w��A���{��`��ݾ�ݸފw��ihttp://www6.plala.or.jp/jshg/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ�����擾���Ă��邱�Ƃ��]�܂���
�E���{�l�ވ�`�w��܂��͓��{��`�J�E���Z�����O�w��̉����3�N�ȏ�
�@�E�Տ���`���㐧�x�ψ���̔F��{�݂�3�N���C
�@�E3�N�ԂɈ�`��w�Ɋւ��_�����\2�҂������͊w��\4�K�v
�@�E30��̈�`�Տ��o���̗v��
�@�E��������E�M�L��������
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�@�@
�E�Տ���`����2���ȏ�i����1���͎w����j
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l���i�w����͎Q�l�F���ȁj
�@�@�E���㌤�C�F��{��
���m���S�g��Q�҃R���j�[
�E����F
���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�@�����ȁ@�@�@�@���쐽�i
�@�@�E�w����F
���m���S�g��Q�҃R���j�[���B��Q�������@�@�@�@�@�ᏼ�����i�_�o���ȁj�@
���m���S�g��Q�҃R���j�[���B��Q�������@�@�@�@�@���}���M���i�����w�j
c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�F�R���j�[�����a�@�ł͐��F�ُ̈�̐V�����N��50���A��`�nj�Q���`�������̏Ǘ���L�x�ł���B��`�J�E���Z�����O�͔N�Ԗ�50���̗��K�҂�����A����擾�ɕK�v�ȏǗ�┭�\�ł���Ǘ�͏\�ɂ���B�܂��אڂ��锭�B��Q�������ŕ��q��`�w�A�זE��`�w�̊�b���w�Ԃ��Ƃ��\�ł���B
d�j�e���������擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@�E�����Ȃ̏\���Ȋ�b���C���I���Ă����Ɨǂ��B���C�w��{�݂ɋΖ��ł��Ȃ��ꍇ�͈�`��w�Z�~�i�[�̎Q���ȂǂŎ͉\�ł��邪�A���̏ꍇ�����C�w��{�݂ւ̓o�^�͕K�v�ł���B
�@�@�E3�N�ԂɈ�`��w�Ɋւ��_�����\2�҂������͊w��\4�K�v�B�܂���`�J�E���Z�����O�������͈�`�Տ��̌o���i30��j�̗v�K�v�B��������i��`�J�E���Z�����O���[���v���C�j�ƕM�L����������B
�@�@�E�ȑO�͏����ȁA�Y�w�l�ȊW���啔���ł��������A�ŋ߂͓��ȁA���_�Ȃ̗Տ��オ�������Ă���B�����Ȉ�̌��C���]�܂��B
e�j�e���������擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E���C�J�n�͂����o��A��萔�̈�`��Â̎��т�ςޕK�v������B
�@�@�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�ɋΖ����Ĉ�`��Âɏ]������B
�@�@�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�Ō��C�͂����o��A��`��w�Z�~�i�[�ɖ��N�Q���B�Ǘᐔ�̑����a�@�ŋΖ����A���m���S�g��Q�҃R���j�[���ȂǂŎ��т�ςށB
�@�@�E�������{�݂ɒZ�����w����B
�����{�������m��w��@�@�@
���́F���{���m��w�����
����F��w��F���{���m��w��ihttp://www.jsom.or.jp/html/index.htm�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���A���{���m��w��̔F��{�݂�3�N�A�����3�N
�@�E50�Ǘ�̈ꗗ�y�сA���̂���10�Ǘ�̗Տ���o
�@�E�F�莎���i�M�L�����A��������j����
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�K��Ȃ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�E����F��{�݁F�@�K��Ȃ�
�@�E����F
�@�@�@���������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�R���p��
�L���N���j�b�N�@�@�@�@�@�@�@�L�����V
�����{�����~�}��w��@�������ł͌��݂͐��㐧�x�Ȃ�
���́F���{�~�}��w�����
����F��w��F���{�~�}��w��ihttp://www.jaam.jp/index.htm�j
�K�v�����F
�E��������s�v�i���W�j
�@�E���{�~�}��w��̔F��{�݂ŋ~�}����̐�]��Ƃ���3�N
�@�E�����3�N�A�Տ��o��5�N
�@�E�M�L��������
�����{�������E�}�`�w��@�������ł͐��㐧�x�Ȃ�
���́F���{���E�}�`�w�����
����F��w��F���{���E�}�`�w��ihttp://www.ryumachi-jp.com/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���s�v�i���W�j
�E�F�苳��{�݂ł̗Տ�3�N�A������p��5�N
�B �����Ȋw��̐�啪��ł͂Ȃ����A��������Ɗ֘A���������i�F���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
�����{�Ă�w��@�������E���l�ŋ���
���́F���{�Ă�w��F���i�Տ�����j
����F��w��F���{��w��ihttp://square.umin.ac.jp/jes/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���s�v�i���W�j�A���݂Ă�f�Âɏ]��
�E���{�Ă�w��̌��C�F��{�݂�1�N�A�����5�N
�@�@�E��X�̕a�^���܂�50��̋�̓I�ȃ��X�g����яǗ�ڍL�q5��
�E�Ă�Ɋւ���_���i�����Ƃ��ėՏ��_���B�ŋ�10�N�Ԃ̂���5�ҁA����3�҂͕M�����҂Ƃ��Ă̗Տ��_���j�B
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�ȔF���F�K��Ȃ�
b�j����֘A�ł̔F���F��{�݂ƔF���E�w����̐l��
�E�F���F��{�݁F�w��F��
�E�F���
�@�@�@�@���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�@�����_�o�ȁ@�@�@�O�Y���M
�@�@�@�@���m������������Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����K�O�Y
�@�@�@�@�������z�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H��i�q
�@�@�@�@������w��w�������a�@�@�������@�@�@�@�@ �@�@ �@�������q
���É���w��w�������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@ �@�@ �@�Ė� �~
�@�@�@�@�����a�@�쐶���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�����v
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E���É����ԏ\���a�@�F�Ă�̏Ǘᐔ�͑����B�Ėڐ搶���摜��͂̒m���������Ă���A�������\�ł���B�S�ʓI�ɕ�Ȃ����C�ł���\��������B
�@�@�E����s���a�@�F�Ă�̏Ǘᐔ�͑����A�������d�ςȂǑ����B�]�g��_�o�摜�ɂ��ėՏ��E�����Ŏ��т�����B�S�ʓI�ɕ�Ȃ����C�ł���\��������B
�@�@�E���m�������_�Ƒg���A�������X���a�@�F�Ă�̏Ǘᐔ�͑����B��������Q�̍����ǂƂ��Ă̂Ă�̏Ǘ�������B�]�g��_�o�摜�ɂ��ėՏ��E�����Ŏ��т�����B�S�ʓI�ɕ�Ȃ����C�ł���\��������B
�@�@�E���m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�F�d�x�̏�Q���������A���̍����ǂƂ��Ă̂Ă����B
�@�@�E�����������ی���Ñ����Z���^�[�F�Ă�̏ǗႪ�W�܂����B����͌��C�{�݂Ƃ��ċ@�\�ł���\�����������A���݂͏�X�^�b�t1���ł���A�\���Ȍ��C������ł���B���2���m�ۂł���A��Ȃ����C����̂ɗǂ��{�݂ɂȂ�Ǝv����B
�@d�j�e����F�����擾���邽�߂̉ߒ���擾����
�@�@ �����Ȑ�����擾��A1�N�̔F��{�݂ł̌��C���܂߁A2�`3�N���x���É���w��w�������a�@���A��L�̌��C�ɓK�����a�@�ł̃g���[�j���O���K�v�ł���Ǝv����B�F���擾�Ɋւ��ẮA1�����̕a�@�ł�����x�̊��Ԍ��C����Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ǝv���邪�A�a�@�ɂ��Ǘ�̓��e�ɂ͍������邽�߁A2-3�����̌��C�{�݂Őf�Âɏ]������̂����z�ł��낤�B
e�j�e����F�����擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E��w�@�ɐi�w����ꍇ�F�Œ�1�N�͖��É���w��w�������a�@�ł̗Տ��Ɩ��ɏ]������B�㖱�Ő_�o�O�����p���I�ɒS������B
�E��w�@�ɐi�w���Ȃ��ꍇ�F��L���C�ɓK�����a�@��2�`3�N���C���邩�A���É���w��w�������a�@�ň���Ƃ��ėՏ��Ɩ����s���B
�@�@�E������ɂ���A�w���ł����t��K���ȕa�@�ɔz�u���邱�Ƃ��K�v�ł���B�_�o�������Ƃ��Ă�NICU�̂���a�@���ׂĂɎw���͂̂����t���Œ�1�l�A�ł���Ε����z�u�������B������z�u���闝�R�́A�_�o�����̐f�Âɂ����Ă͕����̖ڂŌ��ċq�ϐ��E�Ó������m�ۂ���K�v�����邩��ł���B�]�g�̔��ǂЂƂ��Ƃ��Ă��A1�l�ōs���Ă���ƕ肪�ł��Ă��܂��͔̂������Ȃ��B
�����{�Տ��_�o�����w��@�������E���l�ŋ���
���́F���{�Տ��_�o�����w��F���ihttp://square.umin.ac.jp/JSCN/�j
����F��w��F���{�Տ��_�o�����w��
�K�v�����F
�E�Տ��o����5�N�ȏ�i�����Տ����C���Ԃ�2�N�Ԃ��܂ށj
�E���{�Տ��_�o�����w��������3�N�ȏ�L���邱��
�@�@�E�]�g���邢�͋ؓd�}�E�_�o�`���̗Տ��I�����E�����f�f��3�N�ȏ�]�������o����������
�E���{�Տ��_�o�����w���Â̊w�p�W��A�Z�p�u�K���ъ֘A�u�K��A�܂��͊֘A�w��ւ̎Q����2��ȏ゠�邱��
�E�F�茤�C�{�݂��邢�͔F��ψ���݂Ƃ߂錤���{�݂ɂ�����1�N�ȏ�̌��C����L���邱��
���́F���{���͈�w�����
����F��w��F���{���͈�w��ihttp://www.jsdt.or.jp/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���ł��邱��
�E3�N�ȏ�p���������{���͈�w��̉���ł��邱��
�E���{���͈�w��F��{�݁E����֘A�{�݂ɂ�����3�N�ȏ�A���{���͈�w��C�J���L�������Ɋ�Â������͗Ö@�Ɋւ���Տ����C���I�����Ă��邱��
�E�f�Î��тƂ��āA����̌o���Ǘ�̋L�^�y�їv��̒�o���\�ł��邱��
�E�����ƐтƂ��āA���{���͈�w��N���w�p�W��ւ̎Q����1��ȏ�A�M���҂Ƃ��Ă̌��t�@�Ɋւ��锭�\1���ȏ�A����ь����i�M���҂łȂ��Ă悢�j1�҈ȏオ�K�v�ł���
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�w����1���ȏエ��ѐ���1���ȏオ���
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�E���{���͈�w�����F
�@�@�@�@�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�s�z��v
�E���{���͈�w��w����F
�@�@�@�@�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�s�z��v
�@c�j����֘A�a�@���Ƃ̓���
�@�@�E�Љ�ی������a�@�F���l�̈�ł͌��t���͏Ǘᐔ�͔��ɑ����B�����ł͕������͂𒆐S�ɓ��͈�Â��s���Ă���B
e�j�e����F�����擾���鐧�x���\�z�����ł̍l�����郂�f���R�[�X
�@�@�E��w�@�ȊO�̃R�[�X�F�����Ȑ�����擾������ɁA���{���͈�w��F��{�݁E����֘A�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���s���B
�@�@�E��w�@���w�R�[�X�F�݊w���͌����ɐ�O���A���̌�A���{���͈�w��F��{�݁E����֘A�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���J�n���邱�ƂɂȂ�B
�@�@�E�Љ�l��w�@�R�[�X�F���{���͈�w��F��{�݁E����֘A�{�݂ɍݐЂ��Ȃ��猤�����s�����ƂɂȂ�B
��ICD���x���c��i���{���������NJw��Ȃ�16�w��E������ō\���j��
���́FICD�iInfection Control Doctor�j
�F��g�D�FICD���x���c���ihttp://www.icd.umin.jp/�j
�K�v�����F
���L��3������S�Ė������ꍇ�AICD�iInfection Control Doctor�j�ɉ��傪�\�ł���BICD�F��ψ����3���������Ă��邱�Ƃ��m�F���A���c�ICD�Ƃ��ĔF�肷��B
�A���c��ɉ������Ă��邢���ꂩ�̊w��̉���ł��邱�ƁB
�B��t����5�N�ȏ�̈�t�܂��͔��m�����擾��5�N�ȏ��PhD�ŁA�a�@������ɌW��銈�����сi���L1�`3�j������A�����{�ݒ��̐��E�����邱�ƁB
�i1�j������ψ��܂��͂���ɏ����銈���̏ؖ������邱��
�i2�j�C���t�F�N�V�����R ���g���[���Ɋ֘A�����w��\���͘_���v3�҂����邱��
�i3�j�{���c��̎�� ����u�K��܂��͌����J���Ȃ̈ϑ��ɂ��@��������u�K��ւ̎Q�����т�3��ȏ゠�邱��
�C�����w���̐��E�����邱�ƁB
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F�K��Ȃ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�@�@�EICD�iInfection Control Doctor�j�F
���É���w��w�@�E�C���X�w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؑ� �G
���m�������_�Ƒg���A����a�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@���藲�j�A�������q
���S�a�@�@�\�h�ڎ�Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�Ì��L
�Љ�ی������a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ēc����
�g���^�L�O�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،ː^��
��{�s�������s���a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �G
���c�ی��q����w�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���쑢
�i�䏬���N���j�b�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�� �G
�ԓc���ǂ��N���j�b�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԓc����
���É����M�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q
�s�����c�a�@�@�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ؗ��j
�����{�Տ���ᇊw��@��2006�N�x�ɑ�P����㎎�����J��
���́F����Ö@����
����F��w��F���{�Տ���ᇊw��ihttp://jsmo.umin.jp/�j
�K�v�����F
�E�����Ȑ���
�@�E�w��F��̌��C�{�݂ɂ�2�N�̗Տ����C
�E���ÂɊւ��錤������5�N�A���ÂɊւ���Ɛ�
�E���{�Տ���ᇊw��̉����2�N
a�j��匤�C�F��{�݂ɕK�v�Ȑ���F
�E�b��w����2���A�܂��́A�b��w����1���Ɛ���1���̏��
�E���ː����Ñ��u�A�{��IRB�A�a���w��F��a������̋Ζ�
�E������ᇊ��҂��펞20���ȏ���@�A�N�Ԃ���̖Ö@��50��ȏ�
b�j����֘A�ł̐���F��{�݂Ɛ���E�w����̐l��
�E����F��{�݁F�i���{�Տ���ᇊw��F��̖��召���Ȋ֘A�a�@�j
�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�i�����ȂƂ��Ă͍����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�̂݁j�A�Љ�ی������a�@�A���������a�@�A���É��t�ω�a�@
�E����F
�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�@������ �@�@�@�@�@�x���h�O
�E�b��w����F
�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�@������ �@�@�@�@�@�x���h�O
VIII. �T�u�X�y�V�����e�B�[�Z�\�K���ɂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
�����Ȍ��C�I����i�����Ȑ���擾��j�ɂ́A�����Ȃ̒��̊e��啪��T�u�X�y�V�����e�B�[�̋Z�\�K�����\�ł���B�T�u�X�y�V�����e�B�[�̋Z�\���K��������@�ɂ͑傫�������āA��ʑ�w�@�R�[�X�A�Љ�l��w�@�R�[�X�A����擾��ڕW�Ƃ������C�R�[�X������B����ɂ���ĈقȂ邪�A��w�@�R�[�X�ł����̊Ԃɐ��̗Տ��o����ςނ��ƂŊe����̐�����擾���邱�Ƃ��\�ł���B����ɍ����A���O�ւ̗��w���\�ł���B�g�ɂ������Z�\�́A�֘A�a�@�̐��f�Â��w�̋����Ƃ��Đ�������Ă������ƂɂȂ�B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
�]���̑�w�@�ɓ��w����R�[�X�ł���B��w�@�ɍݐЂ��Č������s���B��b�������ɂ����錤���⍑�����w�����Č������s�����Ƃ��w�������Ƃ̑��k�ʼn\�ȏꍇ������B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
���܂ł̘_�����m�ɑ���R�[�X�ł���B�֘A�a�@�Ζ����w���Έ���Ƃ��ē����Ȃ����w�@�ɓ��w����B1�N�ȓ��Ƃ͂Ȃ邪�����ɐ�O������Ԃ��w�������Ƃ̑��k�ōl�������B
�R�j����擾��ڕW�Ƃ�����w�@�ȊO�̌��C�R�[�X
�֘A�a�@�ɋΖ����Ȃ�����エ��ѐ��Z�\�擾��ڎw���R�[�X�ł���B�֘A�a�@�ɂ����f�Â�K�v�Ƃ��銳�҂���͑����A�e����̐������������B
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 �N |
|
��w�@�R�[�X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���C�� |
������ |
��w �a�@ |
���� ���C |
��w�@ |
|
||||||
|
�Љ�l��w�@�R�[�X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
���C�� |
������ |
��w �a�@ |
���� ���C |
�Љ�l��w�@ |
|
|
|||||
|
��w�@�ȊO�̃R�[�X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
���C�� |
������ |
��w �a�@ |
���� ���C |
���㌤�C |
|
|
|
||||
�e����̃T�u�X�y�V�����e�B�[�Z�\���K������ɂ́A���ꂼ�����Ƃ���w���҂Ƒ��k�����āA�����悭���C������K�v������B�e��啪��̃��f���R�[�X�Ȃǂɂ��Ă͎��ňȍ~�Ɏ����B
���t��ᇐ������̎��Î{�݂́A�S���I�ɂ���w�����a�@�⏬���a�@�Ȃǂ̐��{�݂Ɍ��肳��Ă���A���É���w�����Ȃ̊֘A�ɂ����Ă��A���É���w��w�������a�@�A���É����ԏ\���a�@�A���É���ÃZ���^�[������ɂ�����B���t��ᇊw�̓����Ƃ��āA���q�����w��Ɖu�w�Ȃǂ̊�b��w�̗������A�Տ��ɒ������邱�Ƃ���A��ʁA�Љ�l�R�[�X���킸�A��w�@�ɐi�w����̂��]�܂����B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
����a�@���C���I����A��L��2�{�݂��邢�́C���̊֘A�a�@�ɂ�����0.5�`1�N�Ԃ̌��C���I����A��w�@�ɓ��w����B����̊֘A�a�@�O�Ō��C���A��w�@���w����]����ꍇ�̓��w�����́A�{�l�̊�]�ɉ����B��w�@���w��́A����܂ł̌��t��ᇐ������̐f�Ìo���ɉ����āA0.5�`1�N�ԁA�������זE�ڐA�̐f�Ìo�����܂߁A��啪��̐f�Âɏ]������B�㔼��3�N�Ԃ́A�a���A�O���Ɩ��͖Ə��Ō����ɐ�O����B��w�a�@�ɍݐВ��̗Տ��o���ŁA�f�Î��т������Ƃ͏\���\�ł��邱�Ƃ���A�w�ʂƐ�����Ɏ擾���邱�Ƃ��߂����B��w�@���ƌ�́A���{�݂ł̐f�Âɏ]������ق��A�C�O���w�A���{�݂ł̌o�����ւāA�����⌤���E�ւ̓����J�����B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
�Љ�l��w�@�̓��w�����́A−�ʑ�w�@���w�R�[�X�Ɠ��l�ł���B���É���w��w�������a�@�ɂ����ẮA���Έ���̃|�X�g�邱�Ƃ��ł���B���É����ԏ\���a�@�A���É���ÃZ���^�[�Ń|�X�g������A�Ђ��������܂܁A��w�@�ɓ��w���邱�Ƃ��\�ł���B�܂��A�����������A3�{�݂����[�e�[�g���邱�Ƃ����肤��B���É���w��w�������a�@�ł́A��ʑ�w�@�R�[�X�Ɠ��l�Ɏ�X�̃Z�~�i�[���͂��߁A����I�@��^������B�܂������Ƃ��āA�a���̐f�Âɏ]�����邪�A4�N�Ԃ̂����A���̊��Ԃ͌����ɐ�O���邱�Ƃ��l������B��w�@�ݐВ��̐f�Ìo�������ƂɊw�ʘ_�����쐬����ƂƂ��ɁA�\���Ȑf�Î��т������邱�Ƃ���A����̎擾���\�ł���B��w�@�C����́A���{�݂ł̐f�Âɏ]������ق��A��含�������������Ȉ�Ƃ��Ēn���Âɏ]�����铹���J����Ă���B�܂��A�{�l�̊�]�ɂ���Ă͈�ʑ�w�@�R�[�X�Ɠ��l�ɁA�C�O���w��A�����ւ̓����J����Ă���B
�����A�����M�[����ɂȂ邽�߂ɂ́A�A�����M�[�w�ɑ��鋭���S�Ɛ��I�m���������A�A�����M�[�Տ��̌o���Ǝ��т�����A���������ŃA�����M�[�����̐f�Â��s���\�͂�g�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\����ς���Ƃ���ƁA�A�����M�[�O���͂قƂ�ǂ̕a�@�⏬���Ȑf�Ï��ɊJ�݂���Ă��邪�A���������őO������̎�ɕ����Ȃ��Ǘ�̑��k�ɉ�����\�͂����߂���B�܂��A���̕���ł͌o����`�I�Ŕ�Ȋw�I�Ȑf�f�⎡�Ẩ����t�������s���Ă���A����͏����L�����W���邾���łȂ��A�d���ȖƉu�w�E�A�����M�[�w�I�f�{�Łu�K�Z�l�^�v��r������͗ʂ����X�������B����͖{�l���g�̖��ł���Ɠ����ɁA���ӂɂ���������ÓI�n�����͂т���Ȃ��悤�A����҂Ƃ��Ă̖��������߂���B�����ŁA�����A�����M�[���R�[�X�ł́A�������Ƃ��֘A�a�@�ŃA�����M�[�����̎��Âɂ����邱�Ƃ���R�[�X�ɉ����邱�Ƃ������A�ł����1�N�ԁA�����A�����M�[���{�݂ŏW�����ėՏ����C���s�����Ƃ𐄏�����B���̏�ŁA�Ɖu�w�E�A�����M�[�w�̐��I�m�������邽�߂ɑ�w�@�Ȃǂ�2�N�ԁA�A�����M�[�����ɎQ�����邱�Ƃ��ł���x�X�g�ł���B���R�[�X�͑��l�ł����Ă������A�Ƃ肠�����A3�R�[�X�����B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
4�N�Ԃ̂�����1�N�Ԃ������A�����M�[���Տ����C�ɂ��Ă邱�Ƃ��]�܂����B���C���\�Ȏ{�݂́A�֘A�a�@���ł͂����������ی���Ñ����Z���^�[�݂̂ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͑����ւ̍������C���K�v�ȏꍇ������i��w�͋����P�����̐f�ËK�͂ł���A���C�����������Ă��Ȃ��j�B�c��3�N�Ԃ̂���2�N�Ԃ̓A�����M�[�����ɎQ������B�����\�͂̔��A�V����̊J��̂��߂ɂ͍����O�ւ̗��w�����߂���B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
��w�ɂ̓A�����M�[�f�Â̂��߂̔��Έ���̃|�X�g���Ȃ��A��w�ŗՏ����C�����Ȃ��猤���ɂ��Q������Ƃ����w���R�[�X�͐ݒ�ł��Ȃ��B�����������ی���Ñ����Z���^�[�ɐg���i���W�f���g�j��u���A�傢�ɓw�͂��A�����Ԃ��w�Ɍ����ɒʂ�������R�[�X�͉\��������Ȃ��B�܂��A���m���擾������ړI�Ƃ���A��ʊ֘A�a�@�������I�ɑ�w�Ɍ����ɒʂ����Ƃ��\�ŁA��w���̃X�^�b�t�ɂ�錤����̃T�|�[�g�͍s���B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
��ʏ����Ȍ��C���I��������A���݂₩��2�N�Ԃ̏����A�����M�[���Տ����C�ɓ���B���̏ꍇ�A�f�ËK�͂�g���ۏ�Ȃǂ��l������ƁA����ɂӂ��킵�����C�{�݂͊֘A�a�@���ɂ͂Ȃ��A�����ÃZ���^�[�⍑���a�@�@�\�����a�@�Ȃǂւ̍������C���K�v�ƂȂ�B�������A�A�����M�[�w�̊�b�I�Ȑ��m���̏C���ɕs��������A���̍����̂��ߌl�I�ȓw�͂����߂���B�ő�̍���͈�ǂ̐l�I�����̕s���ł���A�����Ɍ����ĔS�苭��������K�v������B
�E�C���X�����Ɖu�Ɛ[���������̂��鏬�������NJw��ɂ͓Ǝ��̐��㐧�x�͂Ȃ��B�����NJw��F�肷����㐧�x�͂��邪�A��Ƃ��ē��Ȋ����Lj�ΏۂƂ��Ă���A�擾���Ă��鏬���Ȉ�͏��Ȃ��B����AInfection Control Doctor�iICD�j�͐���ł͂Ȃ����A�a�@���̊�����Ɩ����s��������Infection Control Team (ICT)�Ƃ��Ċ�������̂ɋ��߂��鎑�i�ł���A�擾�����߂���BICD�ɂ͏��������Ǖ���ɂ����āA�E�C���X�����ǂ݂̂Ȃ炸�A�ۊ����ǂ��܂߂����L���m�����v�������B�܂��A�E�C���X�����ǂ́A���ɕ��̍L�������ł��邽�߁A���̎����̐��O���[�v�⑼�ȂƂ̘A�g���������Ȃ�����ł���B����āA���I�Ȏ��Î�Z�͎����Ȃ���������Ȃ����A����̏�͍L���B�E�C���X�������@���ɐ�����̂��A�Ȃ����̐f�f�@��p����̂��A�ǂ����Ă��̎��Â�K�p����̂��A�Ȃǂ̗Տ��I�^��ɑΉ����邽�߂ɂ́A�����Ɖu�̊�b�I���������ɏd�v�ƍl����B�����A�����Ɖu�����ɐ�O�������Ƃ����҂͂������̂��ƁA�D�G�ȗՏ����ڎw���҂ɂ����A���q�����w��זE�����w�E�Ɖu�w�Ȃǂ̊�b�I�����͗L�p�ł���B����āA��w�@�ɐi�w�������Ԋ�b�I�������邱�ƑE�߂Ă���B��ʑ�w�@�E�Љ�l��w�@�A������̃R�[�X���\�ł���B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
����a�@���C���I����ł�����ł��悢�B���É���w��w�������Ȃ݂̂Ȃ炸�A�֘A�����{�݂ł��鈤�m������Z���^�[��ᇖƉu���A���É���w��w�@�������Ɖu�w�u���ɂĂ̌������\�ł���B��w�@���ƌ�́A�ϋɓI�ɊC�O���w�����サ�Ă���B���Ȃ݂ɃE�C���X�������ł́A����16�N�Ԃ�14���̑�w�@�����C���������A����8�����C�O���w���Ă���B8����5���������@�ցE�{�݂ŋ����������͕����Ƃ��ē����A2���͌��ݗ��w���ł���B�܂��A���I�m���E�o�������Ċ����ǗՏ��ɏ]�����邠�邢�͗Տ��������s���ȂǕ��L�����������Ă���B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
���w�����͈�ʑ�w�@�R�[�X�Ɠ��l�ł���B�E�C���X�������֘A�Տ��{�݁i�����������ی���Ñ����Z���^�[�����Ɖu�ȂȂǁj�ŗՏ��ɏ]�����Ȃ���A�Տ��E�C���X�w�������s���B�����ԁi���Ȃ��Ƃ�1�N�ԁj�͂����ꂩ�̌����{�݂Ŋ�b�I�������s�����Ƃ��]�܂����B
�����_�o�����͂�����a�@�̓��@���҂����O���ɂ����Čo�����邪�A�ڂ��������_�o�w���w�Ԃ��߂ɂ͖��É���w�a�@���{�݂ł��閼�É����ԏ\���a�@�A����X���a�@�A����s���a�@�A�����������ی���Ñ����Z���^�[�ȂǁA����ɂ͏�Q������ɐf�Â��鈤�m���R���j�[�A������ÃZ���^�[�ɂ����āA�w���҂̂��ƂŌo����ςނ��Ƃ��]�܂����B����a�@���C�I����͑傫�������Ĉȉ���3�̃��f���R�[�X���l������B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
��w�@���Ƃ��Ė��É���w�Ő�匤�C�A�������J�n����ꍇ�A�ŏ���1�N�Ԃ͑�w�̐_�o�O������ѓ��@���҂̐f�Âɏ]�����邱�ƂŁA�����_�o�w�̗Տ��o����ς����̏������s���B�������ɔ]�g���ǂȂǂ̐��Z�\�K�����s���B���̌�͗Տ��Ɩ���Ə����ꌤ���ɐ�O���邱�Ƃ��ł��邪�A�Տ������Ɋ֘A����O����a���Ɩ����p�����邱�Ƃ���]����ꍇ�͌p�����\�ł���B�܂��w�O�̌����{�݂Ō������s�����Ƃ��\�ł���B���݁A����̐����w�������ɂ�����_�o�����w�I�����A���m���R���j�[���B��Q�������╟����w�ŏ����_�o�����̈�`�q�������s���Ă���҂�����B�����_�o�w�����擾�̂��߂̗Տ��o���͑�w�@���ɂ��ςނ��Ƃ��\�ł���B���ƌ�͊�a�@����{�݂ł̐f�ÁA���O���w���\�ł���B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
�Љ�l��w�@�ɓ��w�����ꍇ�A��w�̈���Ƃ��āA�܂��͊֘A�a�@�ɋΖ��������_�o�Տ����C���s���Ȃ����w�@���Ƃ��ėՏ��������s���B�O�����֘A�a�@�A�㔼���w�ň���Ƃ��ċΖ����邱�Ƃ��\�ł���B�֘A�a�@�ɋΖ�����ꍇ�A�\�ł���Ώ����_�o�̎w���҂̂����a�@�ŗՏ��������s�����Ƃ��l������B�������܂Ƃ߂邽��1�N�ȉ��̌����ɐ�O������Ԃ��l�������B�P�j�̃R�[�X�Ɠ��l�ɐ���擾�̂��߂̗Տ��o����ςނ��Ƃ��\�ł���B����͂P�j�Ɠ��l�Ɋ�a�@����{�݂ł̐f�ÁA���O���w�Ȃǂ��\�ł���B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
�w�ʂ�������̎擾�Ɏ���u�����R�[�X�ł���B��w�̔��Έ���Ƃ��āA�܂��͊֘A�a�@�ɋΖ��������_�o�̗Տ����C���s���Ȃ�����{�����_�o�w�����擾��ڎw���B������擾�ɂ��A������5�N�ȏ�̉�����A�Ǘ�v��A�w��o�Ȃ┭�\�A�_�����M�A�����Ȋw��ȂNJ�{�̈�̊w��̐���Ȃǂ��K�v�ł��邪�A�����͑�w�a�@���a�@�ł̐f�ÁA���C�Ŏ擾�\�ł���B������̃R�[�X���A�Ă�̐f�ÁA�������s�����{�Ă�w��̔F���i�Տ�����j���擾���邱�Ƃ��L�p�ł���B
���Y������i�V�����j�͏����Ȑ���擾��Ɍ��C���J�n���邱�Ƃ��ł��邽�߁A��w�a�@���C�I����ɑ��₩�ɏ����Ȑ�����擾���邱�Ƃ��]�܂����B���Y������i�V�����j�̌��C���Ԃ�3�N�ł���A���̂���6�����͊�{�݂ł̌��C���`���Â����Ă���B���É���w�����Ȋ֘A�{�݂ł́A���É����ԏ\���a�@�A��_�s���a�@�A����X���a�@�����Y������i�V�����j�̌��C�ɂ������{�݂ł���B�c��͊�{�݂܂��͎w��{�݂Ō��C���s���B���É���w�����Ȋ֘A�{�݂̌��C�w��{�݂́A���É���w��w�������a�@�A���������a�@�A�g���^�L�O�a�@�A����s���a�@�A���m���R���j�[�����a�@�ł���B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
��{�I�ɕa���Ɩ��͍s�킸�ɁA�����ɐ�O���邪�A���㌤�C���J�n����Ӗ��ŁA��w�@4�N�Ԃ̒��ōŌ��0.5�`1.0�N�Ԃ́A���ԓ��̕a���Ζ����s�����ƂƂ���B��w�@�C��͊֘A�̌��C�{�݂ֈٓ������āA���C���p������B��w�@�C����ɁA�����O�̌����{�݂ł̌�������]����ꍇ�́A���w��D��Ƃ��āA���w��Ɍ��C�̍ĊJ���l������B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
�w��̎w�肷�錤�C�{�݂ɐЂ�u���Ȃ���A���É���w�V�����֘A�{�����l�b�g���[�N�iNU-NRN�j�̃V�X�e���Ɋ�Â��A�Տ��������J�n����B��{�I�ɑ�w�@4�N���ŁA��w�ɐЂ��ڂ��āA�����̂܂Ƃ߂��s�����ƂƂ���B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
��w�a�@���C�I����܂��͏������C��i�����Ȑ���擾��j�Ɋw��̎w�肷�錤�C��{�݁A���C�w��{�݂ֈٓ������A���C���J�n����B
�P�j��ʑ�w�@���w�R�[�X
�������Ɖu�s�S�nj�Q�̗����̂��߂ɂ͊�b�Ɖu�w�̒m�����K�{�ł��邱�ƁB�����̐f�f�A�a�ԉ𖾂��s�Ȃ����߂ɂ͍זE�����w�I�A���q�����w�I�����Z�p�̏C�����K�v�ł��邱�ƁB�H�Ȏ����ł���A�قƂ�ǂ̏ǗႪ��w�ɏW�ς��Ă��邱�ƂȂǂ����w�@���w�ɂ��m���A�Z�\���K�����邱�Ƃ��������߂�B��w�@���ƌ�͊�]�ɂ��C�O���w���\�ł���B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
��L���R�ɂ���w�@�ȊO�̃R�[�X�͊�{�I�ɂ͊��߂Ȃ��B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
��L���R�ɂ���w�@�ȊO�̃R�[�X�͊�{�I�ɂ͊��߂Ȃ��B
�P�j��ʑ�w�@�R�[�X
�Տ���̎��_���d�v�ł����w�@4�N�Ԃ̂���6�����`1�N�Ԃ����ԓ����a���Ɩ��͍s�����̂Ƃ���B�֘A�O�{�݂ł̌�������]����ꍇ���̖ړI�ȂǂƏƂ炵���킹�ċ����邱�Ƃ������Ƃ���B��w�@�C����͊֘A�̐��{�݂ֈٓ����Č��C���p������B��w�@�C����̍����O�ł̌����̊�]������ꍇ�����k�ɉ�����B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
�֘A�̐��{�݂ɂ����Č��C���s���Ȃ���Տ��������J�n����B���r�Ŗ�2�N��w�@�ɐЂ��ڂ��Č����̂܂Ƃ߂��s���B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
��w�a�@���C�I����܂��͏������C��Ɋ֘A�̐��{�݂ł̌��C���s���B
�P�ɏ����̐t�E�A�H�����݂̂łȂ��A�L���t�E�A�H�̐����E�a�ԂɊւ���m�����K�v�ƂȂ�B�̉t�i���E�d�����j�A�������i�������߁j�A�����t�s�S�i�ۑ������܂ށj�A�}���t�s�S�A���͗Ö@�A�t�ڐA�Ȃǂ��d�v�Ȏ����ł���B�X�ɂ́A���l�̐t�����i���A�ɐt�ǂ▌���t�ǂȂǁj�ɑ����ʓI�Ȓm�����K�v�ł��邪�A�w��⌤����ւ̎Q���Ȃǂɂ���ďK���\�ł���B���s���āi�قړ������Ɂj���{���͈�w�������擾���邽�߂̌��C���A�ݐЂ��錤�C�{�݂ɂ���Ă͉\�ł���B
�P�j��ʑ�w�@���w�R�[�X
�@�@�݊w���͌����ɐ�O���A���̌�A���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���J�n���邱�ƂɂȂ�B
�Q�j�Љ�l��w�@�R�[�X
�@�@���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂ɍݐЂ��Ȃ��猤�����s�����ƂɂȂ�B
�R�j��w�@�ȊO�̃R�[�X
�@�@�����Ȑ�����擾������ɁA���{�t���w��̎w�肷�錤�C�{�݂�3�N�Ԃ̌��C���s���B�Ȃ��A���{�t���w��̑S�_����5�N�ȏ�K�v�ł��邽�߁A�t�����U����ƌ��߂��珬���Ȃ̌�����C���s���Ă��邤���ɓ��{�t���w��֓���Ă������Ƃ��]�܂����B
��w�ɋ����̂��Ȃ�����ł͌��C�͔��ɍ���ł���B��V��ӈُ�ǂɋ����������ꂽ���ɂ́A���q��`�w�I�����̉\�ȍ������{�݂Ō��C���s�����ƂɂȂ�B
���C�J�n�͂����o��A��萔�̈�`�f�Â̌o����ςނ��Ƃ��K�{�ł���B���f���R�[�X�Ƃ��Ă͏Ǘᐔ�̑����a�@�i��Ɉ��m���S�g��Q�҃R���j�[�����a�@�j�Őf�Â̎��т�ςޗՏ����S�̃R�[�X�ƁA��w�@�ŕ��q��`�w�I�����ɏ]�����Ȃ�����ŗՏ��o����ςޕ��@�ɑ�ʂ����B
�P�j���m���S�g��Q�҃R���j�[�ɋΖ����ėՏ���`�f�Âɏ]������B
�Q�j���m���S�g��Q�҃R���j�[�Ō��C�͂����o��A��`��w�Z�~�i�[�ɎQ�����ă|�C���g�����߂Ȃ���Ǘᐔ�̑����a�@�ŋΖ�����B
�R�j��`��������ΏۂƂ��鑼�̃O���[�v�̌����ɏ]�����Ȃ���A���s���ăR���j�[�Ō��C�͂����o���A��`��w�Z�~�i�[�ɖ��N�Q�����ă|�C���g�𑝂₵�A�Ǘᐔ�̑����a�@�Ŕ��ŋΖ�����B��`��������ΏۂƂ��鑼�O���[�v�Ō������s���Ȃ���Տ���`������擾���邱�Ƃ͏\���\�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()